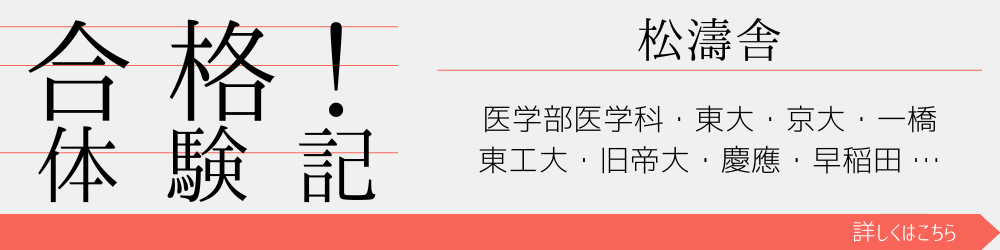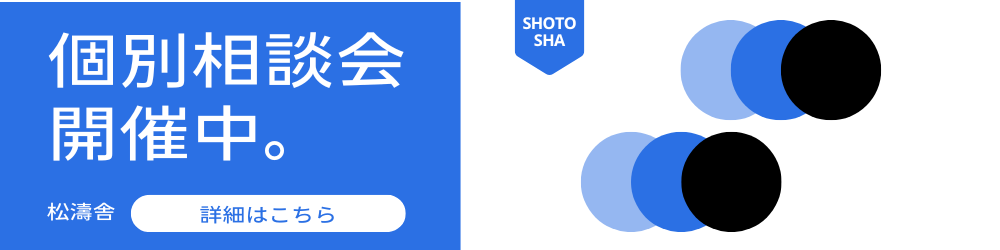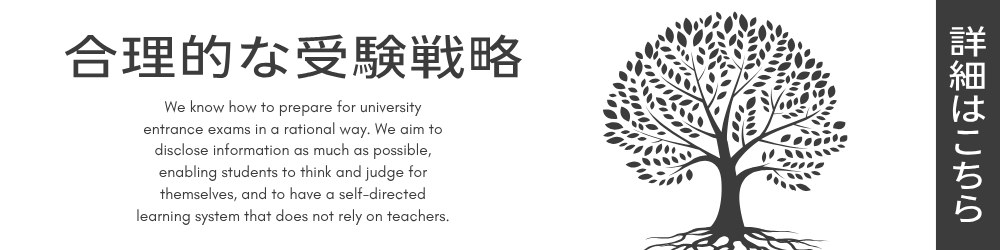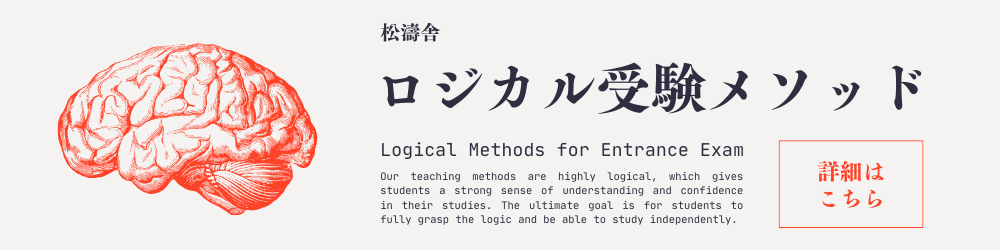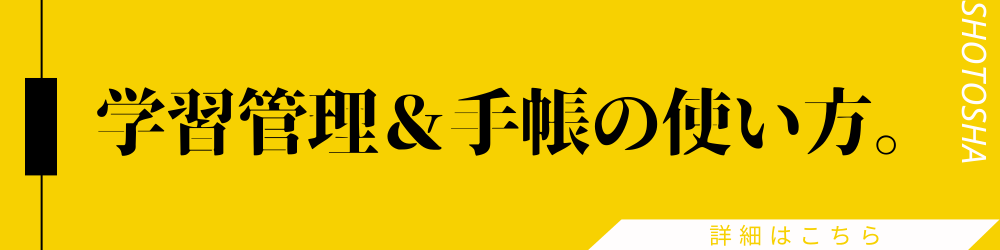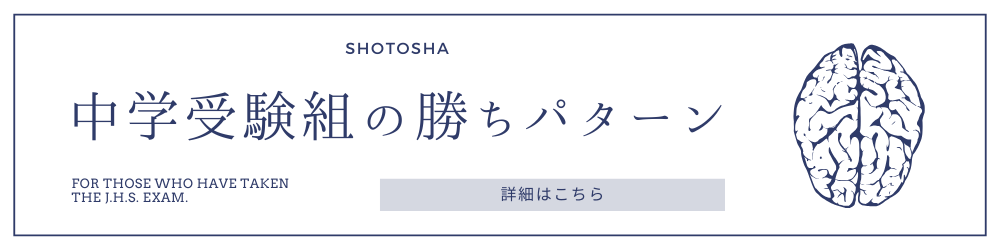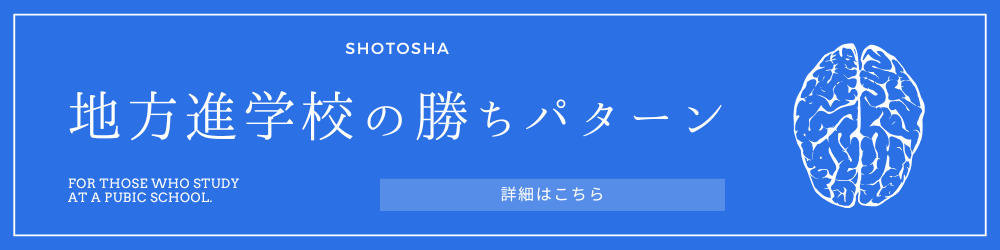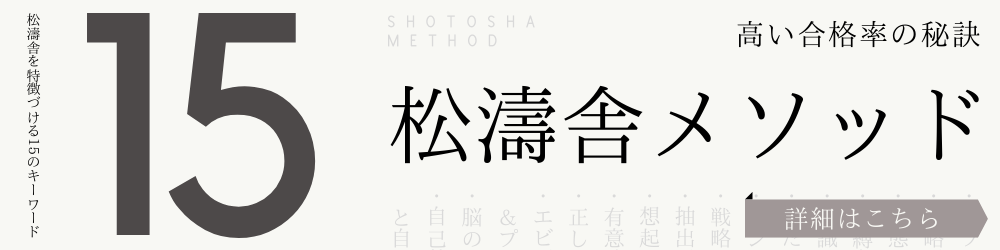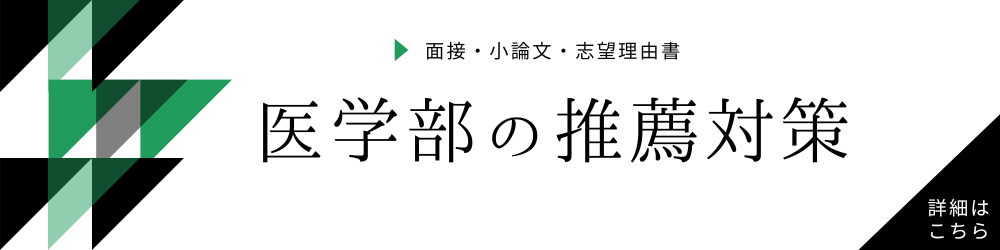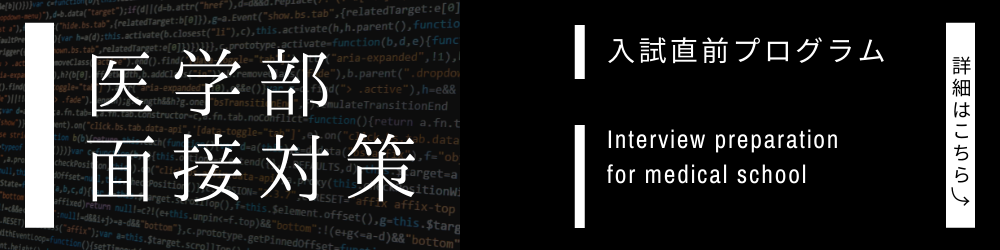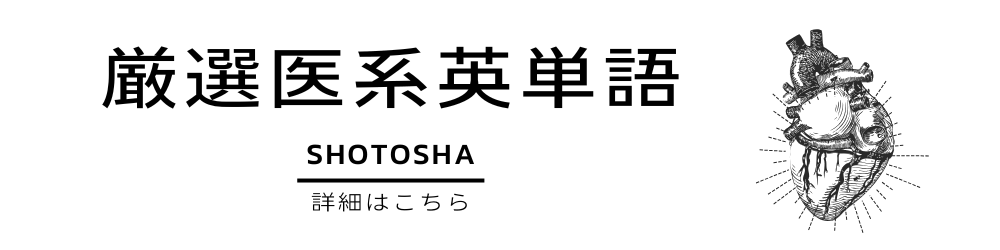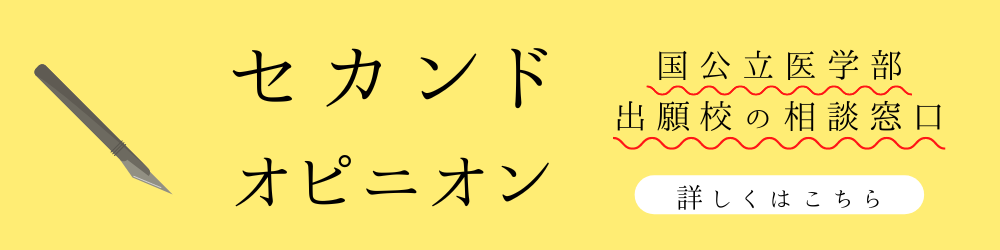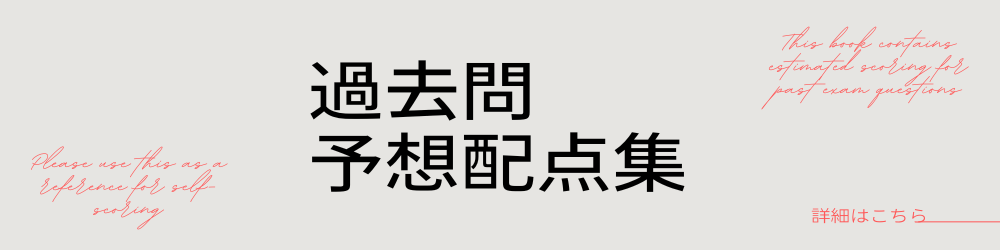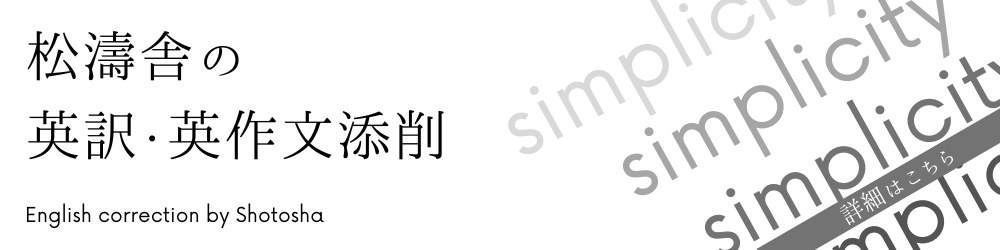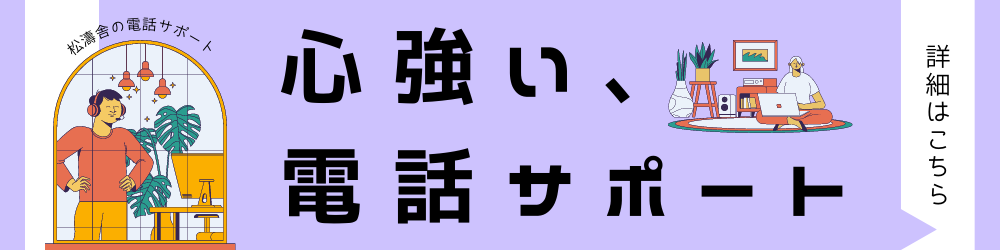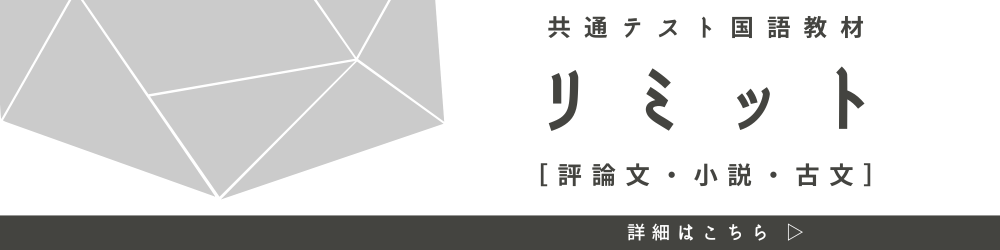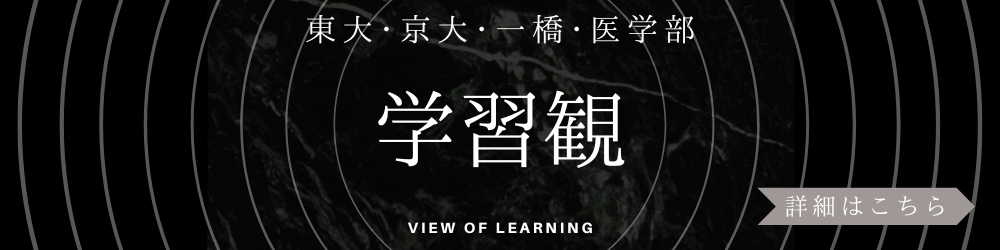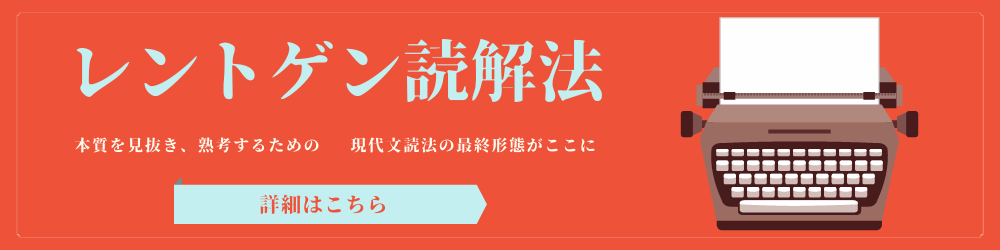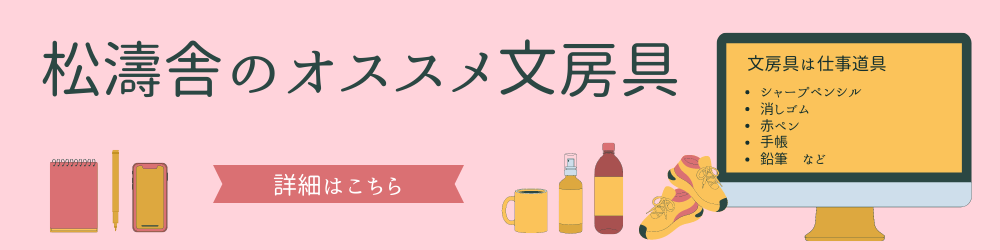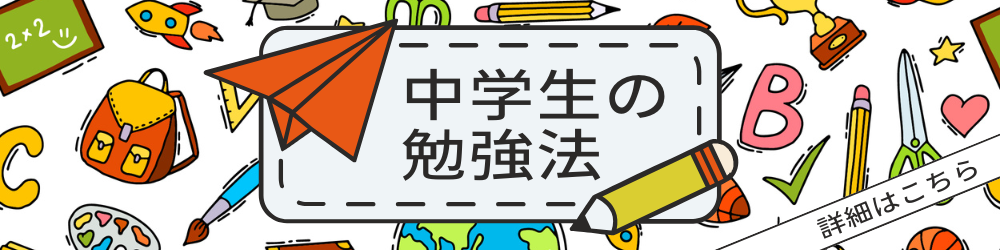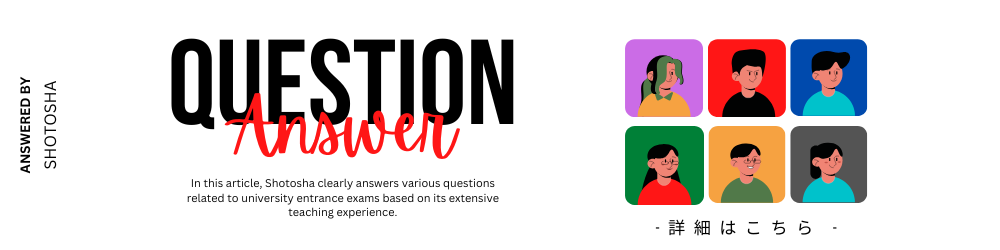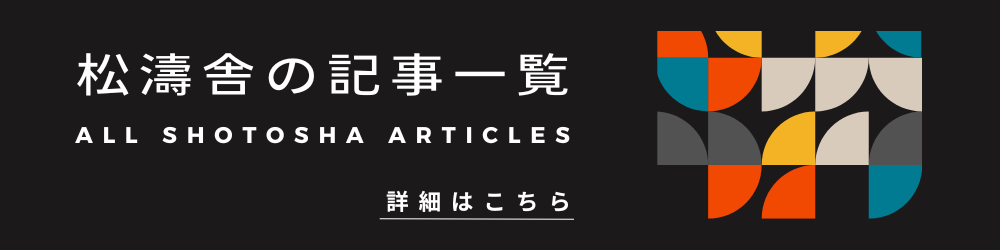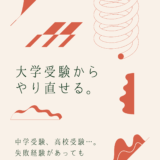目次
- はじめに
- 多読多聴で「意味想起プロセス」を自動化する
- リスニングは「負荷を高めた英文読解」
- 多読多聴量と語彙量が、英語の成績を決める
- 多読多聴量や語彙量は、学校や塾では不足しがち
- 「日本語を介さずに理解できる状態」を目指す
- 英語長文を日本語に訳して読んでしまう主要因3つ
- 英単語をコアイメージで覚えよう
- 英文法もニュアンスを掴もう
- 長文問題は簡素化と長文化が進んでいる
- 多読多聴の正しいやり方
- 日本語訳をしていたら読解スピードに限界が来る
- 長文のレベルは簡単なものから始めるのがポイント
- 多読多聴におすすめの教材とは?
- 多読多聴の効用:自然な英文和訳が書ける
- 多読多聴の注意点
- まとめ
- お問い合わせフォーム
はじめに
大学受験の英語は、長文問題が配点の約6~7割を占めます。
そんな長文対策で必要不可欠なのが多読多聴です。
多読多聴とはその名の通り、たくさん読み、たくさん聴くことです。多くの人が、その重要性にまだ気づいていなかったり、気づきつつも出来ていなかったり、間違えた方法で行うせいで効果が出ず、継続しないといったケースが多いです。
この記事では多読多聴の重要性の重要性やメカニズムに触れた上で、正しいやり方や注意点についてご紹介していきます。
多読多聴で「意味想起プロセス」を自動化する
多読多聴は、英文読解プロセスにおける、英単語の「意味想起プロセスの自動化」に寄与します。
いくら英単語を知っていても、スピーディーに英単語の意味が想起できなければ、英文を読むのが遅くなったり、それまで書かれていた英文の内容を忘れてしまって読み返す、といった事態に陥ってしまいます。
英単語の意味を高速で想起しながら、次々と英単語を読んでいくプロセスに、多読多聴が必要なのです。
リスニングは「負荷を高めた英文読解」
多読だけでなく、多読多聴である(=リスニングをする)理由は2つあります。
1つは、リスニングは黙読と比べて負荷が高いからです。
「英語の語順のまま、ナチュラルスピードで(=日本語を介す余裕がないスピードで)、流れていく」ので、英語を英語のまま読まざるを得ません。黙読だと、どうして返り読みしてしまったり、読解スピードが遅いにも関わらず問題ないと思ってしまいがちです。リスニングはいわば「負荷を高めた英文読解」なのです。長文を読むのが難しい移動時間中や隙間時間にも、聴くだけで長文読解したことになるので非常に手軽でもあります。
もう1つリスニングをやるは、共通テストのリスニング対策です。共通テストからR(リーディング)と同じ配点になり、L(リスニング)の重要性が格段に高まりました。そのため、リスニング対策は当然のように必要なのです。
多読多聴量と語彙量が、英語の成績を決める
ここで、多読多聴と同じくらい重要な英単語暗記にも触れておきたいと思います。
先述の通り、多読多聴は「意味想起プロセスの自動化」に寄与するのですが、これはつまり「十分な語彙量がある」ことが前提になっています。英単語を知らなければ、想起も何もありません。
よって、多読多聴と英単語暗記は、セットで必要なのです。
①十分な英単語を覚え、②想起をスピーディーに行うが2つ揃ってはじめて速読できるようになるのです。
英語の成績は、多読多聴量と語彙量でほぼ決まります。多読多聴に入る前に、語彙量が不足していないか確認が必要です。
多読多聴量や語彙量は、学校や塾では不足しがち
多読多聴量と語彙量は、ただ学校に行ったり塾に通うだけでは絶対的に不足します。
まず、学校ではほぼ多読多聴をしません。やるのは専ら「全訳(=全英文の日本語訳)」という、「英語は日本語に訳して理解するもの」「英語は、構造解析し、返り読みしながら読むもの」といった間違った英語観に繋がるような指導がなされています。英単語暗記も、小テストを出す学校が多いですが、小テストは短期記憶にしかならないですし、1冊の英単語帳をやるだけでは、特に医学部・上位校受験には不足します。
英語塾も同じようなものです。週1回1長文しか読まない、しかも2~3時間かけて解説するといった、量も足りなければ効率も悪い学習をすることになります。
多読多聴は、毎日1~2長文読むことを意味します。長文のレベルは、可能な限り全英単語を知っている、比較的短いもので十分です。
例えば、松濤舎では「180~260words/CEFR B1=中学〜高1教科書+少し上レベル」くらいの英語長文を毎日配信しているのですが、この程度で十分です(具体的な英文は後ほど紹介します)
英単語は、毎日180語をテスト形式で進めてください。1語10秒で進められるので、1日30分あればOKです。英単語暗記は、質より量が大事であることが科学的に知られているため、分散学習しながら、とにかくぐるぐる回せばOKです。
英単語暗記については以下の記事を参考にしてみてください。
「日本語を介さずに理解できる状態」を目指す
多読多聴した先にある状態ゴールは、日本語を介さずに、英語を英語のまま理解できている状態です。
英語を日本語を介さずに理解できている状態が、想像できない人も多いでしょう。
しかし、実は皆さんも、簡単な英文ではできているのです。
例えば、次の英文を日本語介さずに読み、情景を想像することができるか試してみてください。
Two children are practicing soccer on the school ground.
できますよね。これくらい簡単な英文なら、わざわざchildren を「子ども」に、school を「学校」に変換しなくても、情景が目に浮かんだはずです。これが、英語を英語のまま理解できている状態です。
この状態が、英単語の難易度が高い英文でもできるようになるのが、多読多聴のゴールです。
多読多聴をやる上で最も重要なのは「日本語に変換する回路をシャットダウンする」ことが重要です。
多読多聴をする際は、唯一、これさえ注意していれば問題ないと言ってもよいでしょう。
どうしても日本語に訳して読んでしまうのであれば、それはシンプルに、読んでいる英文(英単語)の難易度が高すぎるからです。先ほどの簡単な英文では、日本語を介さず理解できたのですから。
英語を習い始めた小学校や中学校では、1つ1つの英単語を日本語に変換しなければ理解できませんでした。しかし、それを繰り返している、うちにいつの間にか簡単な英文であれば日本語に訳さなくても理解できる状態になり、最終的にはほとんどの英単語を日本語に訳さなくても理解できるようになっていくのが理想です。
いつまでも小学校や中学校でやっていたような「英語→日本語→理解」をやらないようにしましょう。
英語長文を日本語に訳して読んでしまう主要因3つ
要因①|語彙量の不足
語彙量が不足していると、1つ1つの英単語で躓いてしまいます。その際に「この英単語の意味(=日本語)ってなんだったっけ?」と日本語を想起する回路を使ってしまうことになります。これでは、英語を英語のまま読むことはできません。
多読多聴と英単語暗記はセットです。
松濤舎でも、英語の課題作成では語彙量と多読多聴量の足並みを揃えています。
なお、語彙量を増やす際に意識していただきたいのは、コアイメージも覚えることです。
単に、一語一義でたくさんの英単語の意味を覚えても効果が薄いです。
一語一義で覚えると、「英単語→日本語→意味」というプロセスを経なければならなくなるからです。
どれだけの英単語のコアイメージを暗記できたかが重要です。コアイメージが覚えられれば、わざわざ英語を日本語に変えずに「こんな感じの意味」で処理していけるため、「英語→理解」というプロセスが可能になります(詳しくは後述します)
要因②|長文レベルがあっていない
英語長文を日本語に訳して読んでしまうのは、長文レベルが難しすぎる可能性があります。
後ほど紹介しますが、「180~260words/CEFR B1=中学〜高1教科書+少し上レベル」の英語長文で十分です。実際、この難易度の英文でも、英語を英語のまま理解できない人が多いのではないかと思っています。先ほど紹介した、
Two children are practicing soccer on the school ground.
くらいの難易度でいいので、とにかく「英語を英語のまま理解できるレベルの英語長文」をたくさん読むことです。
東大英語で8割以上取得している松濤舎スタッフは、海外の小学生レベルの絵本から多読多聴をスタートしていました。そのレベルから読むので、英語を英語のまま読めている状態から徐々に難易度を上げていくことができ、最終的に大学受験レベルの英文を英語のまま理解できるのです。
面白いのが、その過程で少しずつ語彙量も増えていくということです。「英語長文は語彙の宝庫である」という英語観を持っており、多読多聴することで語彙量も勝手に増えていくのです。まさに多読多聴は最強の英語学習と言えるでしょう。
要因③|トレーニングが足りていない
十分な語彙量を覚え、難易度の低い英文を選べているのであれば、あとはトレーニングを積むのみです。
最初はどうしても「英語→日本語→理解」という回路を使ってしまうものです。ですが、「英語→日本語」の回路を意識してシャットダウンし、「英語→理解」の回路のみを使うことを意識してみてください。
いつの間にか「今読んでるとき、日本語のこと考えてなかった」となる時がきます。そうなったらOKです。
英単語をコアイメージで覚えよう
「英単語の意味は日本語で覚えているのだから、日本語を介さず読むなんてできない」
と思う人も多いでしょうが、それは、英単語を暗記する時点で間違えている可能性が高いです。
そもそも、英単語と日本語は1対1対応するものではありません。
例えば、play を「遊ぶ」という日本語と1対1対応しているわけではありません。
それは、play に「演奏する」という意味もあるからということでもありません。1対N対応するものでもないのです。
実は、play には、「何かに参加し、楽しむ」というコアイメージがあります。ネイティブはそのような意味でplay を読み取っていると考えてください。英語を英語のまま理解するには、play をそういう意味を持った記号として読み進めていくのです。
I play seccer. ・・・私は、参加して楽しむ、サッカーを
I play the guitar. ・・・私は、参加して楽しむ、ギターを
といった感じです。長文読解する際は、このようにコアイメージで読んでいけば十分です。
「和訳しなさい」と言われた場合にだけ、文脈に応じて「遊ぶ」と訳したり、「演奏する」と訳すだけなのです。
この「コアイメージで読んでいく」は、やっていて非常に楽しいです。日本語に訳すのは大きな負荷がかかり、ストレスを感じやすいです。「どうせ日本語訳するのであれば、最初から日本語の文章を読んだ方がいい」と思うようになります。
しかし、英語を英語のまま理解することで、英語にしか表現できないニュアンスがあることを知ったりと、楽しさを感じられるようになります。その結果、英語長文を読むのが楽しくなり、習慣化し、成績が上がる、という好循環に入っていきます。
推奨教材(詳細は後述します)
英文法もニュアンスを掴もう
英単語に加え、英文法もニュアンスを掴むと、日本語を介さないスピーディーな読解に繋がります。
例えば、must という助動詞には「内側から強く湧き出る、避けられない必然性」というコアイメージがあります。
高校では、must に「義務」「推量」「禁止」といった用法があると習いますが、そんなものは覚えなくても、コアイメージさえ掴めていれば英語は理解できるのです。例えば、次のようにです。
You must study for the exam. ・・・あなたには、必然性がある、勉強をする、試験のために
He must be tired. ・・・あなたには、内側から強く湧き出ている、疲れが
You must not use your phone during the class. ・・・あなたは、必然的にしてはいけない、使うことを、携帯を、授業中に
このように、文法もコアイメージさえ知っていれば、英語を英語のままスピーディーに処理していくことができます。決してmust に「義務」「推量」「禁止」といった意味や用法があるのではありません。これは日本人がmust を無理やり日本語に訳す場合、この3つの訳し方をすると自然になることが多いため、便宜的に分類しているだけなのです。
注意点があるとしたら、大学受験の和訳問題では、この「義務・推量・禁止」といった用法がわかっていることをアピールする必要もあるということです。よって、和訳問題ではある程度、これらのニュアンスを明示的に盛り込む必要があります。
推奨教材(詳細は後述します)
長文問題は簡素化と長文化が進んでいる
長文問題は、どんどん簡素化・長文化が進んでいます。
過去には300~500 words の長文問題が主流で複雑な英文を和訳させるような出題が多かったのですが、近年は500~1000over wordsの長文問題が主流となってきており、平易な超長文の要点を、短時間でスピーディーに把握する能力が求められるようになりました。
ここからも、多読多聴を通した日本語を介さないスピーディーな情報処理能力の構築が必要なことが理解いただけるのではないかと思います。
多読多聴の正しいやり方
これまでの内容を踏まえて、具体的な多読多聴の方法を記載します。
まずはリスニングをします。3回聴いてわからなければ英文とスクリプトを確認しましょう。
「意味のわからない英語を読んだり、聴いたりしても、英語能力は上がらない」ということが科学的に知られています。よって、一つの目安ではありますが、3回で切り上げましょう。
次に、音源を聴きながら、英文を見ながらでいいので音読をします。これをパラレルリーディングと言います。シャドウイングが英文を見ないのに対して、パラレルリーディングは見てOKです。パラレルリーディングを行うことで、音韻処理(=心の中で英文を音読する過程)を自動化し、日本語を介さずスピーディーに理解することに繋がります。
音源のスピードで読んでいくので、ナチュラルスピードで読むことのなり、理想の読解スピードも掴めます。
最後に黙読をします。STEP1でスクリプトを確認してすでに内容がわかっているということもありますが、日本語を介さずに理解できている状態になっているはずです。この状態で英文を読むことが重要です。日本語を介さずに「英語→理解」の回路を強化することができます。
日本語訳をしていたら読解スピードに限界が来る
日本語を介する読み方をいくら極めても、英語を英語のまま理解するスピードには勝りません。
多読多聴を「よりスピーディーに日本語訳していくこと」と思ってトレーニングをしても全く意味がありません。その先に「英語を英語のまま理解する状態」はありません。
長文のレベルは簡単なものから始めるのがポイント
多読多聴で使用する教材は簡単なものであるべきと繰り返しお伝えしてきましたが、具体的にはどれくらいのレベルでしょうか。例えば、松濤舎が生徒に毎日配信している英語長文(ライト版)は「180~260words/CEFR B1=中学〜高1教科書+少し上レベル」で、以下の難易度の英語長文となっています。
〈テーマ〉
Canada’s Ice Hotel and Eco Design(氷で作るエコホテル カナダ)
〈英文〉
In the heart of Quebec, Canada, there exists a fascinating hotel called the Hôtel de Glace. Opened in 2001, this unique hotel is made entirely of ice and snow. Each year, it is rebuilt with a new design, offering a fresh experience for its guests. The Hôtel de Glace is not only a marvel of architecture but also an example of eco-friendly design. Since the hotel is made from natural materials, it has a low impact on the environment. The ice and snow used for its construction eventually melt back into the river, causing no harm to nature.
One of the most interesting aspects of the Hôtel de Glace is its artistic rooms. Artists from around the world come to create stunning ice sculptures that decorate the hotel. Guests can sleep on beds made of ice, covered with cozy sleeping bags to keep them warm. You might wonder if it’s too cold, but the hotel maintains a temperature of around -3°C to -5°C, which is quite comfortable with the right clothing.
The Hôtel de Glace is a perfect blend of art and sustainability (eco-friendliness). It provides a unique experience that attracts thousands of visitors each year, proving that luxury can go hand in hand with caring for our planet. (209 words)
〈和文〉
カナダのケベック州の中心に、氷と雪でできたユニークなホテル「Hôtel de Glace」があります。このホテルは2001年にオープンし、毎年新しいデザインで再建され、訪れる人々に新鮮な体験を提供しています。Hôtel de Glaceは建築の驚異であると同時に、環境に優しいデザインの一例でもあります。ホテルは天然素材で作られているため環境への影響が少ないです。建設に使われた氷と雪は最終的に川に溶け込み、自然に害を与えません。
Hôtel de Glaceの最も興味深い点の一つは、その芸術的な部屋です。世界中のアーティストが集まり、美しい氷の彫刻でホテルを飾ります。宿泊客は氷でできたベッドで眠り、暖かい寝袋で保温します。寒すぎるのではと思うかもしれませんが、ホテルは約-3°Cから-5°Cの温度を保っていて、適切な服装をしていればかなり快適です。
Hôtel de Glaceはアートと持続可能性(エコフレンドリー)を完璧に融合させています。このホテルは、毎年何千人もの訪問者を引き付け、贅沢と地球への配慮が両立できることを証明しています。
(松濤舎「毎日英語・ライト版」より抜粋)
このレベルの英文から始めるのが非常に重要です。このレベルでも、英語を英語のまま理解するのが難儀だと感じた人の方が多いくらいでしょう。難しい英文(≒語彙レベルの高い英文)は、すぐに詰まってしまい、日本語を使う回路を使ってしまうので背伸びするのは厳禁です。
簡単な英文から、徐々にレベルを上げていくようにしましょう。
多読多聴におすすめの教材とは?
多読多聴におすすめの教材は以下となります。いずれも松濤舎の指定教材です。
速読英単語シリーズ
定番の速読シリーズです。特に「入門編」「熟語」から始めることがポイントです。無理なく、英語を英語のまま理解できる英文からはじめましょう。
やっておきたい英語長文シリーズ
新版になって音源がつきました。長文問題が解けることに加え、音源もついているため多読多聴ができ、収録長文数も比較的多いという、コストパフォーマンスに優れた教材になっています。
VENN4000
医学部・上位校受験に必要十分な語彙量が収録された英単語帳です。書く英単語にはなるべく多くの意味が掲載されており、コアイメージが掴みやすくなっています。①高い網羅性、②コアイメージが掴める、という特徴から、語彙不足が原因の失点が限りなくゼロになる英単語帳といえます。
総合英語 FACTBOOK
ネイティブの感覚やコアイメージで英文法を解説する唯一無二の英文法書です。文法問題集と並行して読み進めることで自然と英文法のニュアンスが掴めるようになります。英文法を、速読に繋がります。
多読多聴の効用:自然な英文和訳が書ける
「多読多聴(速読)」と「英文和訳(精読や構造解析)」は対極にあるものだと勘違いしている人が多いです。
英文和訳は、多読多聴して英語を英語のまま理解できるようになれば自然とできるようになるもの。詳しくは以下の記事をご覧ください。
多読多聴の注意点
日本語を介する回路をシャットダウンする
とにかくこれを意識しましょう。
日本語を介した多読多聴をいくらしても無意味です。
まずは、日本語を介さずとも理解できる難易度の英文から始めることです。そこから徐々にレベルを上げていきましょう。
英単語や英文法のコアイメージを掴んでおく
英単語や英文法のコアイメージを知らなければ、英語を英語のまま理解するのは難しいです。
英単語を一語一義で覚えているうちは英語のまま理解できないので、ニュアンスを掴む勉強をしましょう。
松濤舎の推奨教材を選べばまず問題ありません。
全訳しない
「英語長文を全訳(=全文和訳)する」授業を行なっている学校や塾は多いですが、いくらやっても英語長文の成績は上がりません。「英語→日本語→理解」というプロセスを経ていては、読解スピードが遅い状態ですぐに頭打ちしてしまいます。
日本語を介すと、認知容量も大幅に消費してしまい、読んだ内容を保持したり、次の展開を予想したりする認知活動も制限されてしまいます。
まとめ
多読多聴は、英単語暗記と並ぶ、英語学習の「二大柱」です。
その効用、正しいやり方、おすすめ教材、注意点について、長年の現場指導を踏まえて記載しました。特に、医学部・上位校受験生には参考になったはずです。
多読多聴を日々の学習に取り入れ、医学部・上位校合格を果たしてください。
お問い合わせフォーム
こちらからもお問い合わせいただけます。