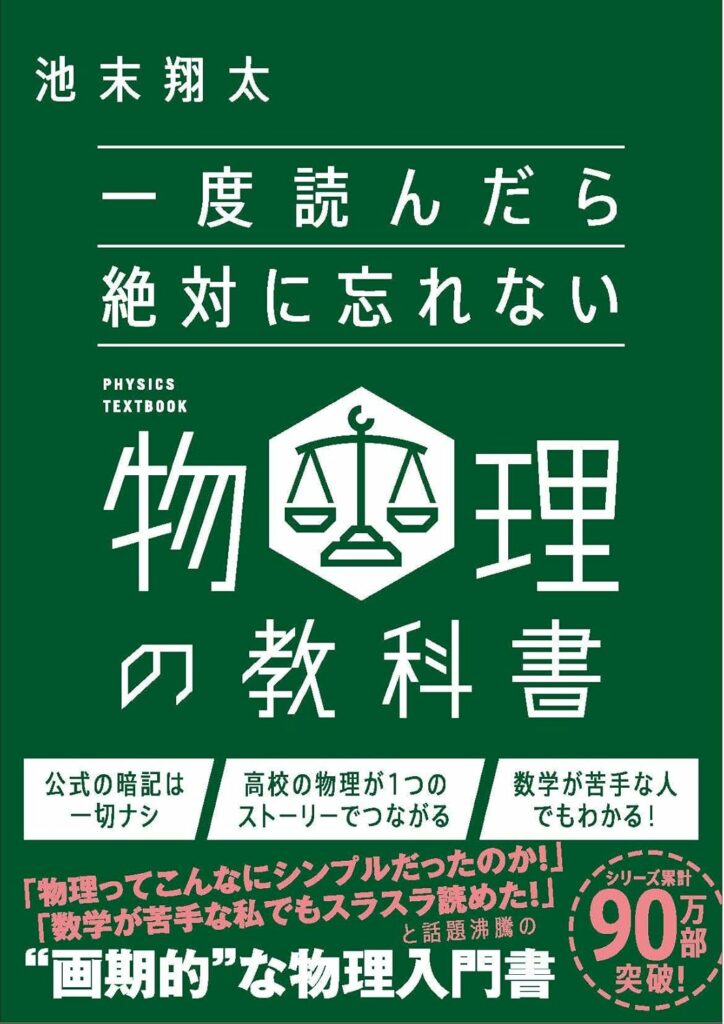[推奨]松濤舎の指定問題集です。
目次
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』で合格可能な医学部・上位校
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』で取得可能な偏差値
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の習得レベル(+到達可能な偏差値)
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の使い方
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の1周目、2周目…の役割
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の習得にかかる時間
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』のスケジュール
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の特徴
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の欠点
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の補助教材
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』が指定教材の理由
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の前にやるべき参考書
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の後にやるべき参考書
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』と並行すべき参考書
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の位置づけと役割
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』と代替可能な参考書
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の対象者
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』を購入するタイミング
- 物理の完全攻略法
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』と同じカテゴリーの参考書
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』と他書の比較
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の目次/問題数
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』に関するQ&A
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』で合格可能な医学部・上位校
松濤舎での合格実績を以下に記載します。
・医学部医学科
大阪大学、東京科学大学、千葉大学、横浜市立大学、筑波大学、広島大学、金沢大学、新潟大学、熊本大学、信州大学、岐阜大学、浜松医科大学、鳥取大学、愛媛大学、大分大学、福島県立医科大学、群馬大学、高知大学、宮崎大学、香川大学、富山大学、弘前大学、秋田大学、慶應義塾大学、東京慈恵会医科大学、順天堂大学、日本医科大学、国際医療福祉大学、自治医科大学、昭和大学、東京医科大学、東邦大学、日本大学、聖マリアンナ医科大学、東海大学、帝京大学、東京女子医科大学、埼玉医科大学 ほか
・他学部
東京大学、京都大学、大阪大学、名古屋大学、北海道大学、東北大学、一橋大学、神戸大学、慶應義塾大学、早稲田大学 ほか
※代替可能な問題集を使った合格実績も含む。
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』で取得可能な偏差値
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』は読み物のため、取得可能な偏差値はありません。ただし、本書を読むことで後続の学習が非常にスムーズになるため、1冊目の参考書として指定教材にしています。
*全統記述模試(河合塾)の偏差値
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の習得レベル(+到達可能な偏差値)
レベル1:一読した。
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の使い方
難しいことは考えず、冒頭から順に読んでいけばOKです。気になる分野やテーマがあったら先にそこから読んでもいいですが、力学をベースに話が典型しているため、時間もそこまでかからないですし、冒頭から読んでいくことをオススメします。
高校物理の全体感や各テーマの関連性、ストーリーなどを掴むことができます。
公式の見え方や捉え方が変わるだけ、その後の学習に大きな差が生まれるのです。
「なるほど!」と思った箇所にはドッグイヤーをつけておきましょう。2回目に読みたくなったとき、ドッグイヤーをつけた箇所だけを読むと非常に効率的です。
本書は読み物系の参考書なので、何度も繰り返し読んで知識を頭に入れるようなものではありませんが、問題集を解き進める過程で迷子になったり、引いて見ることができなくなることがあります。そういったときは本書に戻って改めて読んでみると、知識の点と点がつながったり、腹落ちしたりすることがあります。
1冊目の参考書として読んでもらいたいのですが、それだけで終わりにせず、例えば模試の前には全体を一読してみるとよいでしょう。意外と1周目にさらっと読み飛ばしていたところも、後から読んでみるととても大事だったと気づくことがあります。
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の1周目、2周目…の役割
1周目の役割
1周目は全体感を掴んだり、テーマごとの関連性を把握することが目的です。物理とはどのような学問で、何がすごい発見で、それゆえにどんなことを学んでいくのか、といったことを掴み、学ぶ下地をつくります。
2周目以降の役割
2周目以降は、問題集で学習を進めながら、頭の整理をしたり、改めて俯瞰して見る際に役立つ参考書になります。また、学ぶ前はさらっと流していたところが、意外と勉強が進んだ後だと大事なことに気づいて・・・ということも多々あります。
「初学者向けの簡単な読み物」で片付けず、「最後まで共にする相棒」という位置付けにしましょう。
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の習得にかかる時間
通読の所要時間:3時間(=約250ページ、1見開き1~2分として)
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』のスケジュール
あらゆる物理の参考書、問題集の前に読む参考書になります。例えば、力学を習う前に力学の章を一読する、といった使い方です。スケジュールというほどではありませんが、学習前に読むことで迷子にならず、何を勉強しているのか、何に注意して勉強していったらいいかを掴んだ上で進めていくことができます。
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の特徴
物理を1つのストーリーで串刺し、全体観が持ちやすい
本書は「高校物理とは、物体(粒子)が関与しているというモデル(仮説)をつくることが根底にある」というストーリーで記述されています。そのため、まずは力学を勉強し、力学の言葉で熱や波、電磁気について解説しようと試みる、という流れで解説されています。このように、物理全体に共通することが書かれていると、勉強しやすいですよね。
学ぶ目的を書いてくれているため、理解しやすい
例えば、力学は「物体の運動論を完全に記述すること」が目的であり、では何がわかると運動について理解できたと言えるかというと「物体の位置を時刻の関数として求めることができたとき」と言ってます。そして、加速度を求めれば速度、位置が得られることを示し、運動方程式が成り立つことから、物体にかかる力を求めることが重要だという流れになっています。
このように説明されると、なぜ力の図示が必要なのかがよくわかりますよね。
さらに、力が一定でない運動に出くわしたら、仕事やエネルギー、力積や運動量について立式したらいい、という話になっていきます。学ぶ目的がわかれば、当該テーマで何が大事なのかがわかり、何に注意して勉強したらいいかが明確になります。
原理と定理の違いを説明してくれている
物理の教科書には多数の公式のようなものが載っていますが、それは原理なのか、定理なのか、覚えるべきなのか導出できるものなのか、きちんと書かれていません。その結果、、いつ使ったらいいかもわからないまま、ただ公式暗記を進めていくことになります。本書では「こういう関係が成り立っているということは受け入れないといけないもの」と「その原理から導き出されるもの」を分けていたり、仕事やエネルギーを「名前を後付けしているものにすぎない」と説明してくれたりしています。このような説明があると、どのように解釈したらいいかに迷うことがありません。
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の欠点
導入としては非常に優れています。何度も読み返したり、問題集を進めた上でたまに戻ってくると発見も多いでしょう。
欠点を挙げるとしたら、入試で使うテーマをすべて扱っているわけではない点です。これは導入用としては仕方のないところです。また、もう少し端的に表現できる部分もあるように感じます。その分、情報密度を上げ、見開き1ページに主要な情報がまとまっていると使いやすいように思います(複数ページにまたがって書かれている場合、自分で情報の集約を行わなければならないため)
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の補助教材
松濤舎では本書の補助教材は用意してありませんが、書かれている内容を端的にまとめ、追記したような資料があれば、復習に最適だと思います。
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』が指定教材の理由
物理は「意図」を持って学ばないと、数学のようなパターン認識では対応できないフェーズがやってきます。そのテーマを学ぶ目的は何か、それを踏まえて何に注意しないといけないのか、その操作をする意義は何か、それを踏まえてどういったことを問われるのか・・・こういったことが根底にないと非常に勉強がしづらく、そして勉強していても苦痛になるのです。本書はこういった根本の根本について補足してくれる、非常に優れた教材です。
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の前にやるべき参考書
特にありません。本書を1冊目の参考書として使用しましょう。
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の後にやるべき参考書
実際に問題演習に入りましょう。松濤舎では、学校指定の教科書傍用問題集(なければ『エクセル物理』(実教出版))と『宇宙一わかりやすい高校物理』を使って、実際に問題を解いたり、躓いたら参考書を読んで進めるようにしています。
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』と並行すべき参考書
単なる読み物なので並行すべき参考書はありませんが、今後問題集を使いながら都度本書に戻ると、頭の整理になっていいでしょう。
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の位置づけと役割
物理全体の見通しを持ったり、学ぶ意義を理解したり、それゆえに当該テーマのポイントを掴んだりすることで、スムーズなスタートを切ることが本書の役割です。物理はどうしてもポンポンと新しい公式やテーマが出てきて、どうしてそれを学ばないといけないのか、それをどう解釈したらいいのか、というところに時間がかかってしまいます。パズル的に楽しめる人ならいいですが、楽しめるようになるまでのスパンが非常に長いのが物理の特徴です。
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』と代替可能な参考書
上記のような役割を担う参考書がないため、大体可能な参考書はありません。
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の対象者
すべての物理選択者におすすめです。初学者向けに思うかもしれませんが、ある程度学習が進んだ人ほど頭の整理になって理解が進むと考えています。
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』を購入するタイミング
理科選択する前から(=物理基礎を学校で習うタイミングから)購入しましょう。おそらく物理で挫折する人の多くは、本書に書かれている内容を知らないからです。松濤舎では、医学部受験生には生物選択を強く推奨していますが、本書を読んで物理に興味が湧いた人は物理選択でもいいと思います。
物理の完全攻略法
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』と同じカテゴリーの参考書
『宇宙一わかりやすい高校物理』シリーズは、初学者向けという意味では同じようなカテゴリーになりますが、本書が一般読者も含めた層を対象とした、あまり受験受験していない、導入や入りやすさを重視している一方、『宇宙一わかりやすい高校物理』シリーズは、勉強する意義などはそこまで重視しておらず、あくまでも勉強することを当たり前とした前提で、さまざまなテーマについて噛み砕いて説明することに重きを置いています。そういった意味では、どちらか一方でいいものではなく、両方持っておきたい参考書です。
前提として、松濤舎ではやり込む問題集は絞るべきだと考えていますが、補足として使用する参考書は複数あっていいという立場です。一つでも学ぶことがあれば(1,000円ほどで購入できるので)ラッキーなのです。
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』と他書の比較
先述の通り『宇宙一わかりやすい高校物理』シリーズと比較するのがいいと思いますが、本書の場合は問題やその具体的な解説は載っていません。ほとんど数式は登場せず、あくまでも「読んで理解できること」を重視しています。一方、『宇宙一わかりやすい高校物理』シリーズには、別冊で問題が載っていますし、本冊子にも具体的な問題や解説が載っています。あくまでも問題が解けるようになることを優先した実戦的な大学受験参考書という位置付けです。
どちらが優れているということではなく、どちらも欠かせない参考書と考えています。
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の目次/問題数
| 章 | 内容 |
|---|---|
| はじめに | 物理には”1つ”のストーリーがある! |
| 物理に公式の丸暗記なんて一切不要! | |
| 物理は”ストーリー”で学べ! | |
| これだけ!物理に必要な数学 | |
| 第1章 力学 | 力学は運動方程式が9割 |
| 物体が「いつ」「どこ」にいるかを知ることが力学の目的 | |
| 「3つの式」の意味を「v-tグラフ」から読み解く | |
| 「動いているもの同士」の「速度」や「位置」を求める | |
| 「力」と「加速度」の因果関係を示す運動方程式 | |
| 力の発生には2つ以上の物体が必要 | |
| 接触力とは原子・分子による電磁気的な力 | |
| 斜面の運動は力を「分解」する | |
| 力のつり合いとは「加速度0」の運動方程式 | |
| 摩擦力は3つに分けて理解する | |
| 弾性力の大きさを求める「フックの法則」 | |
| 重力、接触力以外の見かけ上の力「慣性力」 | |
| 運動方程式から得られる2つの情報 | |
| 仕事とは「力の距離の合計」 | |
| 仕事とエネルギーにはどんな関係があるのか? | |
| 力積とは「力の時間の合計」 | |
| 力積と運動量にはどんな関係があるのか? | |
| エネルギーや運動量はいつ使えばよいのか? | |
| 重力の仕事をエネルギーとして扱う「位置エネルギー」 | |
| 「力学的エネルギー」は運動エネルギーと位置エネルギーの合計 | |
| 運動量の総和は衝突前後で同じになる | |
| 衝突前後の相対速度の違いから「はね返り係数」を求める | |
| 一定の速さで動く円運動の速さと角速度の関係 | |
| 加速度が限定された円運動の運動方程式 | |
| 「向心力」と「遠心力」は別の力 | |
| 必ず単振動になる加速度の形 | |
| 単振動の代表例・水平ばね振り子 | |
| 質量を持つ物体同士には引力が必ずはたらく | |
| 万有引力の位置エネルギーの求め方 | |
| 地球を1周できるボールのスピードは? | |
| 天体の運動に関する3つの法則「ケプラーの法則」 | |
| 物体を回転させようとする作用「力のモーメント」 | |
| 力のモーメントを決める2つの要素 | |
| 3つの力の作用線は必ず1点で交わる | |
| 「数学的な重心」と「物理学的な重心」は同じ | |
| 第2章 熱力学 | 熱現象を「力学的」にアプローチした熱力学 |
| 「ニュートン力学」と「確率統計論」の融合 | |
| 力学的な温度「絶対温度」 | |
| 「物体」の温度を1[K]上げるのに必要な熱量 | |
| 「分子の動き」から熱現象を掘り下げる | |
| ボイルの法則とシャルルの法則から形づくられた「状態方程式」 | |
| 理想気体の運動エネルギーの合計を求める | |
| エネルギーの収入と支出を表した「熱力学第一法則」 | |
| P-V図から「気体の変化」を追う | |
| 代表的な気体の4つの変化 | |
| 気体の圧力を「粒子の運動」としてとらえる | |
| 第3章 波動 | 波の現象を「細かい粒子の動き」としてとらえた波動現象 |
| 「分子の振動」によって生じる波動現象 | |
| 「波動現象」は大きく2つに分けられる | |
| 「振動方向」から波を分類 | |
| 波を特徴づける6つの物理量 | |
| 波動現象を数式で表した「波の基本式」 | |
| 波はぶつかるとどうなる? | |
| 逆走した同じ波が形づくる「定常波」 | |
| あらゆるものが持つ振動 | |
| 弦に伝わる波の振動を求める | |
| 筒の中にある空気分子の振動「気柱の振動」 | |
| なぜ、救急車が通り過ぎるとサイレンの音が変わるのか? | |
| 第4章 電磁気学 | 古典物理学に「場」という新たな視点が生まれる |
| 電磁気を「粒子の動き」でとらえる | |
| 電荷同士にはたらき合う力を数式で表した「クーロンの法則」 | |
| 「電荷の運動」を表現する空間「電場」 | |
| 「電位」とは電気的な位置エネルギー | |
| 電磁場の4つの法則を表した「マクスウェル方程式」 | |
| 「電気力線」を定量的に評価した「ガウスの法則」 | |
| 金属内の電子はどのように移動するのか? | |
| コンデンサーと電気容量の関係 | |
| 電荷の大行進「電流」 | |
| 抵抗と電流から電圧を求める「オームの法則」 | |
| 電流が流れることで生じる熱「消費電力」 | |
| 回路の電流、電圧を求める「回路方程式」 | |
| 電荷が磁場から受ける力「ローレンツ力」 | |
| 磁場の様子を表す「右ねじの法則」 | |
| 磁場を変化させると「電場」ができる | |
| 第5章 原子物理学 | 「古典力学」から「現代物理学」への転換期 |
| 原子レベルのミクロな世界を見る「前期量子論」 | |
| 金属内から電子が飛び出る「光電効果」 | |
| 光を粒子として考える「光子仮説」 | |
| 光の性質は波か?それとも粒子か? | |
| 電子の波動性を示す物質波(ド・ブロイ波) | |
| 原子モデルの歴史 | |
| ボーアの水素原子モデル | |
| 質量とエネルギーの等価関係 | |
| じつは、質量とエネルギーは同じ | |
| 陽子、中性子から成る原子核 | |
| 核子をバラバラにすると質量が変わる | |
| 原子核の崩壊によって放出される「放射線」 | |
| 確率的に生じる原子核の崩壊 |
『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』に関するQ&A
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の特徴は?
- 本書は物理を一つのストーリーで学べるように構成されており、全体の関連性を理解しやすくしています。また、学ぶ目的が明確に示されているため、理解が深まります。
- どのように『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』を使うべき?
- 初めて読む際は、冒頭から順に読み進めることを推奨します。気になるテーマがあれば先に読むのも良いですが、全体感を掴むことが重要です。
- 本書を何周することが推奨されているの?
- 1周目は全体感を掴むため、2周目以降は問題集との往復を通じて知識を整理する役割があります。繰り返し読むことで理解が深まります。
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の対象者は?
- 初学者から物理を学ぶ全ての学生におすすめです。特に、ある程度学習が進んだ人には頭の整理に役立つ内容となっています。
- 本書を読むのにかかる時間はどのくらい?
- 通読には約3時間かかります。250ページ程度の内容で、1見開き1〜2分を目安に進めると良いでしょう。
- 本書の欠点は何ですか?
- 入試で必要なテーマを全て扱っているわけではなく、情報密度がもう少し高ければ使いやすいと感じる部分があります。
- 『一度読んだら絶対に忘れない 物理の教科書』の補助教材はある?
- 松濤舎では本書の補助教材は用意していませんが、内容を端的にまとめた資料があれば復習に役立つと考えており、今後塾生向けに作成する可能性があります。
- 本書を購入するタイミングはいつが良い?
- 理科選択をする前、つまり物理基礎を習うタイミングから購入することを推奨します。基礎知識を得ることで、物理への理解が深まります。
- 本書と他の参考書の違いは?
- 本書は物理のストーリーを重視し、理解を深めることに特化しています。一方、類書とも言える『宇宙一わかりやすい高校物理』シリーズは、問題演習に重点を置いているため、補完的に利用するのが良いでしょう。