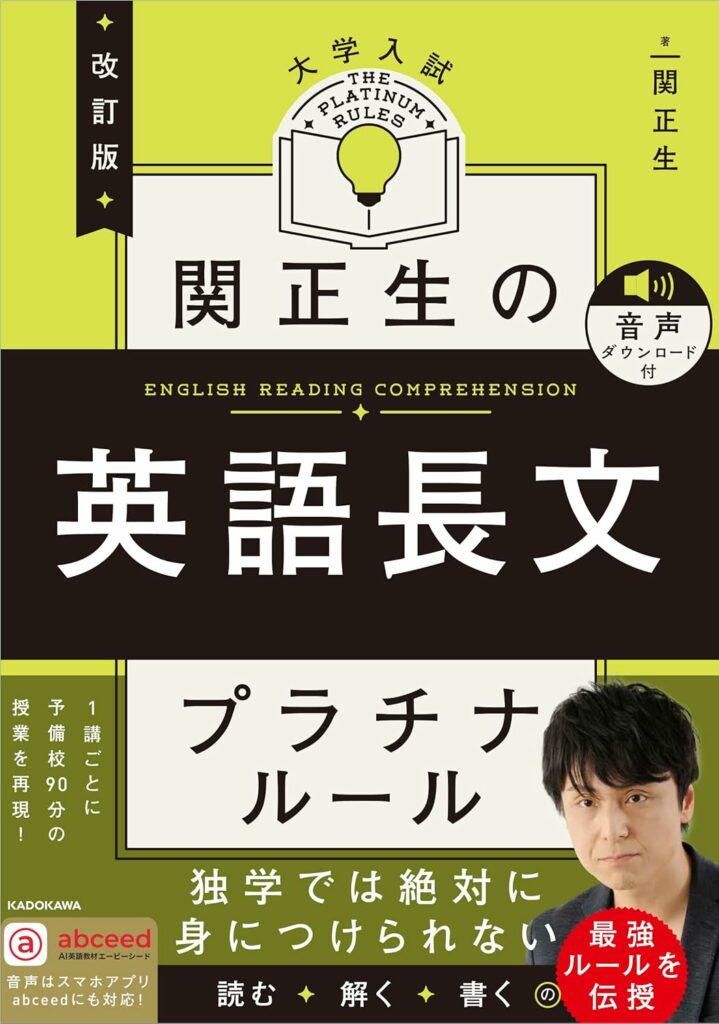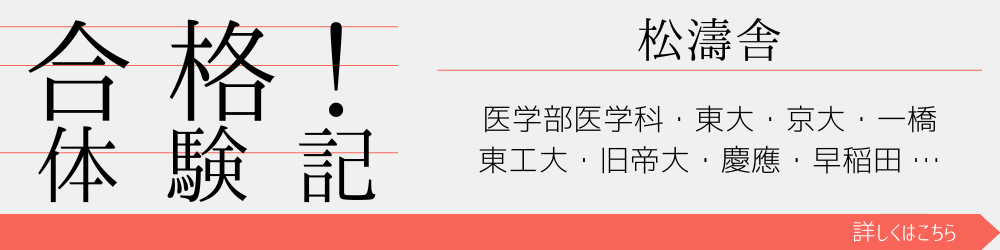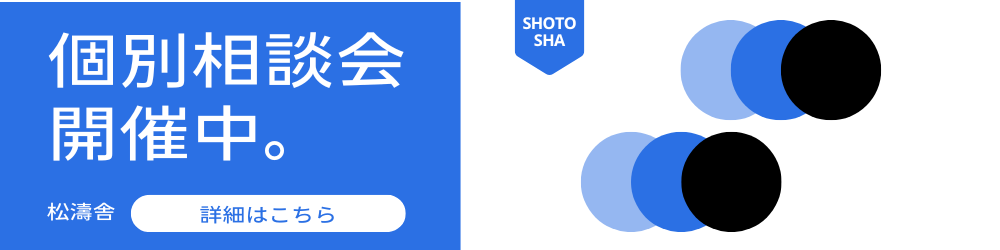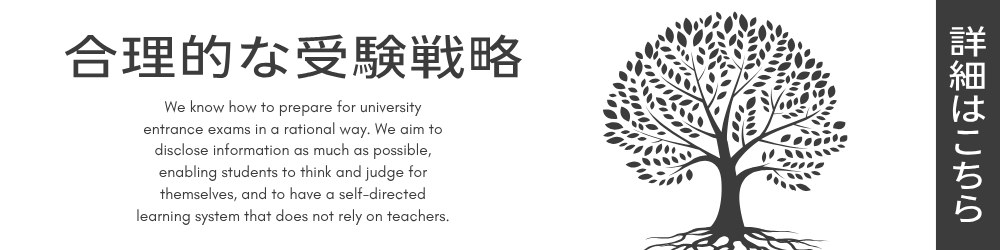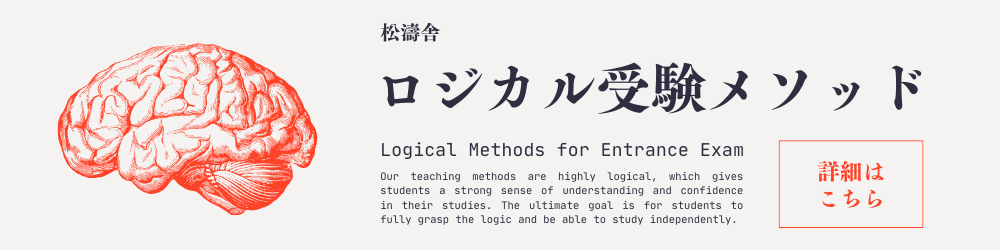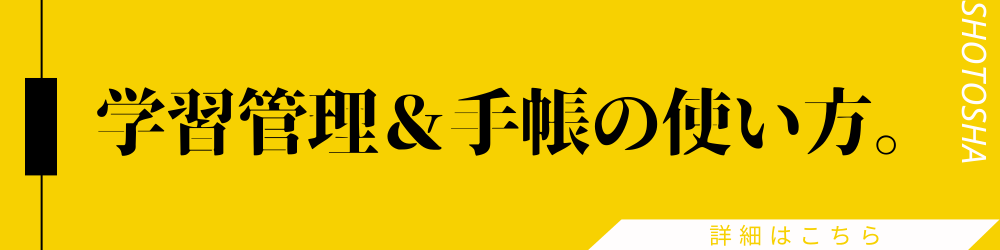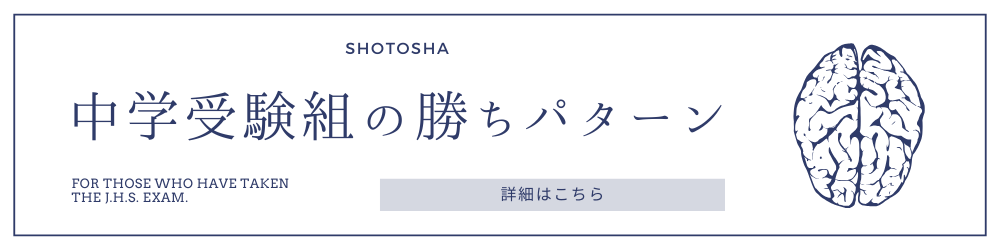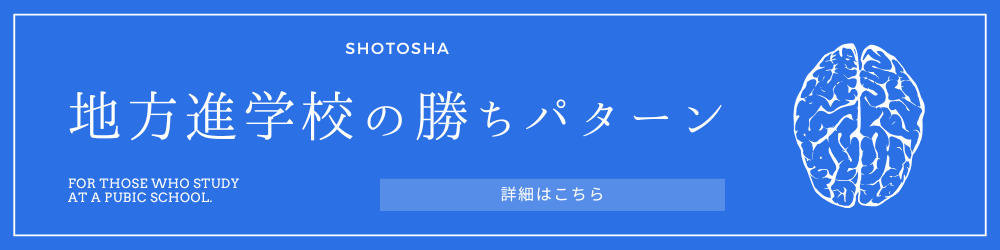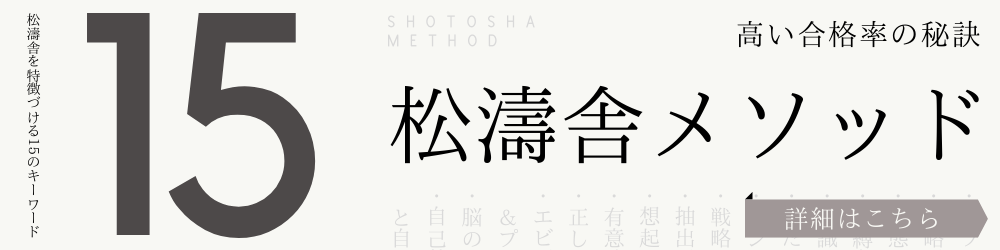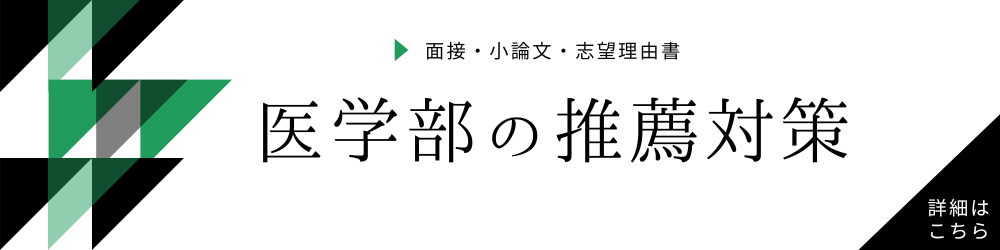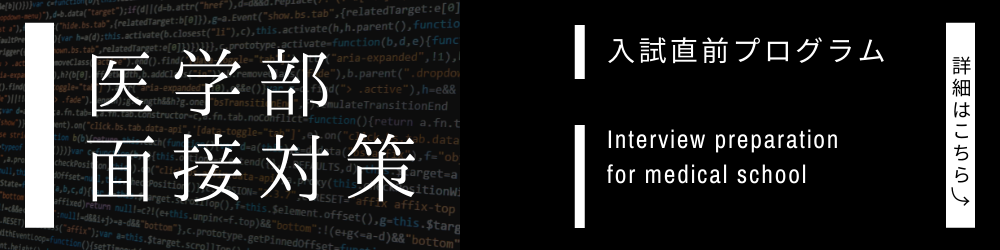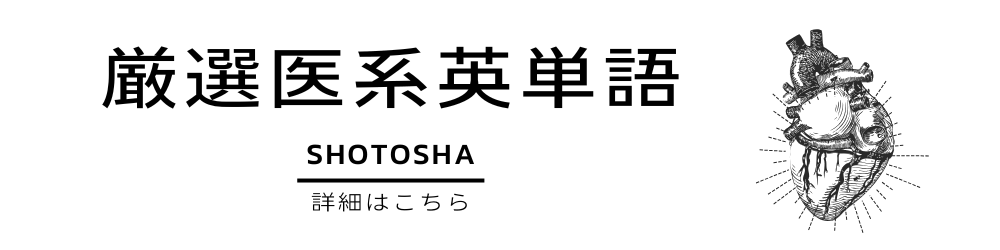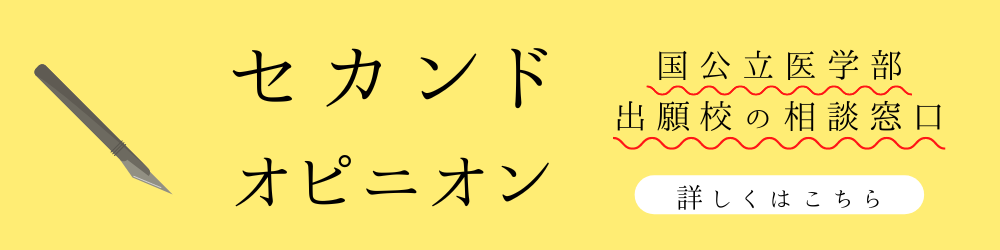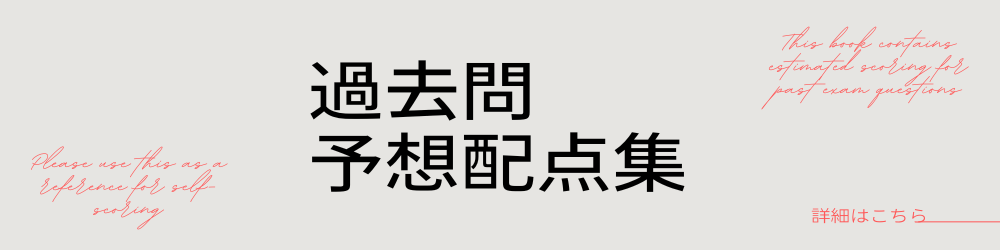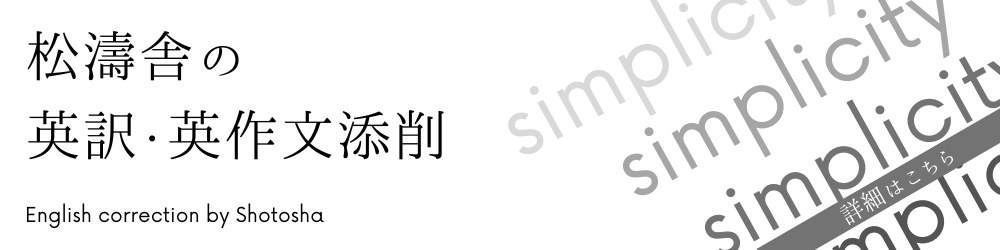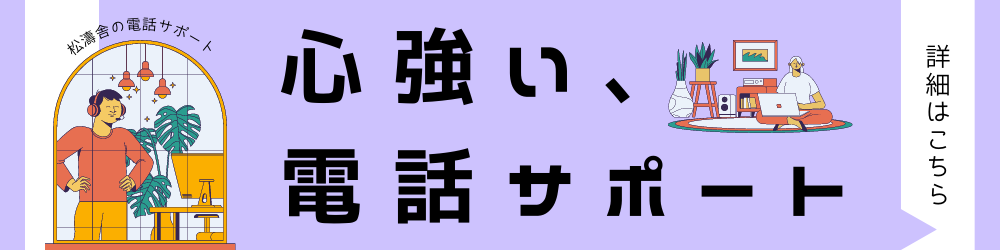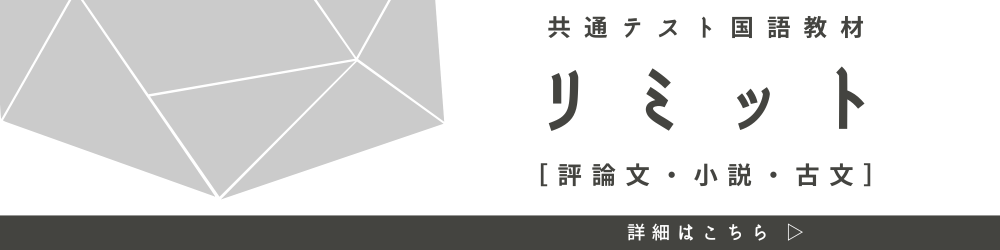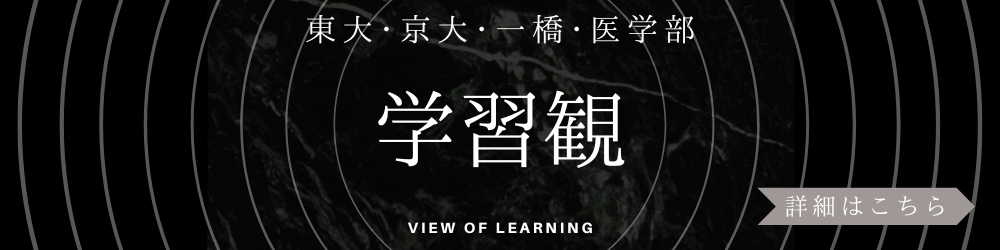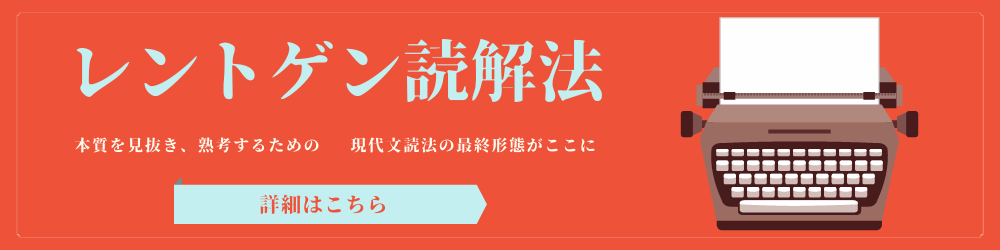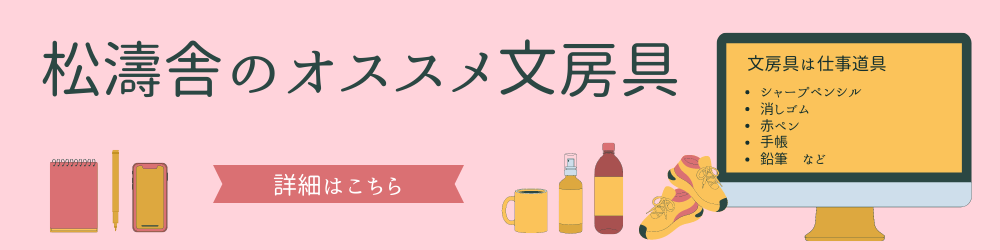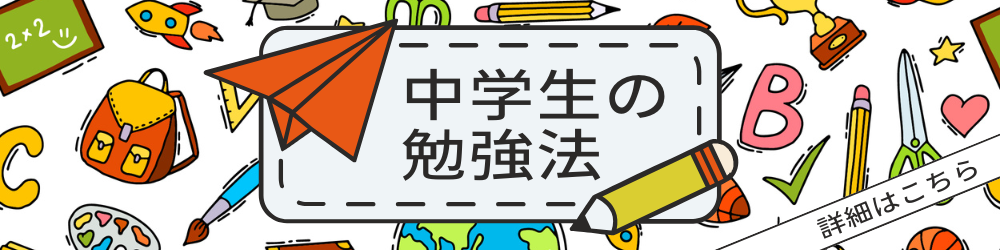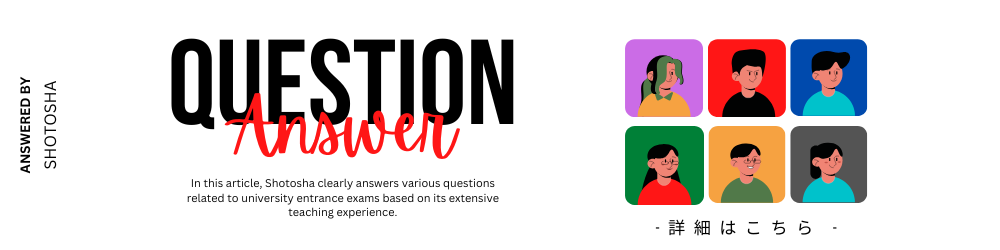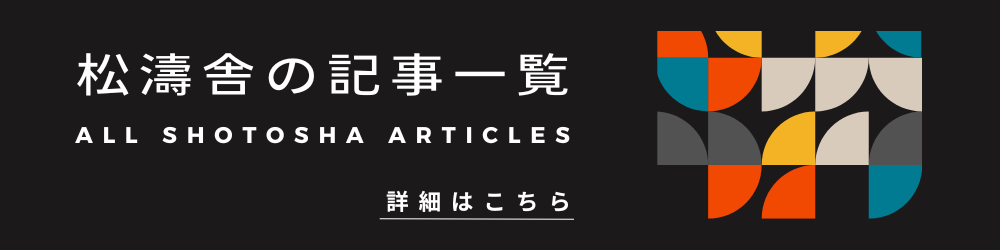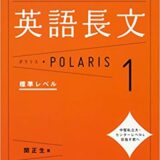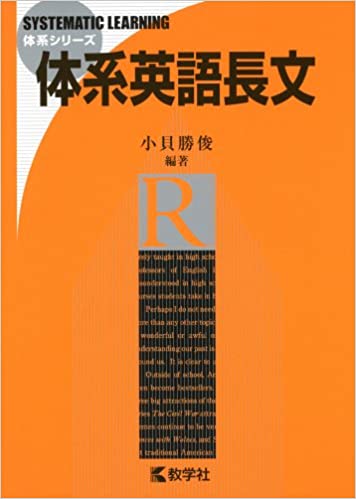『英語長文プラチナルール』で合格可能な医学部・上位校
松濤舎での合格実績を以下に記載します。
・医学部医学科
大阪大学、東京科学大学、千葉大学、横浜市立大学、筑波大学、広島大学、金沢大学、新潟大学、熊本大学、信州大学、岐阜大学、浜松医科大学、鳥取大学、愛媛大学、大分大学、福島県立医科大学、群馬大学、高知大学、宮崎大学、香川大学、富山大学、弘前大学、秋田大学、慶應義塾大学、東京慈恵会医科大学、順天堂大学、日本医科大学、国際医療福祉大学、自治医科大学、昭和大学、東京医科大学、東邦大学、日本大学、聖マリアンナ医科大学、東海大学、帝京大学、東京女子医科大学、埼玉医科大学 ほか
・他学部
東京大学、京都大学、大阪大学、名古屋大学、北海道大学、東北大学、一橋大学、神戸大学、慶應義塾大学、早稲田大学 ほか
※代替可能な問題集を使った合格実績も含む。
『英語長文プラチナルール』の習得レベル
レベル1:設問の8割を解くことができる
レベル2:黙読で長文を読み下し、意味を掴むことができる
レベル3:音読で長文を読み下し、意味を掴むことができる
『英語長文プラチナルール』の特徴
長文問題集であれば載っているコンテンツを除くと、応用性の高くないTipsがパラパラと載っているのが本書の特徴です。
長文問題集なら基本的に載っているコンテンツ
- 英単語まとめ
- 構造解析(一部 or 全文)
- 各設問の解説
- 全訳
- 最新のテーマ/今後も出題されるであろうテーマを扱う
『英語長文プラチナルール』の使い方
長文を読みはじめる前に設問と選択肢に目を通します。だいたい30秒くらいで「どんなテーマを扱っているのか」がわかればOKです。
『イチから鍛える英語長文』で身につけた方法で勉強していってください。つまり、SとVを見つけながら、カタマリごとに読み下していきます。SとVが見抜けなかったり、どこまでをカタマリと認識したらいいかわからなくなったら、解説の「構文解析」を読みましょう。また、単語がわからなかったら解説で調べましょう。
設問を解いてみましょう。解説は詳しいので独学でも問題なく理解できます。
「構文解析・語句」というコンテンツで全英文の構造解析がされているのですべてに目を通し、構造が見抜けているか確認してください。
音読してください。当然、SとVを探しつつ、カタマリを読み下す、という方法は忘れないように。さらに、意味を理解しながら音読することが、長文読解の回路を作ることになります。ただ文字を音声に変換するだけの作業には絶対にしないでください。
単語の意味や構文でわからないことがない状態になったら、あとはSTEP.5を繰り返します。最終的に、音読しながら自然と意味が読み取れるようになったら完了です。
『英語長文プラチナルール』に関する前提
プラチナルールは汎用性が高いとは言えない
本書は、長文の読み方を体系的に教える問題集ではありません。
掲載されているプラチナルール(全16個)は、
- 「固有名詞を見たら具体例」
- 「「比較級」を見たら「主張」を考える!」
などです。このように、そこまで応用性が高くない読み方のTipsがパラパラと紹介されている問題集、というのが正直な感想です。
何か1つでも学ぶことがあればいいというスタンスで使う分には良いでしょう。
予備校の授業の非効率性
本書のウリには「1講ごとに予備校90分の授業を凝縮」とありますが、問題集を使った独学でも、正直あまり得るものがありませんでした。これを90分かけて予備校の授業で学ぶことは、非常にコストパフォーマンスが悪いと感じます。
本書で得られるのは、汎用性が高くない16個のルールです。全部で9レッスン載っているので、810分(=13.5時間)の授業を受けて学ぶことが16個(90分の講義で1−2個)というのは、効率が悪すぎると言わざるを得ません。
『英語長文プラチナルール』を勉強する目的
長文の多読用です。
問題の選定は悪くないため、最終的に音読しながら意味を掴めるようになれば、本書はクリアとなります。
ただ、繰り返しにはなりますが、本書を強く推奨する理由はありません。
『英語長文プラチナルール』の音源について
音源はダウンロード可能です。
ただし、すべての長文問題集で音源を聴いて勉強するのは効率的ではありません。発音に不安がある単語だけGoogleで調べるに留めるようにしましょう。
【決定版】英語の勉強方法と年間スケジュール
医学部・上位校受験生向けに、英語の勉強方法と年間スケジュールをまとめました。参考にしてみてください。
『英語長文プラチナルール』に関するQ&A
- 『英語長文プラチナルール』の習得レベルはどのように分かれていますか?
- 『英語長文プラチナルール』は、設問の8割を解けるレベル1、黙読で意味を掴むレベル2、音読で理解を深めるレベル3に分かれています。各レベルでの習得が、長文読解の向上に寄与します。
- 『英語長文プラチナルール』の特徴は何ですか?
- 本書は、長文問題集に一般的に含まれるコンテンツに加え、応用性の低いTipsが紹介されています。具体的な読み方のルールが16個あり、長文読解の基礎を学ぶのに役立ちます。
- 『英語長文プラチナルール』をどのように使うべきですか?
- 使用方法は、まず設問を読み、次に黙読で長文を読み下し、設問を解き、構文解析を確認し、最後に音読を行います。このプロセスを繰り返すことで、理解力を高めることができます。
- 『英語長文プラチナルール』はどのような目的で勉強するのが良いですか?
- 本書は長文の多読用として設計されています。音読を通じて意味を掴むことが最終的な目標であり、繰り返し学習することで効果を最大化できます。
- 予備校の授業と『英語長文プラチナルール』の効率はどうですか?
- 本書は「1講ごとに予備校90分の授業を凝縮」と謳っていますが、実際には得られる知識が限られており、独学での学習効率が低いと感じることもあります。
- 本書に音源は付いていますか?
- はい、『英語長文プラチナルール』には音源がダウンロード可能です。ただし、すべての問題に音源を使用するのは効率的ではなく、発音に不安がある単語のみ調べることが推奨されます。
- 『英語長文プラチナルール』の内容はどのようなものですか?
- 本書には、英単語まとめ、構造解析、各設問の解説、全訳などが含まれています。これにより、読解力を高めるための基礎的な情報が提供されています。
- どのような学生に『英語長文プラチナルール』は向いていますか?
- 本書は、大学入試を目指す受験生や、長文読解に苦手意識を持つ学生に向いています。基礎から応用まで幅広く学べる内容が特徴です。
- 『英語長文プラチナルール』の活用法は何ですか?
- 本書は、設問を解くための基礎力を養うために活用できます。特に、音読を通じて理解を深める方法が効果的です。
- 本書を使う際の注意点はありますか?
- 本書は応用性が高くないため、他の参考書と併用することが推奨されます。また、音読時には意味を理解しながら行うことが重要です。