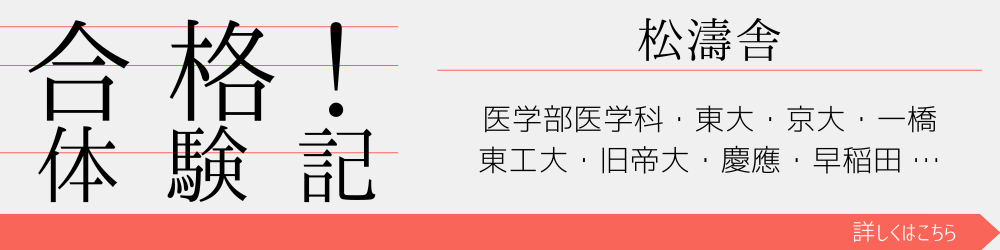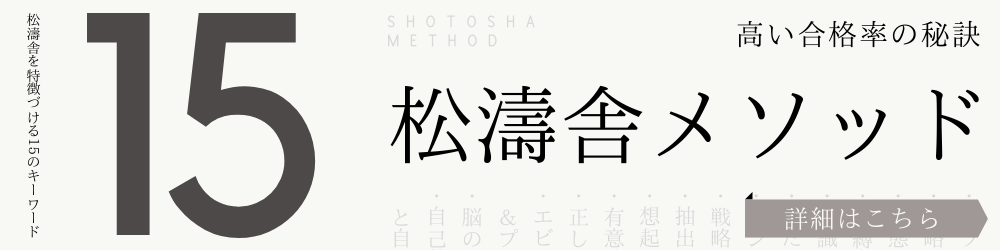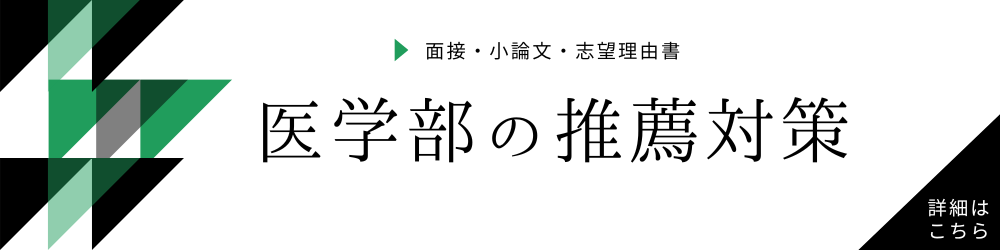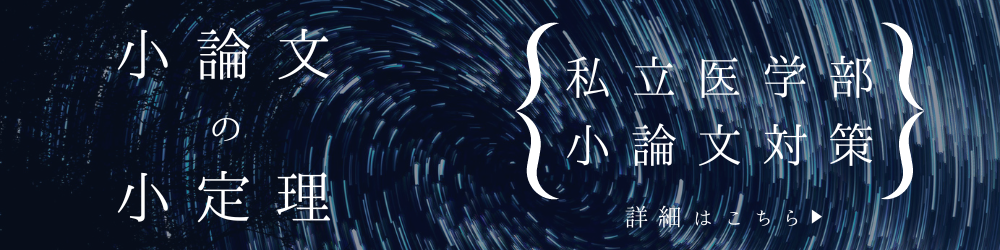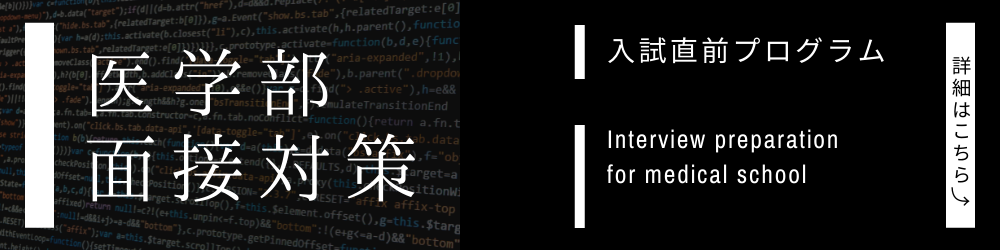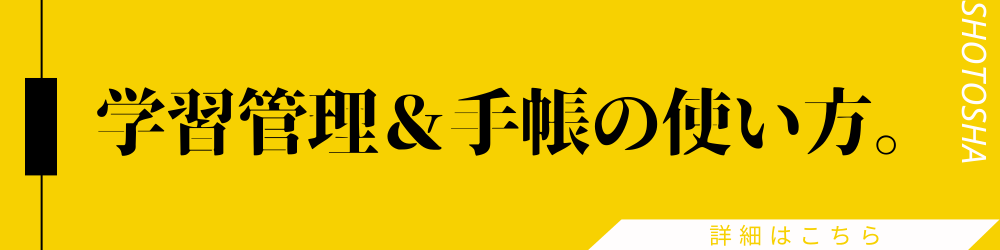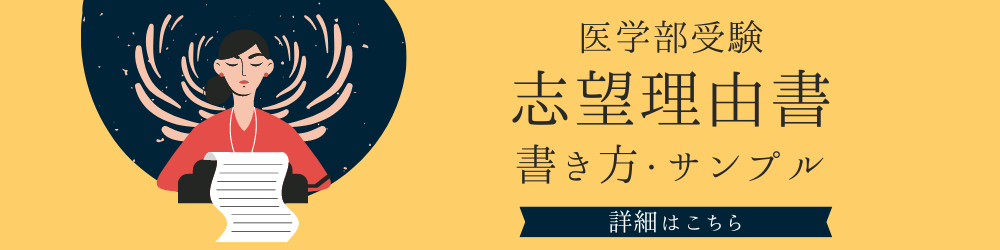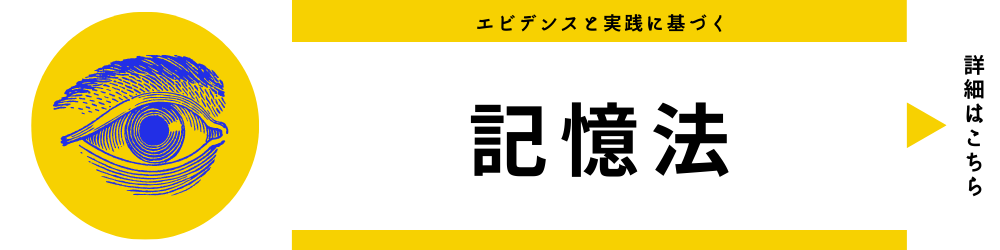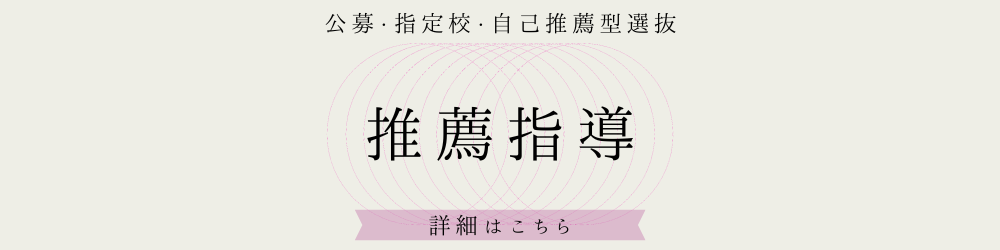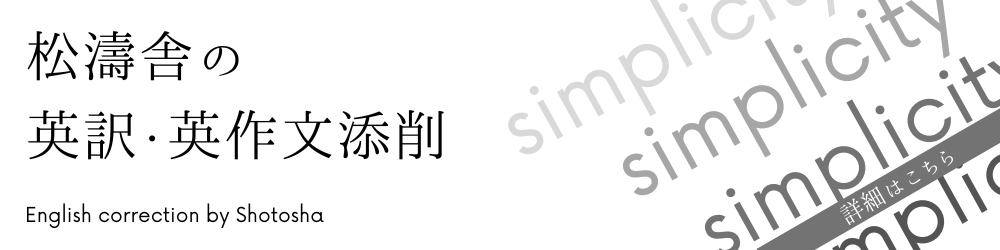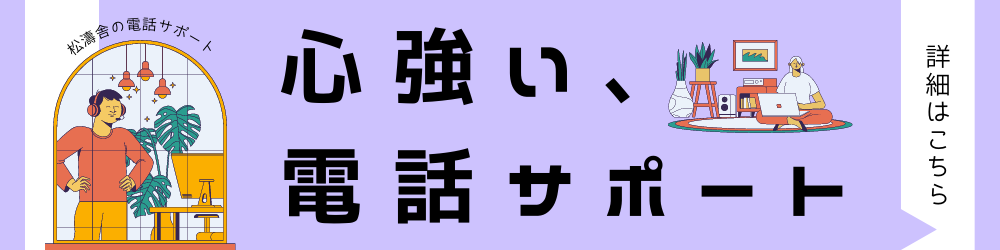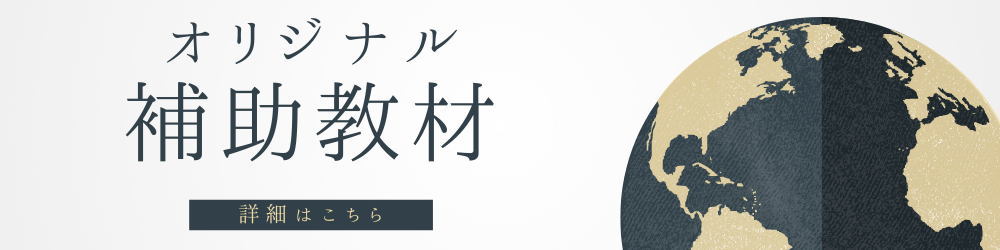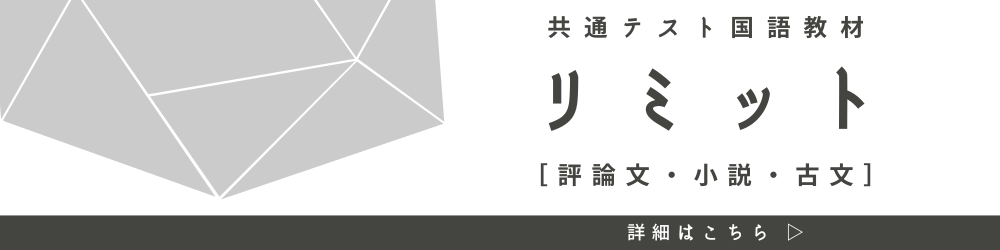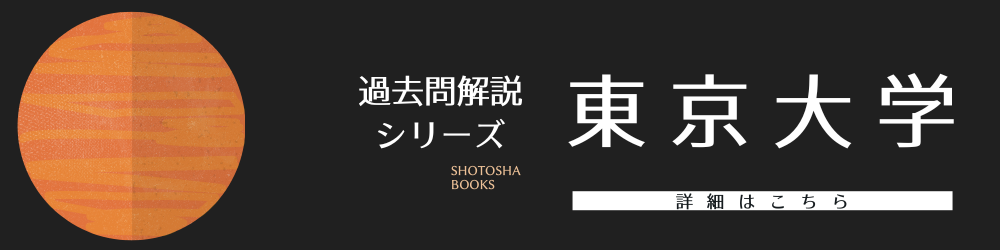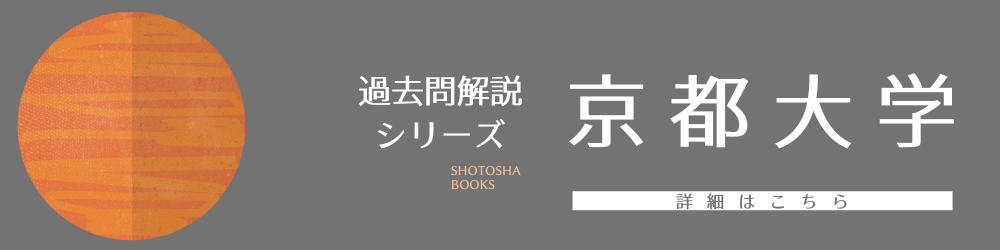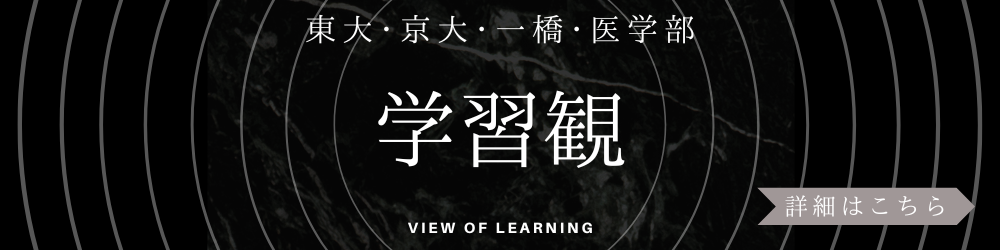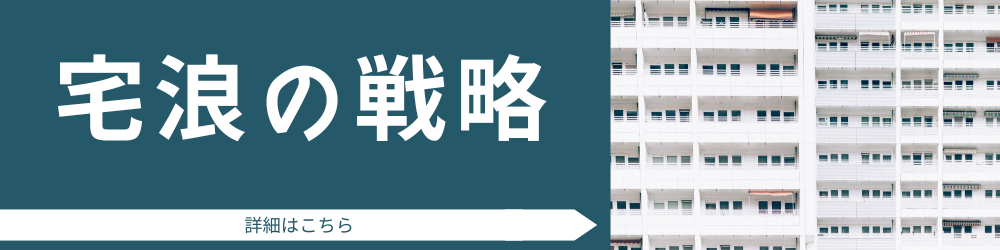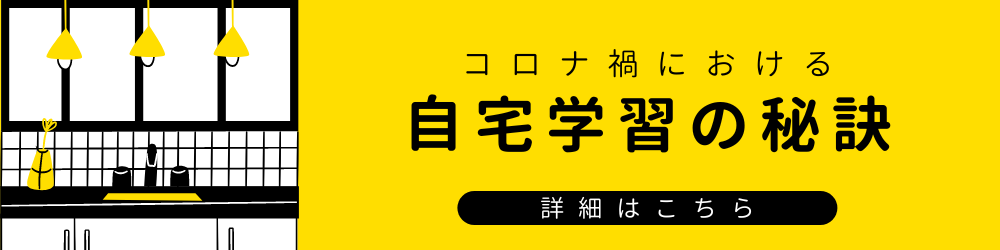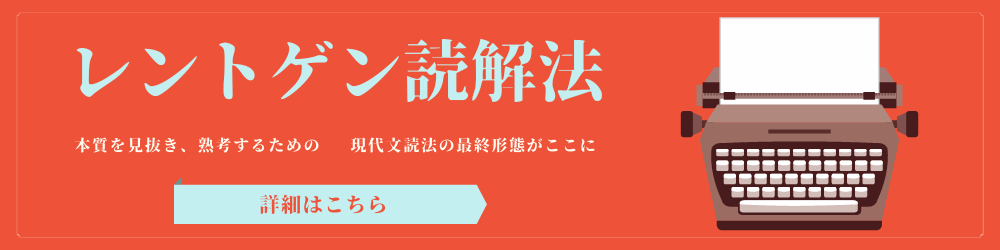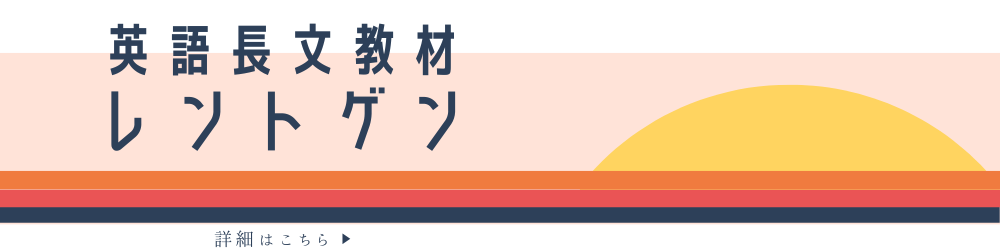▼受験観
・本番で、周りよりも相対的に点数を取ることができれば良いというもの。基本的に例年の合格最低点を目安に勉強をする場合が多いが、テストの難易度によって今年の合格最低点は簡単に変動しうる。だから、点数という絶対的な数値が高いか低いかということや例年の合格最低点だけでなく、本番で周りより相対的にどのくらい多く点数が取れるかということにも注意していた。
・どんな状況にあったとしても確実に合格するというのは、自分の学力がその大学から逸脱していないとほぼ不可能。理由は、その大学を志望する人は同じような学力レベルの人が多く、そのため点数の幅があまり広くならないから。そのため、ミスをしない、体調をしっかり整える、など数点単位(場合によっては数十点)に影響してくる、学力に関係のない部分の対策にかなり気をつけていた。
・合格することを考えるなら、安定して得点できる教科を得意科目にすることが大切。理系の場合、具体的には化学と英語を得点源にするのがいいと思う。数学や物理に比べて、大きくミスすることが少なく、安定するからだ。数学の場合、2次試験で1問丸々解けないと、それだけで数十点失う。また、物理では、最初の計算をミスしたり、状況把握でミスをすると、後半の問題も連鎖的に間違うということがある。実際、僕の場合、数学と物理で押し切ろうと考えていたが、大幅な難化と計算ミスなどにより結局あまり得点できなかった。
・参考書や予備校をどこに選ぶかということが合格に直結しうる。入試問題は、教科書からしか出ない、学校での勉強で受験勉強は事足りると言われることもあるが、それは受験勉強をある程度終えた後に感じることであって、初学者の段階から学校の教科書だけ勉強することや、参考書や予備校を使わずに難関校に合格することは、普通の人には無理がある。なので、できるだけ理解しやすいような参考書や自分に合った環境(予備校など)で勉強することを意識していた。
・自分のタイプや1日で勉強に集中できる時間を知ることが大事。僕は短期集中で1日15時間以上くらい勉強できるタイプではないと考えていたので、高一からコツコツ勉強するようにしていた。
・難関大突破には先取り学習が必須。東大京大に行くような人の多くは、中高一貫校のような進度が早い学校の出身であり、これまでの勉強量も多いはず。僕は地方の公立高校だったので、中高一貫校の生徒に追いつこうと、早く早く勉強していた。(数学を例にすると、高1で数2Bのチャートまで終わらせ、高2の夏には数3のチャートまで終わらせた。)
▼記憶観
・その時点でどれほど記憶していたとしても、時間が経てば驚くほど忘れていく。なので、覚えた自信のある単語に対しても慎重に見返していた。
・単発で記憶できる量には限界がある。うまく知識を紐づけることで、結果的に多くのことを実践で使うことができる。理由や原因を考えることで他の知識と関連させて覚えるようにしていた。
▼モチベーション観
・受験において、モチベーションに頼ってはいけない。モチベーションがないときに、「やる気を出そう」と頭で考えるだけではやる気は出てこない。(だから、みんなやる気を出せないわけである。)やる気を出すためには、実際にやってみることが大事。実際にやってみると、脳が色々と働いて、その結果やる気を生み出すということは科学的に実証されている。
・とはいえ、勉強を楽しいと思うかそうでないかは学習成績に顕著に現れる。できるようになるから好きになるのか、好きだからできるようになるのかは人によりそれぞれだが、どちらにせよ、楽しんで勉強できると知識の吸収、集中の度合いが違ってくる。僕は、できるだけ受験勉強にも楽しみを見出すようにしていた。
▼国語観
現代文
・「問題作成者がどのような理解をしたか」が問われているもの。問題作成者は、「実際に書いてあること」、「書いてあることから一般的に推測できること」から問題を出す。だから、自分の思い込みを排除した上で問題文を読むように心がけていた。(「書いてあることから一般的に推測できること」の例:子供がこけて、涙を流している→痛い )(ここで、「もしかしたら子供のお母さんが病気になったんじゃないか?だから泣いているんだ」などと本文にない事象を持ってくるのはナンセンスである。)
・現代文を正確に教えることのできる先生は数少ない。有名な予備校講師が作った解答である過去問の解答にすら、予備校ごとに解答の根拠が異なるということがある。このことからわかるように、問題集や模試の解答は本当に正しいかどうか疑わしい部分もある。なので、世の中から信頼の厚い予備校講師の授業を受けたり、問題集や模試の解答を盲信せず、自分で「どうしてその解答が正しいと言えるのか」を考えるように心がけた。
古文
・「覚えたらなんとかなる!」と、高を括って高3まで勉強しないでいると、痛い目をみる。体感として、助動詞判別の習得や単語の暗記にはそれ相応の時間がかかる。なので、時間のある高1、2年までに助動詞や単語は覚えておいた方が良い。
漢文
・他の科目との兼ね合いを考えると、勉強できる内容は、句法と漢字の読み方、漢文に関する知識(例:五言絶句など)のみ。それだけでも、しっかり得点することができるはずである。
▼数学観
・図を書くことが大切な教科。数学ができない人は、数式や文章をそのままに捉えている人が多い。できる人でも図を書かない人がいるが、その人は頭に書いているはずである。
実際、図を書くことで、見えてくるものも多いので、些細なことでも図を書くようにしていた。
・試験中わからなかった問題が、試験後にわかったとき、その解法が以前から知っていた解法であった場合、問題へのアプローチが曖昧であると考えるべき。なんとなく問題に取りかかっているようでは点数は安定しない。事前に、自分の中で、問題へのアプローチを決めておくべきである。(例:図形問題→ベクトルor 座標 or 幾何 と瞬時に出せるようにしていた)
・数学が苦手な人は、演習量や典型問題のストックが足りないだけである。「数学苦手やねん」という人に限って、チャートなどを1周も進められていない人も多い。網羅系の参考書にある問題が少なくとも8,9割解けるようになることで、受験数学の土台ができ、その土台の磐石さが、難関大数学の得点力に大きく影響する。
▼化学観
・典型問題を素早く解くことが大切。出題されるのは、ほとんど典型問題なので、見たことのある問題はすぐ解けるように、同じ問題集を何度も解き直していた。
▼英語観
単語
・単語の意味を文字通り覚えることはあまり意味がなく、イメージとして覚えることが大切。長文読解において、単語の訳し方を文章に応じて変えることが頻繁にあるから。
文法
・自分が使える形で暗記しておくことが大事。「自分がこの文法を使って英文を書くならどうするか」を考えて勉強していた。
・文法というのは、英語の決まり事。だから、自分の主観を入れずに、その概念を理解するようにしていた。
和訳・精読
・文章中で、その単語がどのような役割を果たしているのかを分析すべき。自分の感覚だけで訳すのは間違いの元なので、自分の英訳の根拠が文法や文の構造にあることを最優先にして訳していた。
和文英訳・自由英作文
・(和文英訳)文章をそのまま訳すのではなく、一度頭の中に状況を想像してそれをもとに訳すイメージ。日本語を直訳した「英語」は、英語として上手く意味を成していないことが多々あるから。
・(自由英作文)文章の型をある程度知っておく(決めておく)ことが重要。テスト中に文章の構成を考えすぎるのはもったいないため。文章の構成例を3つほど考えて模試などに挑んでいた。
長文
・国語の長文でも人によって読むスピードが違うように、英語の読解スピードも人によって違う。にも関わらず、必要以上に早く読もうとすると、自分に本来あるはずの読解力が発揮されない。問題演習で自分に最適な速度を見つけようとすることが大切。
・一つの段落で伝えたいことは原則一つしかない。(大学の講義でも学んだので信憑性はかなり高い)その一つを理解することを意識して長文を読んでいた。
リスニング
・リスニングがニガテな人がやってはいけないことは、とりあえず英語音声を聴きまくることである。そもそも正しい発音を知らないのに、闇雲に聞いてもわかるようになるわけがない。僕は、リスニングがニガテだったので、リスニング教材をたくさん聞いたが、英語が聞けるようになった感覚はなかった。
▼模試観
・本番と同様に、得点を取ることだけに集中する場所。模試は、本番でどのくらい点数が取れるのかを知る場所である。だから、得点以外のこと(難問が解きたいから難問を解くなど)に集中し出すと、本番の得点力がうまく推測できず、本来の目的が見失われるし、進路決定の材料になりえない。
▼塾観/予備校観
・受験に関する膨大な情報を有している。それは、個人の学習データや進路状況だけでなく、入試問題そのものの情報にも当てはまることである。予備校の先生から、学校では教えてくれないような合格に大きく関わる情報をたくさん得ることができた。
・しかし、商売であるということも忘れてはならない。たくさん授業を取ることを進めてくる場合がある。非常に良質な講座も存在するが、自分に必要のないものも含まれているはずなので、自分にとって必要な講座のみを取るように意識していた。
▼参考書観/問題集観
・自分の学力<=問題集、参考書に書いてある内容。 なので、右辺の値を大きくする、つまり、問題集や参考書が良書であり、それをしっかり学習すれば、自分の学力の最大値をより大きくすることができると考えていた。
・目的を持って参考書や問題集を購入する。「難問へのアプローチが知りたいからこの参考書!」「苦手な古文ができるようになるために、この参考書!」など、自分の目的をきっちり意識した上で勉強しないと、実力アップとはならず、参考書のメリットが半減する。
・自分の決めた一冊を完璧にすることが大事。僕の場合、「入試数学の掌握」を使用し続けた結果、学んだ知識を本番で使用して問題を解くことができた。
▼友人観
・こちらが選ぶことはできない。できることは、関わり方を考えることである。勉強の妨げになるような友人とは、あまり関わりすぎないことが大事。(そういった友人が悪いというわけではないが、受験生の自分にとっては悪影響なため。)僕の場合、勉強に真剣ではなかった部活の友人との関わりを減らすため、高1で部活を辞めた。
▼部活観
・部活に所属していることは受験にとってあまり重要なことではない。積極的な動機から部活をするのは賛成だが、消極的な動機(周りとの人間関係への不安など)で部活を続けていることは明らかに時間や人生の無駄である。
▼その他
定期テスト観
・定期テストは、学校で学んだことを覚えているかというテストである。受験に出ない科目や単に暗記すれば点数が取れるものを勉強しても、受験の力はあまり成長しない。僕は、定期テスト出題範囲内で受験に出てもおかしくない内容にフォーカスして勉強していた。
・定期テストの順位と合格する大学のレベルに因果関係はない。先ほど述べた通り、定期テストは、学校で学んだことを覚えているかというテストである。なので、「難関大入試を突破する→定期テストの順位がいい」は偽である。実際、僕は、定期テストの順位で考えれば神戸大、よくて大阪大レベルだったが、受験につながるような勉強を意識して学習したので京大に合格できた。
物理観
・定義をきっちり覚えなければいけない。あいまいな記憶だと問1から解けないことがあるから。わからない問題は定義に立ち返るように意識していた。
・定義を言葉そのままに理解する。知らず知らずのうちに、多くの人が定義に自分の思い込みを入れてしまっている。物理は「他人の決めた定義、法則から議論を始めるもの」であって、自分の定義から始まるものではないということに注意していた。
・定義を自分なりに解釈する。その定義や法則を使いこなすには、その定義や法則に対する自分の理解が必要である。なので、自分の言葉で説明することができるようにしていた。(このとき、定義の意味を勝手に拡大したり、間違った意味を含ませないように注意しなければいけないが)
・公式の適応範囲は、全て証明の過程にある。公式を使いこなせないのは、そもそもどうやって導かれたかわからないからである。なので、基本的な公式の証明は完璧にできるようにしていた。(これは数学でも大事だが、数学より得点に直結すると考えている。)
・定義をもとに正しい議論を進めると、難関大入試も簡単にとける。そもそも物理は、原理や法則(+数学的知識)から議論がスタートする。なので、問題がわからないということは、定義や法則に関する理解が足りていない、数式から意味を捉えられていない、のいずれかであると考えるようにしていた。
・公式暗記はかえって遠回り。物理の勉強は、内容の理解であって、公式暗記ではない。
・物理において単位は最も重要なことの一つ。単位があっていなければ、どこかで絶対にミスが起こっている。単位ミスを減らすため、できるだけ無次元量化していた。
受験本番観
・自分の性格を知ることが大事。それが自分に合ったメンタルケアにつながる。プレッシャーをかけて本番うまくいった人の話を聞いていたため、自分の受験時もかなり自分にプレッシャーをかけたが、焦ってミスを多発してしまい、点数が取れなかった。