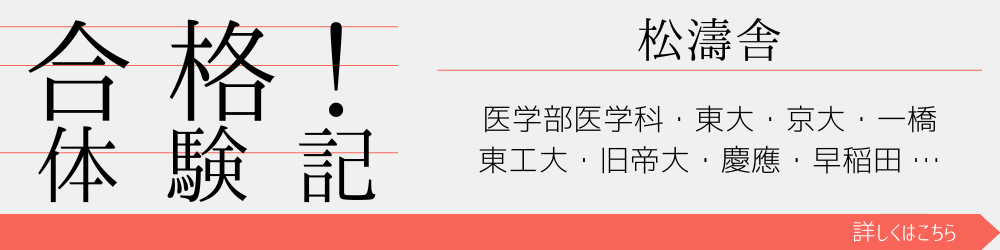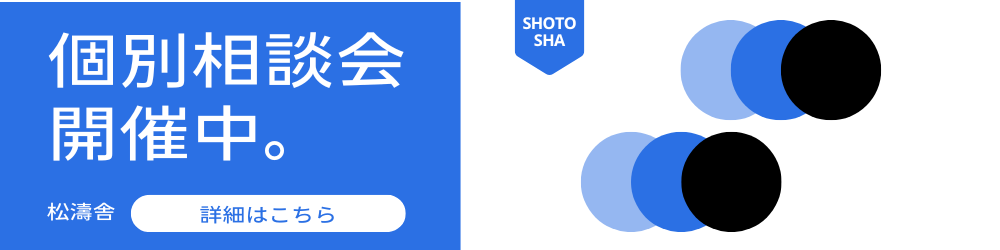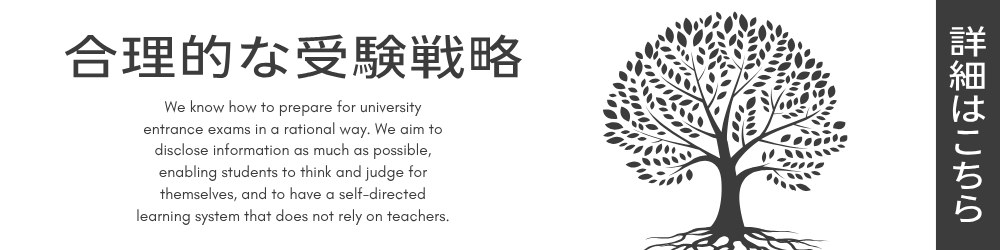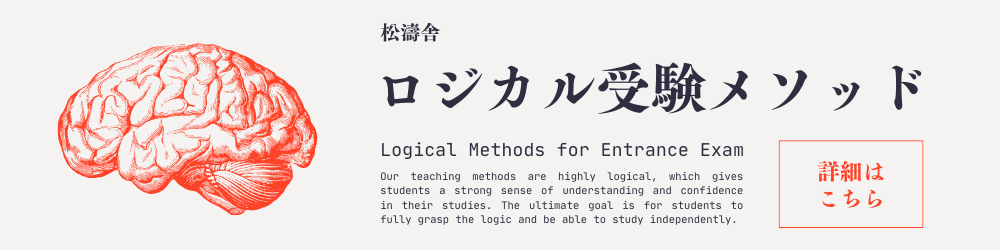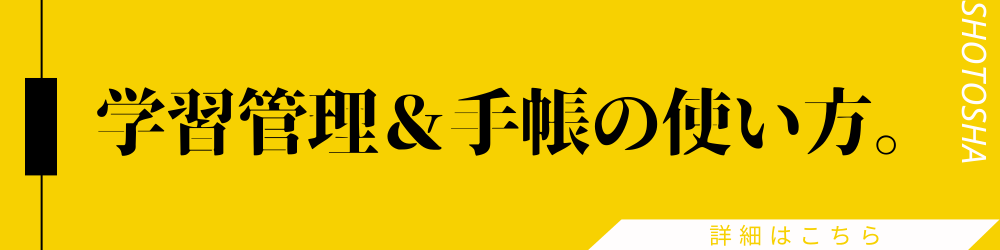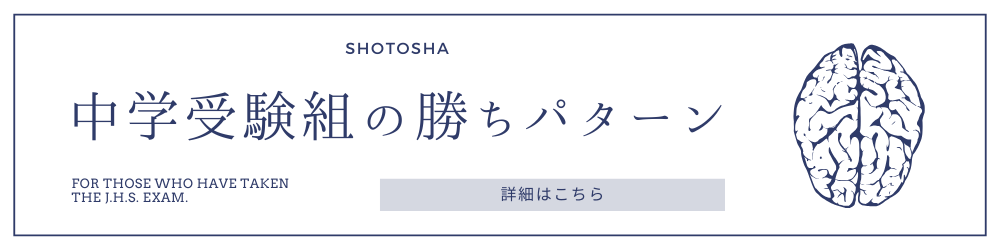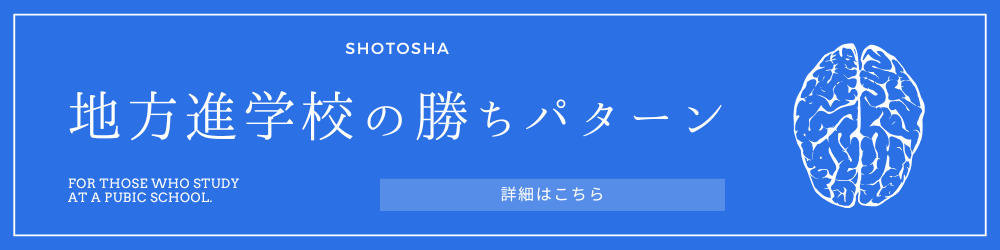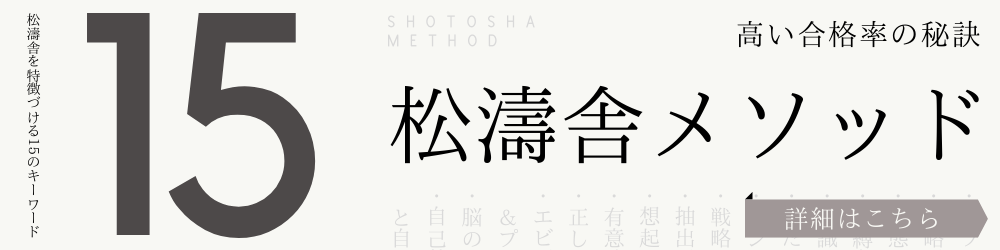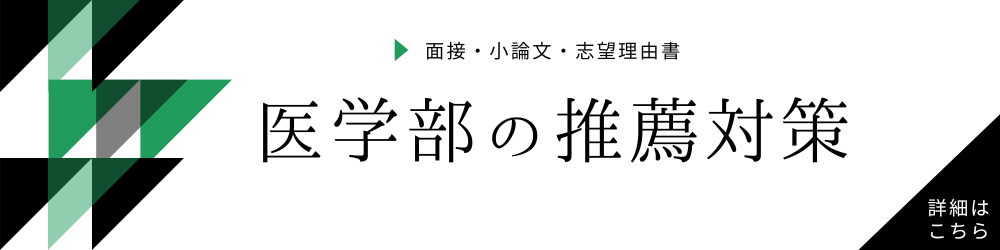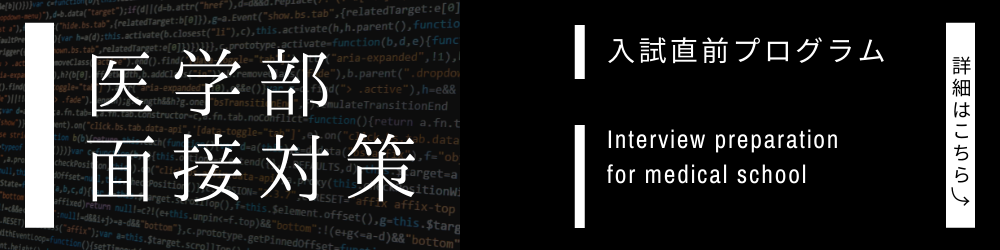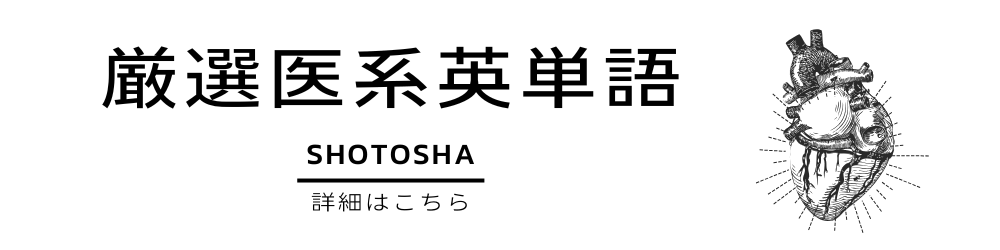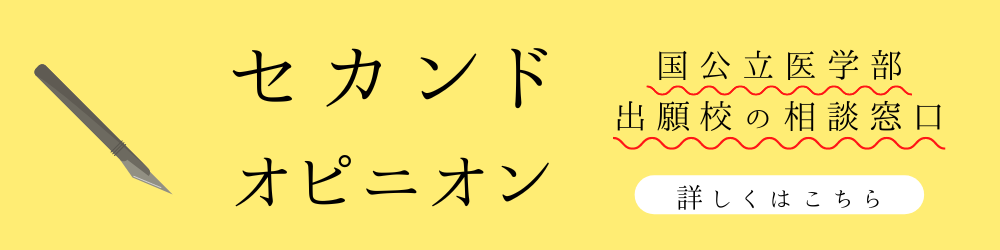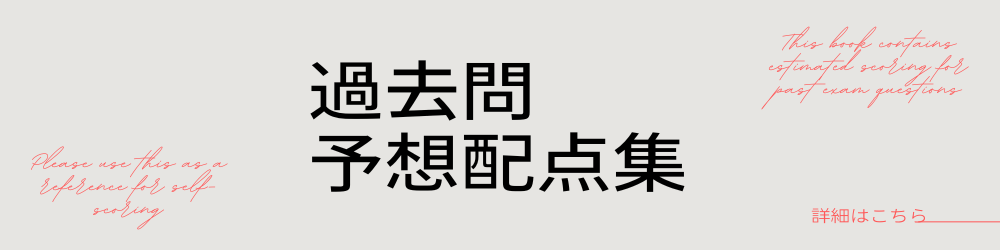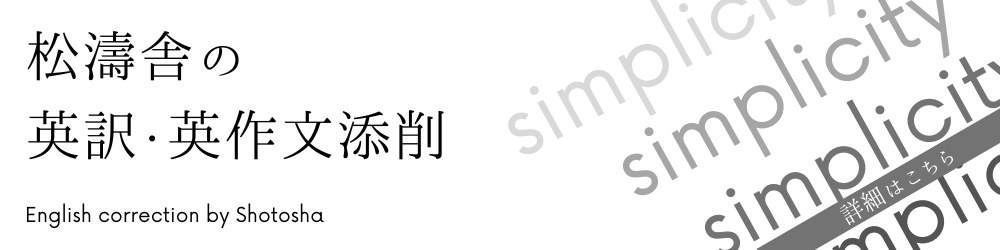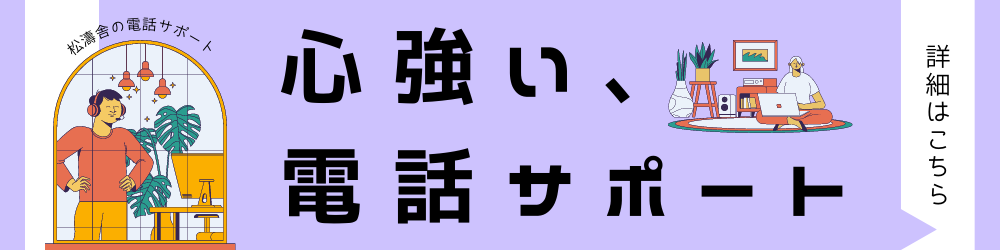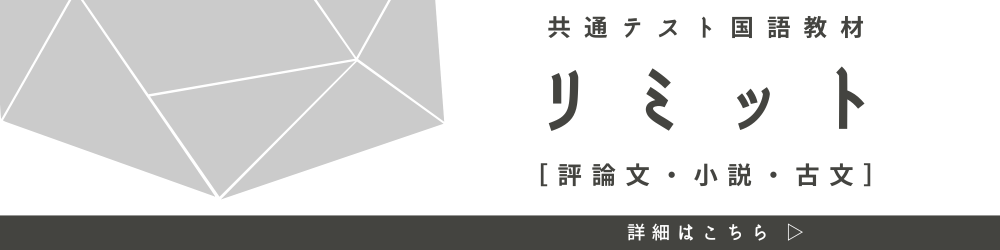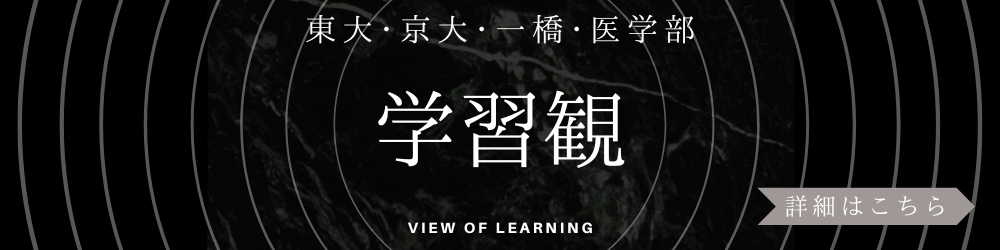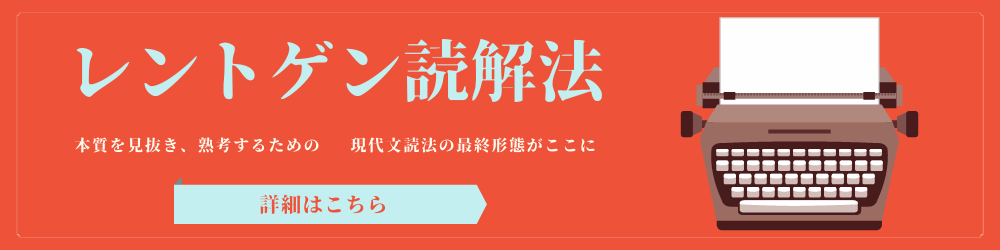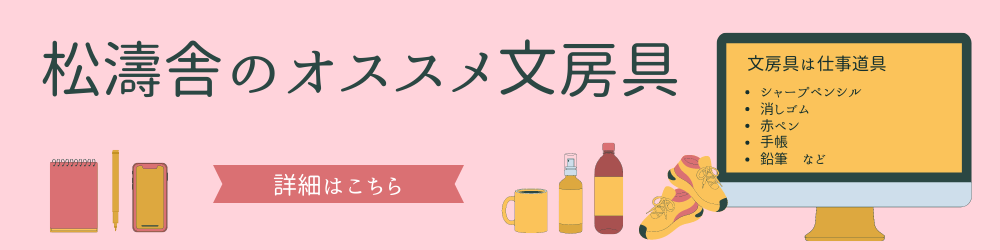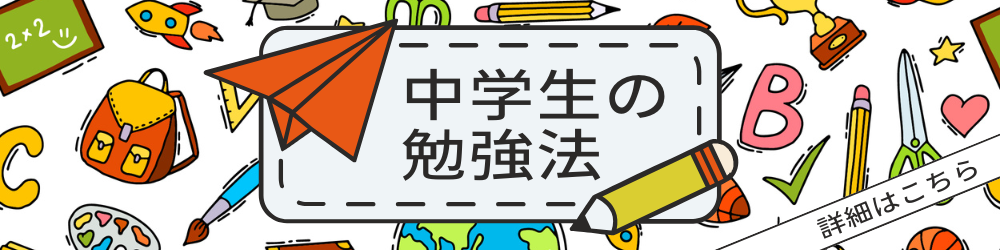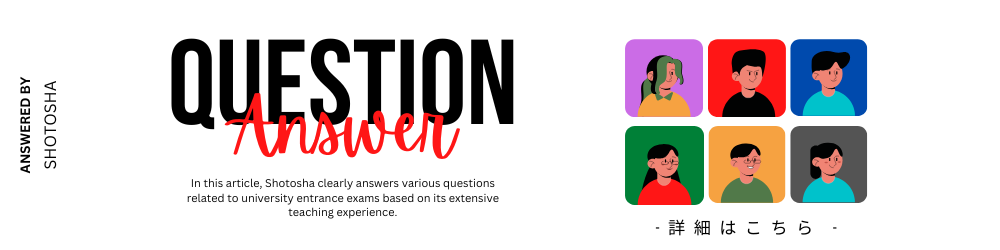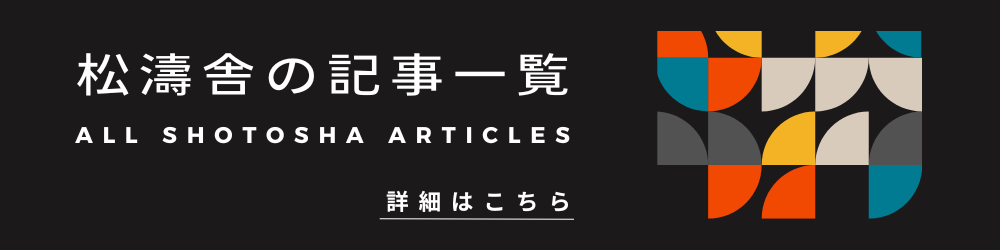▼受験観
・成功例には運などの要素も含まれているが、「〜したら失敗した」と言う例を聞き、その行動を取らないようにしていた。
・最終的には自分との戦いなので、昨日の自分に負けないように努力していた。そこから、R P Gのように昨日の自分よりレベルアップしていく感覚を楽しむようにしていた。
・自分が心から使いやすいと感じる問題集や参考書でないと続かないと思っていた。
・周りの同級生と同じ場所で勉強することで、常に刺激を受けるようにしていた。特に自分の中での「当たり前」の基準を日々高めることを意識していた。
▼記憶観
・大前提として、人それぞれに向いている方法が異なるため、様々な方法を試し、自分に合った方法だけを取り入れていました。
・自分は理解すると長い間記憶が定着したので、前後の文脈や周辺知識と同時に覚えていた。いわゆる丸暗記は極力行わないようにしていた。
▼モチベーション観
・英語が苦手だったため、朝一番に取り組むようにしていました。数学・社会が好きだったので、これらの科目と苦手科目を交互に勉強するようにしていた
・どうしてもメンタルに不調が出ている場合は、「昨日より成長した自分」に目を向けることで自己肯定感を高めていた。受験期終盤には、この思考が浸透し、モチベーションが下がるということはなかった。
▼数学
・数学は解法が明確で、他の科目に比べて曖昧さがないため、きちんと勉強すれば得点が一番伸びる科目だと思っていた。そのため、得点が悪いと一番落ち込んでいた科目でもあった。
・理解が定着への近道だと思ったので、解答解説を読み込み、他人に説明できるレベルまでしっかりと身につけるようにしていました。
・基礎を固めれば難問でも怖くないと考え、「至極の一冊だ」と思ったプラチカを完璧にできるようにしていました。
▼英語
全体
・最後まで苦手意識が抜けない科目だった。そもそも単語と文法を知らないと長文・リスニングもできないと思っていたので、単語・文法は毎日欠かさずやっていた。
・「先週解けなかった文法問題がわかった、先月分からなかった単語の意味が理解できた」など自分の成長に目を向けることで、勉強意欲を駆り立てていた。
単語
・感覚的には「気分転換で5分くらい単語帳でもみよう」というような勉強の仕方だった。10分くらいすると飽きてしまうので、長時間単語帳を見ることはしなかった。
・単語を単体で覚えてもすぐに忘れてしまうため、その単語を使う場面をイメージし、文章とセットで覚えていました。
・「鉄壁」をマスターすれば単語で困ることはないだろうと考え、ひたすら「鉄壁」を繰り返し見ていた。
文法
・あまり好きになれなかったので、得意科目を勉強して楽しくなったところで、やるようにしていた。
・「文法がわかれば長文・リスニングも解けるようになる!」と思って、モチベーションを保っていた。
・いいものを何周もやった方がいいと思ったので、とりあえず「ネクストステージ」を完璧になるまでやり込んだ。
長文
・とりあえず単語と文法を極めれば、読めない長文はないと思っていたので、単語と文法を重点的に学習した。
・加えて、言葉は「慣れ」が大切だと感じていたので、1日1長文を読むことを心がけていた。「この文章で作者が伝いたいメッセージはなんだろう?」と考えて読むと、案外楽しかった。
リスニング
・英語も所詮は言語なので、たくさん聞けば慣れて聞こえるようになるだろうと思っていたので、毎日30分リスニング教材を聞き、通学中に洋楽を聞いていた。
・長文と同様に「結局何を言いたいのだろうか?」と考えると、あまりストレスを感じることなく勉強できた。
自由英作文
・減点方式と聞いていたので、基本的には誰でもわかる簡単な表現しか使わなかった。新しい表現を使う際は先生に添削をしてもらい、使える表現の幅を少しずつ増やしていった。
精読
・ゲームのような感覚で解いていた。難しい構文をきっちり和訳できた時は、ゲームのボスキャラに勝ったような気分で楽しかった
・品詞が分かれば和訳もできると思っていたので、精読した方がいい箇所に当たった際は、まず初めに品詞分解を行っていた。
▼国語
現代文
・基本的に評論文が出題されるので、論理構造が分かれば解けると思っていた。具体的には、類推・比較・因果の3パターンが多いと感じていた。論理構造がわかった時は、英語の精読がうまくできた時と同様に嬉しかった。
・解答する際には、文章の論理構造をそのまま表現するということを第一に考えていた。数学の問題を解くように、論理的な解答を心がけていた。
古文
・英語と同じように、単語と文法を極めることが近道だと思っていたので、単語集と文法の参考書を一冊ずつやり込んだ。
・昔の常識と今の常識は違うので、異国の文化を学ぶ気持ちで、文章を読むことで古典常識を身につけていった。
漢文
・基本的には古文を同じだが、文章が古文に比べ短いので、単語と文法の理解がより重要だと感じていた。
▼世界史
・全世界というスケールの大きさから、一番興味を持って学習できた科目だったので、「疲れた時はとりあえず世界史」というような感覚で勉強していたので、全く苦ではなかった。
・範囲が広いので、興味を持って理解することが第一と考えていた。具体的には、ストーリーを妄想して、R P G感覚で学習していた。
・年号や人名などは、ストーリに付随して登場する付属品のような感覚で覚えていたので、たまにど忘れして思い出せないことがあったが、あまり気にしていなかった。
・文化史に出てくるような画家や作家などは、センター試験で判別できればいいと思っていたので、人名はアバウトに覚えていた(ボッカチオをボカッチオと覚えていても、無理に直そうとはしなかった)
▼日本史
・世界史に比べ、範囲は狭いのでマニアックな知識が必要だと感じていた。そのため、よりストーリーを明確にしておかないと理解しづらいと考え、出来事を鮮明にイメージするようにしていた。
・歴史的な事実には、必ず背景があると思っていたので、一連のストーリーで学習することを意識していた。そうすることで、小説を読んでいるかのような感覚になり、とても楽しく学習できた。
▼物理基礎
・学習時間をあまりかけられないので、初めにじっくり理解することを意識し、その後は演習しかやらなかった。気分転換する目的で、簡単な問題をたくさん解いていた。
▼化学基礎
・広く浅く理解できればセンター試験は乗り越えられたので、早めに全範囲に目を通し、残りの時間はひたすら問題演習に当てていた。興味が持てない科目だったので、割り切って気分が良い時にしか勉強しなかった。
「【学習観】Eさん(東大文系)」に関するQ&A
- 受験勉強における成功の秘訣は何ですか?
- 受験勉強の成功には、自分に合った参考書や問題集を選び、周囲の刺激を受けながら日々の努力を続けることが重要です。特に、他人との比較ではなく、自分自身の成長を意識することが大切です。
- 効果的な記憶法はどのようなものですか?
- 効果的な記憶法は、自分に合った方法を試し、理解を深めることです。丸暗記を避け、文脈や関連知識と一緒に覚えることで、長期的な記憶定着を図ることができます。
- モチベーションを維持する方法は?
- モチベーションを維持するためには、苦手科目を早めに取り組むことや、得意科目との交互学習が効果的です。また、自分の成長に目を向けることで、自己肯定感を高めることができます。
- 数学の勉強法はどのようにすれば良いですか?
- 数学は解法が明確な科目なので、基礎を固めることが重要です。解答解説を読み込み、他人に説明できるレベルまで理解を深めることで、得点アップにつながります。
- 英語の長文読解を効果的に行うには?
- 英語の長文読解には、単語と文法の理解が不可欠です。毎日1つの長文を読む習慣をつけ、作者の意図を考えながら読むことで、楽しみながらスキルを向上させることができます。
- 自由英作文の対策方法は?
- 自由英作文では、基本的に簡単な表現を使い、表現の幅を広げるために添削を受けることが重要です。新しい表現を少しずつ取り入れることで、減点を避けることができます。
- 国語の現代文対策はどうすれば良いですか?
- 現代文対策には、論理構造を理解することが重要です。類推や比較、因果関係を意識しながら問題を解くことで、解答力を高めることができます。
- 古文の学習法はどのように進めるべきですか?
- 古文の学習では、単語と文法を徹底的に学ぶことが近道です。また、異文化を学ぶ気持ちで文章を読み、古典常識を身につけることが大切です。
- 世界史を効果的に学ぶためのポイントは?
- 世界史を効果的に学ぶには、興味を持ってストーリーを妄想しながら学習することが重要です。年号や人名はストーリーに付随して覚えると、記憶に残りやすくなります。
- 物理基礎の効率的な学習法は?
- 物理基礎では、初めにじっくり理解し、その後は演習を中心に学ぶことが効果的です。気分転換に簡単な問題を解くことで、学習のリズムを保つことができます。