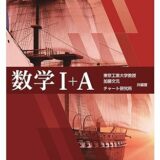前提
数学は、網羅系問題集『Focus Gold』や『青チャート』『レジェンド』を用いて、典型問題の解法を一通り学ぶことで(=8割以上の問題が瞬時に解ける状態)、偏差値67.5まで達成可能である。
つまり、網羅系問題集には数3Cまでの約1,000問の例題が含まれており、約800問を解けるようになれば、国公立医学部の合格者平均の7.5割を超えることができる。
実際、松濤舎ではこの方法で指導しており、毎年多くの医学部・上位校合格者を出している。
ただし、網羅系問題集にはいくつかの欠点がある。それは、網羅することを優先した結果、多くの人が苦手とする、より多くのバリエーションを通して理解を深めるべき分野が手薄になってしまうことである。
そのため、網羅系問題集を習得した後は、多くの人が苦手とする分野を集中的に克服することが効率的である。
ここでは、数3で多くの人が苦手とする体積問題を対象に、網羅系問題集を習得するだけでは足りないテーマの問題を収集した。
収集方法&選定方法
国公立医学部の過去10年分(2024〜2015年)を対象として問題収集した。うち、以下の問題を除いている。
・典型問題(=網羅系問題集で習得できる解法で対応できる問題)
・難易度が高すぎる問題(=本番で出題されても捨てるべき問題)
・計算が重いだけの問題(=本番で出題されても捨てるべき問題、かつ学習効率も悪い)
・学びが少ない問題(=その問題が解けるようになったところで次に繋がらない問題)
問題数
結果的に回転体の体積と非回転体の体積について、以下の問題数が選定された。
・回転体の体積・・・ 22題
・非回転体の体積・・・16題
問題一覧
回転体の体積
楕円の体積
鳥取大学 2019年 大問3(東進過去問データベース)
長崎大学 2016年 大問6(東進過去問データベース)
直線l周りの回転
長崎大学 2024年 大問7(東進過去問データベース)
信州大学 2016年 大問5(東進過去問データベース)
岡山大学 2019年 大問4(東進過去問データベース)
奈良県立医科大学 2017年 大問4(東進過去問データベース)
岡山大学 2024年 大問4(東進過去問データベース)
東北大学 2018年 大問6(東進過去問データベース)
直円柱との共通部分
大阪大学 2017年 大問5(東進過去問データベース)
東北大学 2022年 大問6(東進過去問データベース)
立体の回転
岡山大学 2017年 大問3(東進過去問データベース)
九州大学 2020年 大問5(東進過去問データベース)
神戸大学 2024年 大問4(東進過去問データベース)
京都大学 2020年 大問6(東進過去問データベース)
東京大学 2017年 大問6(東進過去問データベース)
平面の回転
福井大学 2023年 大問4(東進過去問データベース)
東京大学 2024年 大問5(東進過去問データベース)
京都大学 2016年 大問4(東進過去問データベース)
線分の通過領域
大分大学 2023年 大問3(東進過去問データベース)
東京大学 2022年 大問5(東進過去問データベース)
東京大学 2016年 大問6(東進過去問データベース)
京都大学 2023年 大問5(東進過去問データベース)
非回転体の体積
球の軌跡
富山大学 2019年 大問3(東進過去問データベース)
大阪大学 2015年 大問4(東進過去問データベース)
東京大学 2018年 大問6(東進過去問データベース)
円錐の一部
名古屋大学 2019年 大問1(東進過去問データベース)
東京大学 2020年 大問5(東進過去問データベース)
球を平面で切る
京都府立医科大学年 2017 大問3(東進過去問データベース)
福井大学 2017年 大問4(東進過去問データベース)
線分の通過領域
岡山大学 2020年 大問3(東進過去問データベース)
信州大学 2023年 大問7(東進過去問データベース)
四面体の共通体積
福井大学 2019年 大問4(東進過去問データベース)
福島県立医科 2021年 大問2(東進過去問データベース)
福島県立医科 2019年 大問2(東進過去問データベース)
初等幾何
新潟大学 2023年 大問2(東進過去問データベース)
山形大学 2022年 大問2(東進過去問データベース)
影部分の体積
九州大学 2015年 大問3(東進過去問データベース)
連立不等式で表された体積
大阪公立(市立)大学 2016年 大問2(東進過去問データベース)
所要時間
以下を参考にしてみてください。
・解答時間:25分以内/問 ※わからなければすぐに解答を見てOK
・採点時間:20分以内/問
したがって、1問あたり45分以内で進めることができ、全38問を約30時間で一通り演習できるということである。週末2日間で数3の体積問題が極められると考えたらコスパが高いだろう。
最後に
8割以上の体積問題が典型問題からの出題である。
つまり、ここにピックアップしなかった問題のほうが重要ということだ。
上記の問題リストはあくまでも網羅系問題集の8割以上が瞬殺できる状態になった人が対象である。網羅系問題集の習得が未完了の人は、典型問題の習得を優先しましょうね。
関連記事
『分野別マスター数学(数3体積)』に関するQ&A
- 数学の体積問題を効率的に学ぶ方法は?
- 数学の体積問題を効率的に学ぶには、まず網羅系問題集を使って典型問題を習得し、その後、特に苦手な分野に焦点を当てた問題集で演習することが重要です。松濤舎では、この方法で多くの合格者を輩出しています。
- 体積問題の解答にかかる時間はどのくらい?
- 数学の体積問題は、1問あたり解答時間25分、採点時間20分を目安にすると良いでしょう。全38問を約30時間で演習できるため、週末2日間で集中的に学ぶことが可能です。
- 数学の体積問題における典型問題とは?
- 体積問題における典型問題とは、網羅系問題集で習得できる解法を用いて解ける問題を指します。これらは受験において重要な基盤を形成します。
- 数学の体積問題で特に難しい問題は?
- 数学の体積問題で特に難しいのは、計算が複雑すぎる問題や学びが少ない問題です。これらは本番で捨てるべき問題とされています。
- 体積問題を解くために必要な基礎知識は?
- 体積問題を解くためには、立体の性質や計算方法、回転体と非回転体の違いを理解することが必要です。これらの基礎知識が問題解決に役立ちます。
- 数学の体積問題を集中的に学ぶメリットは?
- 数学の体積問題を集中的に学ぶことで、特定の分野に対する理解が深まり、解答スピードや正確性が向上します。効率的な学習が可能です。
- 体積問題の演習におすすめの参考書は?
- 体積問題の演習には、松濤舎のオリジナル教材や『Focus Gold』、青チャートなどの網羅系問題集が効果的です。これらは基礎から応用まで幅広くカバーしています。
- 数学の体積問題を解く際の注意点は?
- 数学の体積問題を解く際は、問題文をよく読み、与えられた条件を正確に把握することが重要です。計算ミスを避けるために、解答過程を丁寧に確認しましょう。
- 体積問題の演習を行う際のスケジュールは?
- 体積問題の演習には、週末を利用して2日間で集中して行うのが理想です。1日あたり数時間を確保し、問題を解く時間と復習時間をバランスよく配分しましょう。
- 数学の体積問題を解くための効果的な学習法は?
- 効果的な学習法は、まず網羅系問題集で基礎を固めた後、苦手分野に特化した問題集で演習を行うことです。理解を深めるために、解説をしっかり読み込むことも大切です。