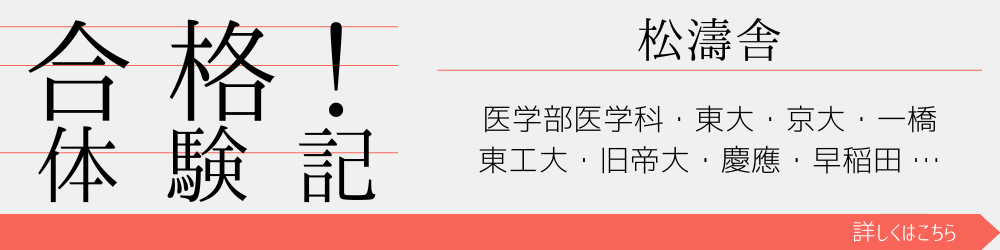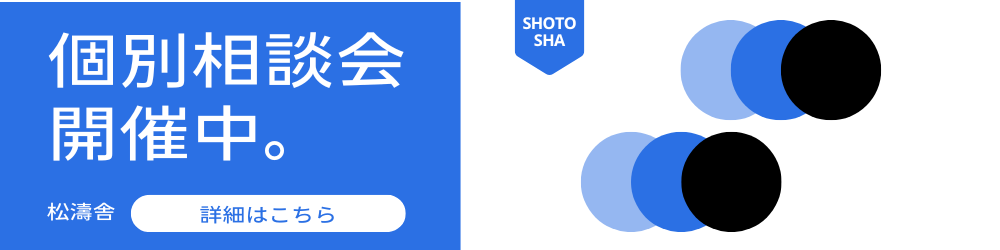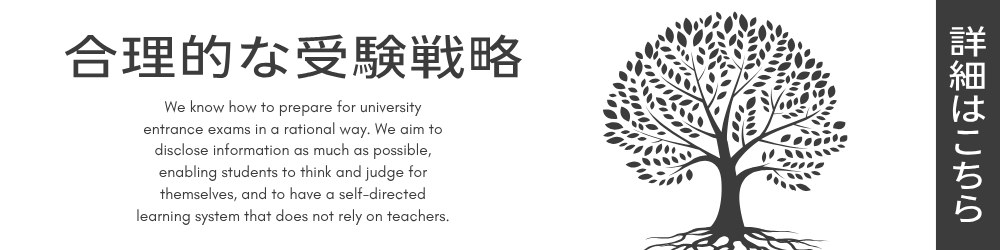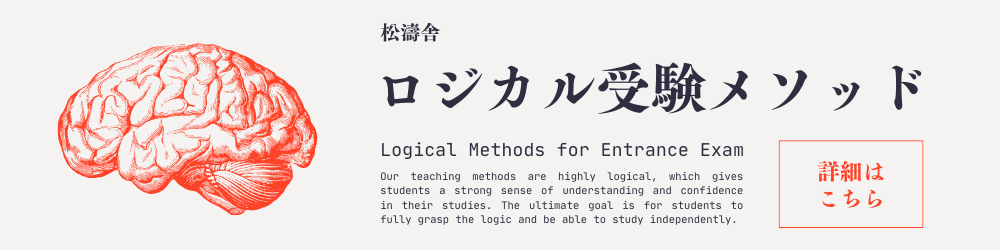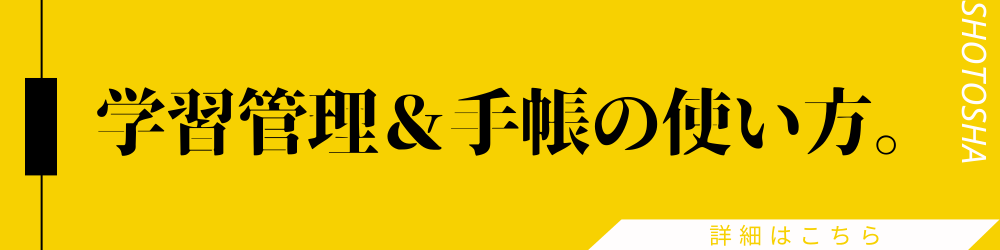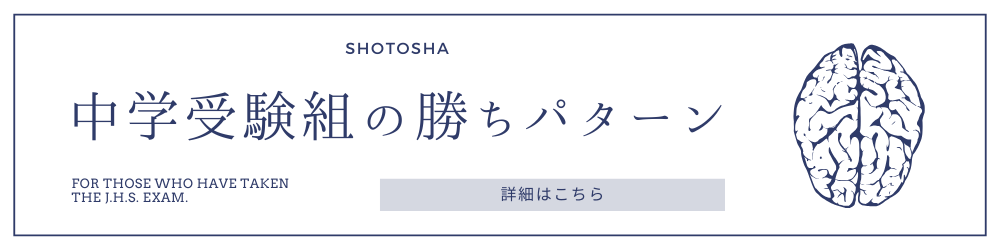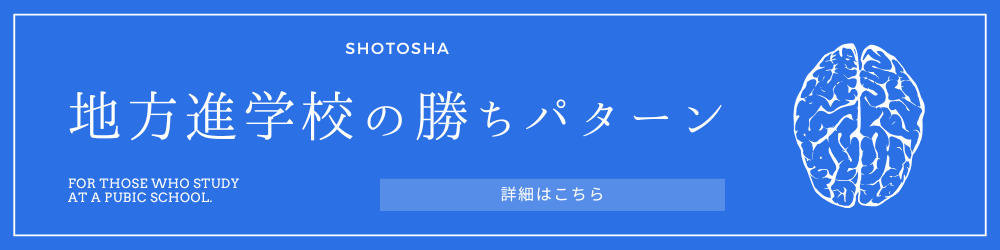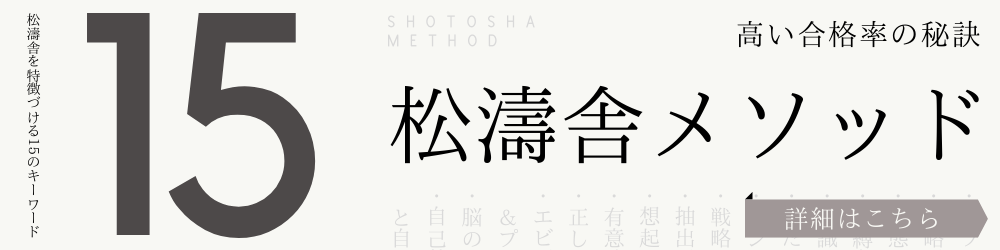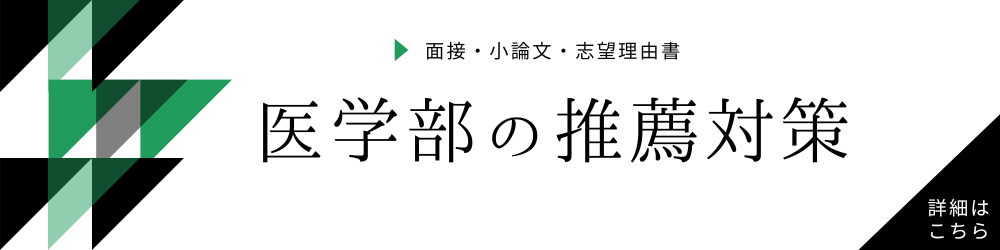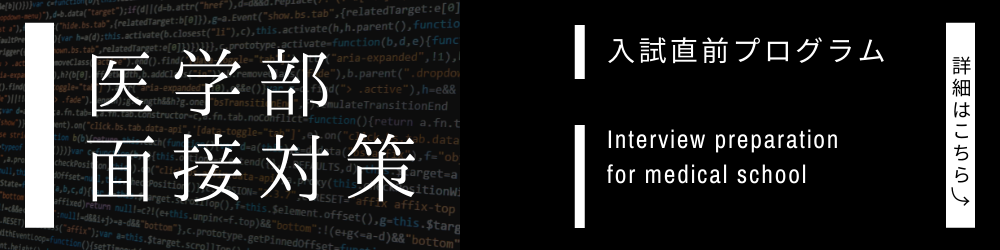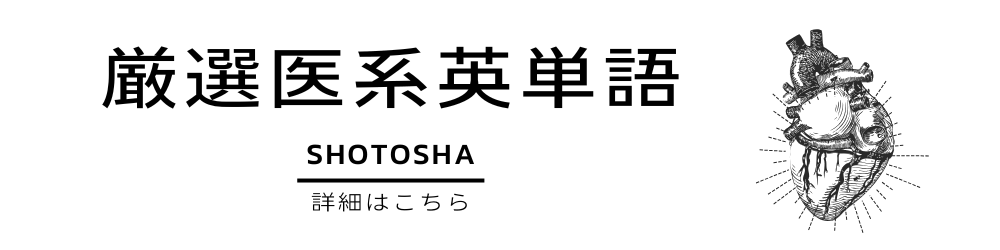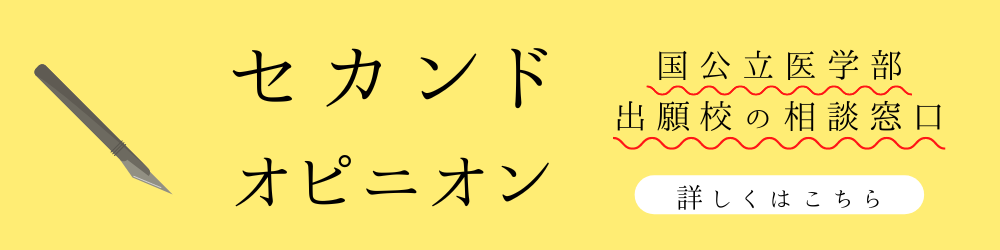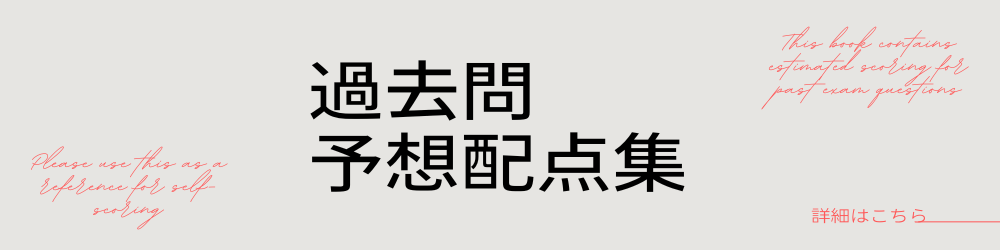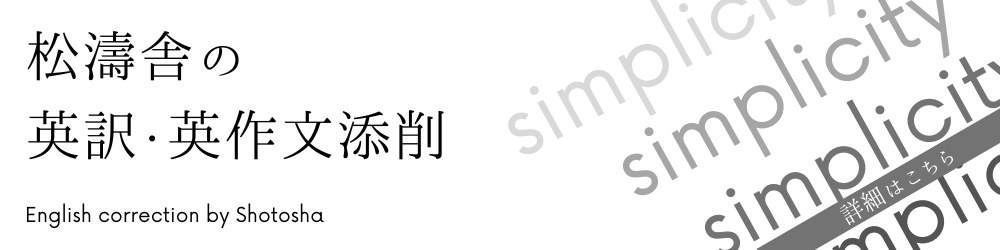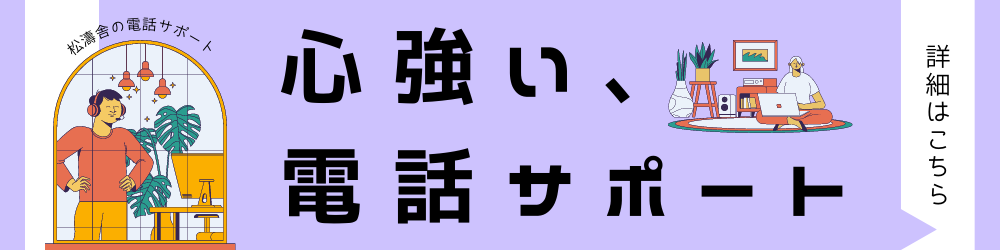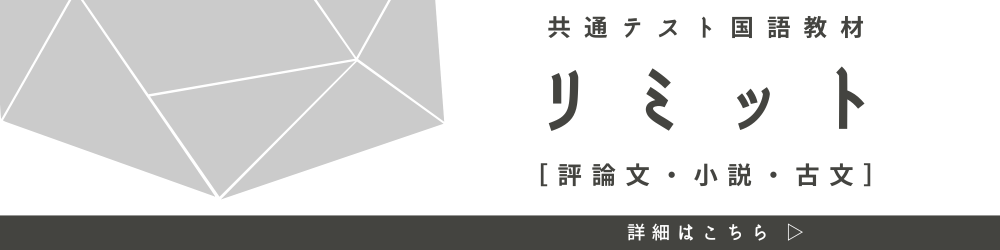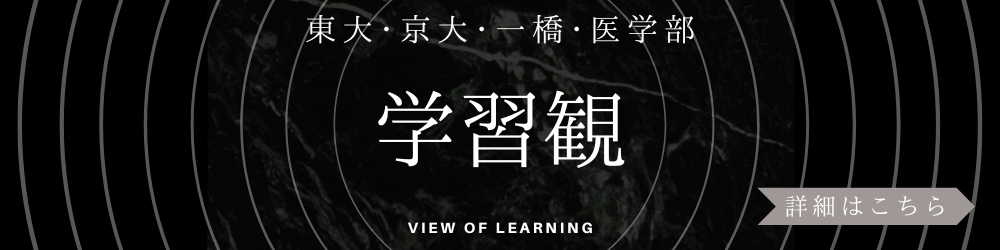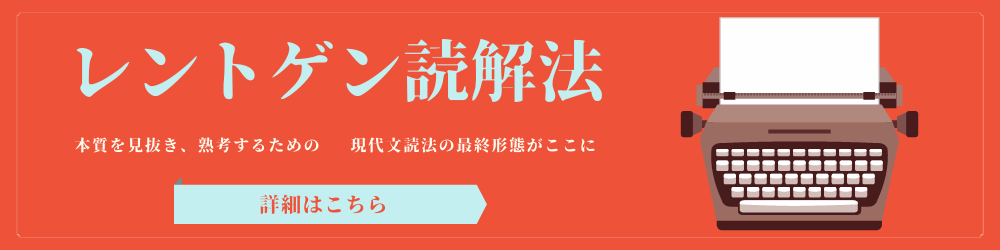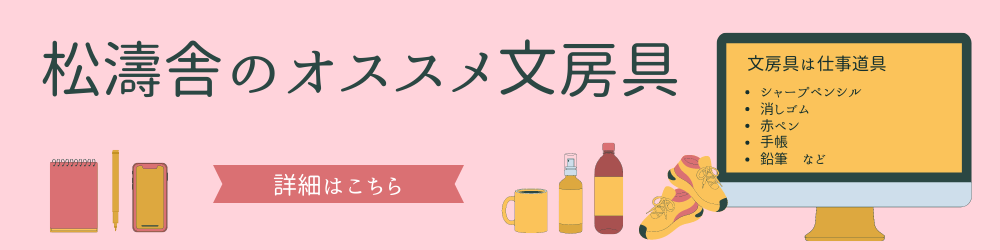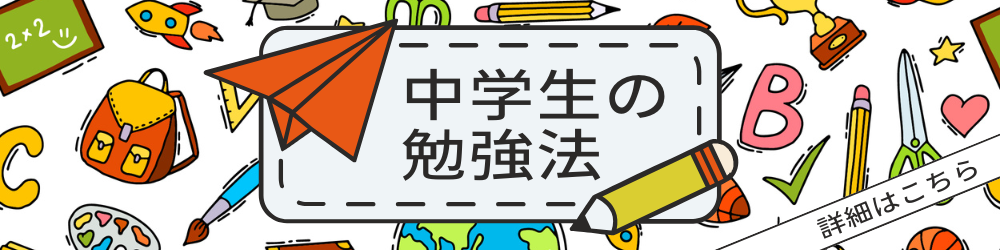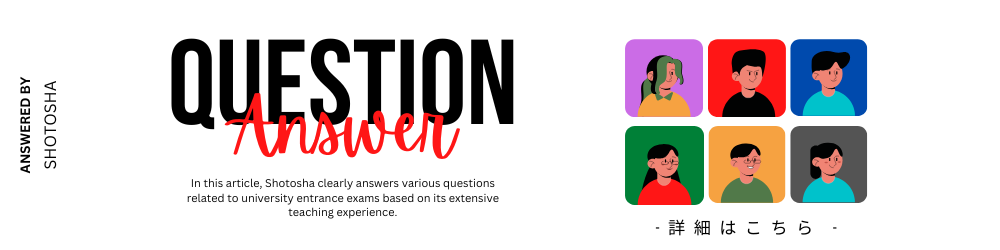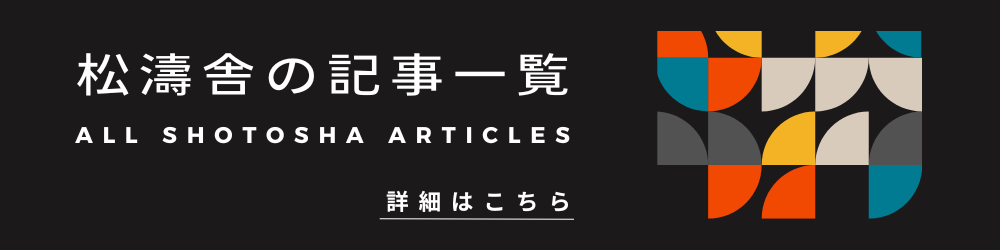▼受験観
・人生の最重要の分かれ道の一つととらえていた。わずかな差(例えば一点差)で一年以上の差(浪人など)が生まれる可能性があるため、確実に目標を達成する必要がある。そのため、目標は志望校よりも高く設定すべきだと考えていた。
・国公立は一校しか受けられないが、非医学部の理系の上位校はすべて国公立なうえに、学費も国公立と私立では大きな差があるので、ギリギリの実力で志望校を選ぶことはリスクが高いため、十分な余裕をもっていたいと考えていた。
・どれだけ努力しても、合格する確率が100%になることはないが、100%に近づけることは可能である。模試の結果にブレがあっても、取り組みを続けていれば実力が落ちることはないため、目先の成績に惑わされずに継続して努力することが重要だと考えていた。
・私立入試は国公立とは問題の性質が異なるため、私立大学を併願しても国公立受験にとっては足かせになる。そのため、国公立への単願で、気持ちと対策をそこに集中させるべきだと考えていた。
・東京大学の過去問・模試はたくさんストックがあるので、それを利用すれば他の大学の問題まで触れる必要は少ないと思っていた。基礎的な力を身に着けたら、過去問と模試を利用して、本番想定での演習を何回も繰り返して、本番の環境にできるだけ適応できるようにしていた。
・落ちた場合でも「運が悪かっただけ」と言えるように、また周囲にもそう言ってもらえるように実力をつけたいと考えていた。そのために本番想定での模試や過去問では点数と順位を意識して取り組んでいた。
・周囲は医学部を目指す人が多かったが、医学部は理科一類と同等やそれ以上の難易度の大学が複数存在し、志望する場合には複数の大学の対策を同時に行う必要があり、負担が大きいと考えていた。医学を志す理由がないのにそのような負担をかける必要はないと思ったため、国内理系では最高難易度でありかつ現実的に志望できる理科一類を目指すことにした。
・本番は絶対に緊張すると思っていたので、本番に近い環境での練習を繰り返せるようにしていた。また、テスト前には肩を回して、深呼吸をするなどのテスト前のルーティンをある程度決めていた。
・自分の実力を把握しておくこと、自分の伸びを見えるようにすることが大事だと考えていたので、過去問の得点は科目ごとにすべてメモしてまとめておくようにしていた。
▼記憶観
・受験当日に思い出せるかが重要で、当日覚えていれば翌日忘れていても良いし、前日までずっと覚えていても当日忘れていたら無価値と考えていた。
・暗記項目は定着をさせておくのが基本で、前日の詰め込みは計算に入れないようにしていた。定着をさせるためには、繰り返し学習することが重要だが、同じ方法で繰り返していてもマンネリになるし、少しの応用に対応できなくなるので、違う形で同じことを繰り返し学習するようにしていた。
・寝る直前に暗記系を重点的にやるようにしていた。翌日は、前日に暗記したものと、新しく今日覚えるものをやり、さらに次の日は前日と前々日のものを覚えたのち新しいのを覚える、、、という風に繰り返していた。
・書いて覚えるのは時間がかかるので、基本は読んで覚えていた。声を出せるなら出しいたほうがいいが、声を出せないときは心の中で読むようにしていた。
・単体で覚えるよりも何かしらの引っ掛かりを作った方が思い出しやすいと思っていたので、ダジャレや省略などが使えるなら積極的に使うようにしていた。
・前日、当日朝の詰め込みは有効だと思っていたので、とにかく直前でも拾いまくるようにし、一点でも多く積み上げようとしていた。
▼モチベーション観
・モチベーションは、一度落ちてしまうと立て直すのが大変なので、波は作らず、ずっと維持できるように努めていた。
・一度遊んでしまうと、自分の中での取り組みの基準が緩くなってしまうし、0と1の差は大きいので、ずっと遊びを0にキープすることが、自分に対しての遊んではいけないという縛りの強化につながると考えていて、ここまで我慢してきたのにここでゆるんだら全部パーだと意識するようにしていた。
・楽しさを見出さないと続かないので、なんとかして勉強を楽しくしようとしていた。友達と問題を出し合ったり、問題に対して意識的に面白いなぁとつぶやいたりしていた。
・志望校の情報をインターネットでよく見ていた。志望校の良い面をいっぱい見ることで、その大学に行きたいという気持ちが高まった。
・模試の冊子に名前を載せたり、高校同期よりいい成績をとったりということに喜びを見出していた。
▼国語観
現代文
・伸ばし方のわかりにくい科目だと感じていた。大失敗を避けるための最低限の力を身に着けることを目指していた。
・センター試験の現代文は、センター試験の科目の中で一番怖かった。大失敗がありうるので、重点的に対策をする必要があると感じていた。
・二次試験の現代文は、安定しにくいが、配点は小さい。勉強したら確実に伸びるというモノではないので、ある程度できるようになったら後回しにしてよいと考えていた。
・センターも二次もやることは変わらず、文章の論理構造を把握すればいいと思っていた。センターの勉強は二次の勉強にもなるといわれていたので、そういう意識で取り組んでいた。
・漢字、慣用句などの知識問題は配点が小さく範囲が大きいので、普段の常識力で対処すればいいと考えていた。
古文
・問題の難易度によって大きく左右される科目。自分ができなかったとしても、問題自体が難しいというときもあるため、点数のブレに惑わされないように気を付けていた。
・古文は文法と単語・用語の二種類のものから構成されていて、それは別個に扱えるので、文法を覚える、単語・用語を覚えるという二つの暗記勉強をそれぞれまとめてやるようにしていた。
・センターにおいては、現代文での時間を確保するためにできるだけ早く解くよう意識していた。実際に何分で解けるかを練習で繰り返すことで測っていた。
・センターの古文は基本的な事項を積み上げていくと着実に解けると思っており、文法の意味の把握、単語・用語の意味の把握ができているかどうかだけが問われるので、文章の複雑な読解をしようというより、丁寧に一つ一つ意味を取っていこうという意識で読んでいた。
・二次の古文は、文法と語句ができることは大前提で、そのうえに古文の背景知識を絡めていく必要があると感じていた。問題演習を通じて、古文におけるパターンをなんとなく読み込めるようにしておき、また、わからない文章があったとしたら、そこはゆっくりと文節を区切って分析して、意味を丁寧に拾っていた。知っている文法事項、単語から、知らない部分の意味を推測しようとしていた。
漢文
・漢文も古文と同じく、暗記が基本であり、またセンターは現代文のために早く解く必要があると考えていた。
・漢文は、センターでも二次でも、満点が狙いやすい科目といわれていたが、満点じゃなくても失敗をしなければ差が生まれるわけではないので、多少わからないところが当ても気にせず、大筋を外さないようにだけ気を付けていた。
・暗記科目という風にとらえていた。必要事項が暗記出来ていたら文章を読んで解釈する部分は自分の素の実力でなんとかなるだろうから、演習を増やしたりはしなくても大丈夫そうだと思っていた。
▼数学観
・英語と並んでウエイトの重い科目だが、すぐに実力が伸びるわけでもないし、演習もたくさんする必要があるから、早い段階から準備を始めなければいけないと思っていた。
・基本的なパターンに対応できていれば、大きな差がつけられることはないので、演習を繰り返して慣れることが大事だと考えていた。塾と高校で演習の機会はたくさん確保されていたので、自分でやるのはそこで間違ったとこの復習が主だった。
・センターの数学は、問題は難しくないし、二次の勉強をしていれば大丈夫だと考えていた。時間が足りるかが心配だったので、2か月前にためしに実際の時間で解いてできるかどうか確認してみたところ余裕があったため、直前に二次の頭からセンターの頭にするために3年分くらい解いた。
・二次の数学は、点数のブレが大きいと感じていた。数学一科目が原因で落ちるということが起こりうるうえに、どの分野で簡単な問題がでてくるかもわからないので、中程度の難易度の問題までをどの分野でも確実に解けるようにして、少しは失敗しても大丈夫なようにしようとした。
・東大の過去問をやる際にはできるだけ本番想定でやるために、6問セットで東進の過去問データベースから印刷して時間設定して解いて、鉄緑会の過去問集を軸にしながら、赤本と東大理系数学系統と分析を併用して、解説を読んでいた。
・数学は定義だけを読んでもよくわからないことが多かったので、問題演習をしながら理解していっていた。
▼化学観
・化学は中学の時から苦手だった。ミクロな事象とマクロな事象の間の結びつきがわかっておらず、教科書の説明ではいまいち理解できなかったので、より簡潔になっている参考書を読んだら理解できるようになった。
・化学は暗記ができないと話にならないと感じていたので、参考書を赤シートで隠しながら、何度も繰り返し読んで基礎的な事項を覚えた。
・センター化学は、二次の化学をやっていたら大丈夫と考えていた。細かい暗記事項もときどき出るが、10点以上の失点にはならないので、無視することにした。センター対策は基本せずに、直前で2年分くらい試しに解いたのみだった。
・二次の化学は、基本問題と応用問題の混合だったので、あまり化学が得意でなかった自分は取れるところを必死に探して拾うようにした。暗記事項単独でとれる小問を逃さないように、全体をまず見ることと時間配分に気を使っていた。
▼物理観
・頭を使って考えることが多く、数学に近い印象だが、数学よりは簡単だと思っていた。勉強を始めるのも、数学や英語がある程度固まった高2の夏ごろからで大丈夫だと思っていた。
・学校の授業での説明があまり理解できていなかったので、自分で参考書を買ってそれに沿って進めることにした。定番の参考書として、「物理のエッセンス」「名問の森」「難問題の系統と解き方」がインターネット上のサイトや友達との話で挙げられていたので、順番に進めた。
・「物理のエッセンス」と「名問の森」をやっている時期は、はじめは何もわからない状態からだったので、基本的な事項と解き方を定着させるために、「問題を解く→解説を読む→もう一度解説を見ずに問題を解く」を繰り返していた。
・センターの物理は、他の理系科目と同様に二次試験の対策をしていれば大丈夫だと思っていたので、直前に確認程度に1-2回取り組んだだけで、特別な対策はしなかった。数学と違い、時間にも余裕を感じていた。知識問題も少し出てくるが、間違えても5点程度で問題にはならないし、そのために対策をするよりはセンター国語や二次試験の対策をした方が点数効率がいいと考えていた。
・二次試験の物理は、大問ごとに一つの流れができているので、前から丁寧に解いていく必要があると感じていた。一番初めのところで間違えてしまうとそのあとも全部間違えてしまって大問まるまる0点になってしまうということもありうるので、基本的な事項に抜けがないように気を付けて対策をし、後半の難しくなっていく部分についてはできなくてもしょうがないと考えていた。途中経過を欠くことができたので、点数が来るかどうかはわからないが、とにかく解答用紙上に式を残しておくようにしていた。
・過去問演習は、鉄緑会の過去問集を使って行っていた。解説が充実しており、毎年どれくらいとれていれば十分かなども示されていたので、解くたびに出来を確認していた。
▼世界史観
・センター試験のみの利用だったが、他の科目の息抜きとして楽しみながら勉強することができた。点数が安定するまでは不安だったが、テストを受けるたびに順調に伸びていき、最終的には9割以上で安定するようになったので、やりがいがあった。
・社会の科目として、高2から、日本史、世界史、地理のうちから一つを選択することになっていた。成績は地理>世界史>日本史の順だったが、個人的に世界史の方が興味があったので、自分の興味を優先して世界史を選択した。
・一問一答などで詰め込んで勉強をする一方で、休み時間に問題をお互いに出し合ったり、事項について解説を行ったりすることで、遊び感覚で勉強をしていた。
・思い出すためには、できごとの連関を把握しておいて思い出すためのきっかけをつかみやすくすることが大事だと思っていたので、大きな流れを把握するために、複数の教科書を同時に読んでいた。
・基準となる年や出来事を設定して、そこから国の名前や王朝の変遷を再現してできごとも把握できるように、王朝をまとめた資料集のページをコピーして、上から隠して繰り返し暗記していた。
・隙間時間にも勉強できるように、資料集のまとめページをすべて印刷し、常に持ち歩いていた。
▼英語観
・受験において数学と並ぶ最重要科目。長い時間をかけて取り組まなければならない。数学と違って、点数のブレは少なく、実力をつければ安定した得点源になってくれると考えていた。
・英語は毎日触れていないとすぐに実力が落ちるという話をよく聞いていたので、高3になってからは、毎日何かしらの形で英語に触れ、直前期は毎日演習をするようにしていた。時間の都合に合わせて、1980-90年代の古い過去問から一題拾ってくるか、最近20年の問題から一年分を本番想定で解くかを交互に繰り返していた。
・センター英語は、問題の難易度としては二次試験の対策をしていれば問題ないが、時間との戦いになると聞いていたので、演習の際にはとにかく早く解くことを意識していたが、ある程度実力がついてくると時間にも余裕ができてきたので、センター直前期は英語に触れる機会の一つという意識で演習を行っていた。
・二次試験の英語は、英語の実力がついてきた2年生ごろから、安定した得点源だと思っていた。毎年、簡単な大問が入れ替わるので、きちんとすべての問題に触れることができるように、問題を解く順番、時間配分をきっちり決めて取り組んでいた。
単語
・単語はとにかく地道に覚えていくしかないと思っていた。鉄壁を軸に、学校で配布された単語帳を補助で使っていた。東大受験生の多くが鉄壁を使っているので、鉄壁の単語を覚えてさえいればビハインドになるということはないと思ったので、鉄壁に載っていない単語については単語帳などで覚えることはせず、演習や過去問で出るたびに学習していた。単語帳としては鉄壁だけを完璧にしようとしていた。
・単語単体で覚えるのは難しいので、他のものと関連付けて覚えられるようにしていた。単語を接頭辞や接尾辞で分解したり、絵を頭のなかにイメージしたりしていた。
・眺めているだけでは思い出しにくいので、声に出して勉強をしていた。発音を誇張することで印象に残りやすくしていた。
文法
・文法は、数がある程度限られていて参考書による差異は少ないと思っていたので、学校で配布されたスクランブル英文法を完璧にしようとした。赤シートを使って隠して、考えて、見て、答え合わせをして、間違えたものにはチェックをつけて翌日復習という流れを繰り返していた。
和訳・精読
・文の構造をとる→意訳(自然な日本語にする)という流れを意識していた。二次試験においては意訳ができているかどうかで差がつくと思っていた。過度に意訳をして元の文における単語が落ちないように、すべての要素は残しておくようにした(わかってるアピール)。わからない単語は周りの文脈や単語の特徴から推測しようとしていた。
・部分点を拾えるように、「文の構造」「単語」「文法」のそれぞれの事項でわかってるところがあれば、わかってる部分だけでもはっきりと入れ込んで和訳を作るようにしていた。
和文英訳・自由英作文
・和文英訳は、要素がある程度あれば部分点がもらえると思っていたので、丁寧に点数をもらいにいこうとしていた。
・和文英訳では、日本語の文章をまず平易にして、平易な文を英語にするという流れで考えていた。とにかく文意を残したまま簡単な構造と単語に落とし込むように取り組んでいたが、繰り返していれば伸びるとも思えなかったので、塾の授業や過去問演習で取り組む以上に特別な対策はしなかった。
・自由英作文は、どのように採点されているのか全く分からなかったので、減点だけはされないように文法と単語の間違いを起こさないよう簡単な単語と文法を使うよう意識していた。
・自由英作文は、文章の構造と論理をしっかり作りさえすれば、あとは簡単な単語と文法で書けばいいと考えていた。文章のプロットを作るところでは、日本語で書くと、そのあと英語にするところで苦労するかもしれないので、最初から英語の単語で書いていっていた。
長文
・長文問題(特に物語文)は、文章の設定や流れを少し読み違えるだけで、全部間違えてしまうということが起こるので、序盤は一文毎に丁寧に意味を確認していくようにしていた。
・文章を読むスピードを上げるために、演習を何度も繰り返していた。読むスピードを上げすぎると、意味をとらえられずに目が上を滑ってしまうことがあるので、そうならないぎりぎりのスピードで読むように意識していた。簡単な部分と難しい部分が分かれていたりもするので、難しいってなったらより集中して読むようにしていた。
リスニング
・リスニングは継続が大事といわれていたので、とにかく毎日触れるようにしていた。ポッドキャストやyoutubeも含めていろいろな教材を使って練習したが、できるだけスクリプトがついているものを選んで、複数回聞いてわからない部分はスクリプトを見て確認するようにしていた。
・直前期は本番でのスピード感やメモの取り方に慣れるために、東大本番想定での演習を過去問とキムタツの東大英語リスニングを使って繰り返していた。
・センター試験のリスニングは、東大の二次試験では点数には入らないうえに、二次試験のリスニングができれば対応できるので、ほとんど対策はしなかった。東大志望の同級生の中には、センター試験本番でもリスニングを受験せずに帰る人がいたが、センター試験の結果次第では、他の大学に志望校を変更する可能性もあったので、センター試験のリスニングも一応受験した。
・二次試験のリスニングは、配点が大きく、また実力のある人は安定するところだったので、自分も得点源にしなければと思っていた。リスニング中に他の問題も解く人もいるが、自分は一つのことに集中していないと、どっちつかずになってしまうので、リスニングの時間はリスニングだけに集中するようにしていた。
・リスニングの時間中に問題の選択肢まで目を通すのは難しいので、リスニングの勉強をする際には、下読みの練習もしていた。事前に選択肢を見て、注目する要素に線を引いたり、選択肢を頭の中に絵としてイメージする練習を繰り返していた。実際に行うには何分ぐらい必要かを事前に測っておいて、直前を中断しやすい文法問題にすることで、リスニングの下読みの時間を確保していた。
▼模試観
・夏と秋にある冠模試は、自分の実力と周りの相対位置を測るいい機会だと考えていて、本番を想定して臨んでいた。自分が中高一貫校や塾に通っていたことから、公立高校で部活を長くやっている層が秋以降に伸びてきて自分を逆転するんじゃないかと思い、冠模試では合格ラインぎりぎりではだめで、余裕のある順位を取り続けなければならないと考えていた。
・冠模試を本番想定で行うために、前日に過去問や模試の過去問で演習をしたり、単語を直前で読んだりと、本番の前日に行う候補のことをいくつか試していた。
・本番でも同じ調子が発揮できるように、模試の際には、カレドショコラのチョコレートを各科目の直前に食べて緑茶を飲む、昼ごはんはコンビニのおにぎり二つで一つは昆布、という風に食べるものを決めていた。
・学校でやる進研模試などのセンターでも二次でもない模試は、演習の機会としてとらえていて、順位はあまり気にせず、間違えたところの復習と反省に重点を置いていた。
・センター模試は、高2のころは自分の実力を測り苦手科目を割り出すものととらえており、3年のころは本番想定で行う演習の場と考えていた。順位はあまり気にせず、9割という目標を達成できるかどうかを重要視していた。
・二次試験の模試では、夏までは物理や化学が完成していなかったために、数学と英語の点数は深刻にとらえていたが、理科はしょうがないと考えていた。
▼塾観/予備校観
・塾はお金がかかるのであまり通いたくなかったが、数学と英語は時間がかかる上に配点が大きいとのことだったので、塾に通うことにした。塾を選ぶ際には、他の人と差をつけられないことを重要視して、他の多くの東大受験生が通っている鉄緑会に通うことにした。
・鉄緑会は実績が十分にあったので、英語と数学に関しては鉄緑会のカリキュラムに合わせていれば問題ないと思っていた。
・東進の東大特進が無料で利用できたので、林修の現代文と、苑田の物理の講習を受けていた。そこですべてを学ぶわけではなかったが、考え方のコツや、自分にこれまでなかった考え方での問題解法を学ぶことができた。
・集中して自習できる環境が欲しかったので、近くの東進衛星予備校を利用していた。参考書もたくさん置いていたので、利用した。チューターの人や校舎のスタッフもいたが、東大受験に対応できる人はいなかったので、自分の好きなように勉強を進めさせていただいていた。
・塾講師だからといって、個人的経験による部分は大きく、自分との相性の問題もあると思っていたので、自分が納得のいくアドバイスだけを聞くようにして、よくわからないアドバイスに関しては納得いくまで質問するようにしていた。
▼参考書観/問題集観
・参考書は、英単語、英文法など種類ごとに、学習範囲を網羅しているものを一冊完璧にするように取り組んでいた。そのうち場所によって覚えたりもしてしまうので、確認程度に他の参考書も使ったりしていたが、それはあくまで補助的な機能だけで、本腰を入れて取り組んではいなかった。
・問題集は、単元を学習している際には定着を図るために平易なもので学習した範囲の復習をしていた。演習期には、自分の学習用として利用していたが、それよりも過去問や模試の問題を利用した学習を重視していたので、問題集は弱点補充を目的としていた。
▼友人観
・友達を自分の実力の伸びを測るバロメーターとして利用していた。高1時点で同程度の実力で同じく東大理科一類志望の人を数人ライバル視し、一般の模試や学校での中間・期末テストではその人たちよりいい成績をとれるようにと意識していた。
・受験勉強と友達関係は別に考えていたので、どういう人と仲良くするかを受験基準で考えることはなく、楽しい人と一緒にいた。ただ、直前期は同じ世界史を受ける人同士で、問題を出し合ったりという風に一緒に勉強をすることもあった。
・周りに何人かとびぬけて優秀な人がいたので、わからないことについてその人たちに質問したりしていた。学校の先生よりも相談しやすく、貴重な存在だった。
▼学校観
・基本的に学校の進度やレベルが他の学校より高いと思っており、また毎年東大にどれくらいの人が合格するかというのが分かっていたので、学校内での順位はかなりあてになると思っており、模試での校内順位は多少気にしていた。
・いくつかの科目の授業については途中でついていくことができなくなり、一度ついていけなくなると追いつくのが難しかったので、そういう科目は参考書で対策すると決めて、授業中も参考書をずっとやっていた。
・学校は勉強する場所という意識はあまりなかった。授業時間は演習になると集中して取り組んでいたが、講義は世界史などの一部の科目を除いてあまり集中していなかった。受験勉強は、塾と自習でやるものという意識が強かった。
▼部活観
・部活は毎年3年生の6月に引退することになっていたので、それまでやろうと決めていた。部活をするというのは大前提だったので、受験勉強よりも優先順位は高かった。
「【学習観】KIさん(東大理系)」に関するQ&A
- 東大受験における学習観はどのように形成されるのか?
- 東大受験においては、目標設定が重要です。志望校より高い目標を設定し、確実に合格するための戦略を練ることが求められます。模試や過去問を活用し、実力を把握しながら継続的に学習する姿勢が大切です。
- 受験勉強における記憶の重要性は?
- 受験当日に思い出せることが最も重要です。定着を図るためには繰り返し学習が必要ですが、同じ方法ではマンネリ化するため、異なる形での復習が効果的です。直前の詰め込みも有効とされています。
- 受験生のモチベーションを維持する方法は?
- モチベーションを維持するためには、勉強を楽しむ工夫が必要です。友人と問題を出し合ったり、志望校の良い面を意識することで、勉強への興味を高めることができます。
- 数学の勉強法として効果的なアプローチは?
- 数学は演習が重要です。基本的なパターンを繰り返し学び、問題演習を通じて理解を深めることが求められます。過去問を本番想定で解くことで、実力を確認することも効果的です。
- 英語の長文読解を効率よく行うには?
- 長文問題では、文章の流れを正確に把握することが重要です。演習を重ね、読むスピードを上げつつ、意味をしっかりと捉える練習が必要です。部分点を意識した解答も効果的です。
- 模試を受ける目的は何か?
- 模試は自分の実力を測るための重要な機会です。本番を想定して取り組むことで、実力を確認し、必要な対策を見つけることができます。順位よりも自己の成長を重視することが大切です。
- 参考書選びのポイントは?
- 参考書は、学習範囲を網羅しているものを一冊完璧にすることが重要です。補助的な参考書は確認程度に使い、主要な参考書に集中することで効果的な学習が可能になります。
- 受験勉強における友人の役割は?
- 友人は自分の実力を測るバロメーターとして重要です。ライバル視することで、モチベーションを高めることができます。また、共に問題を出し合うことで、学習を楽しくすることもできます。
- 国語の現代文対策にはどのようなアプローチがあるか?
- 現代文は論理構造を把握することが重要です。センター試験と二次試験の対策を兼ねて、文章の論理を理解する練習を行い、基礎知識をしっかりと身につけることが求められます。
- 受験における塾の役割は何か?
- 塾は専門的な指導を受ける場として重要です。特に数学や英語のように配点が大きい科目では、他の受験生との差をつけるために通う価値があります。自分に合った塾を選ぶことが成功の鍵です。