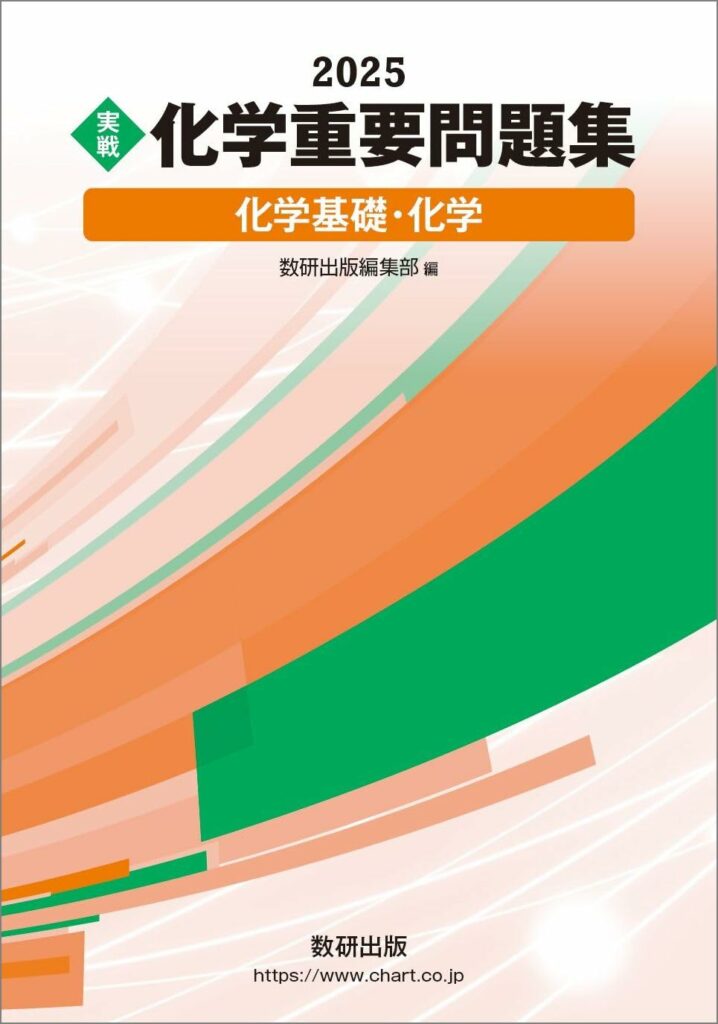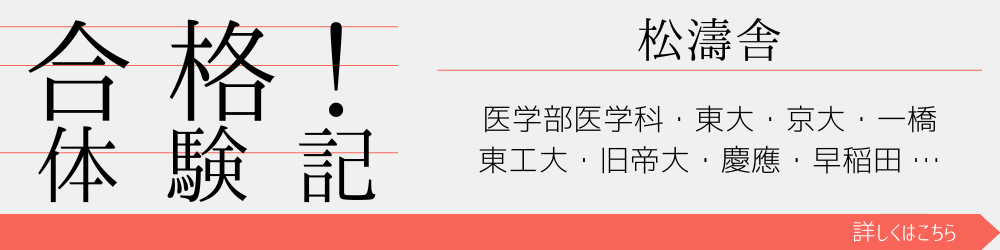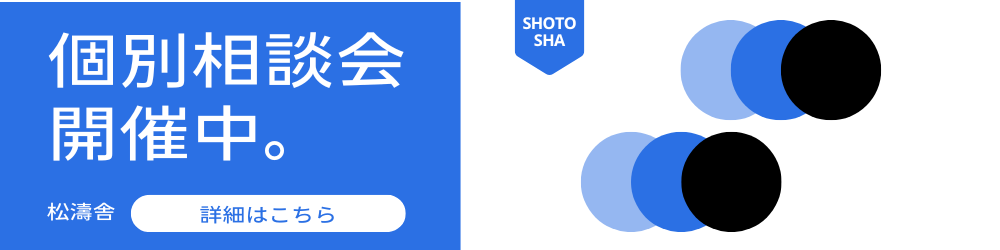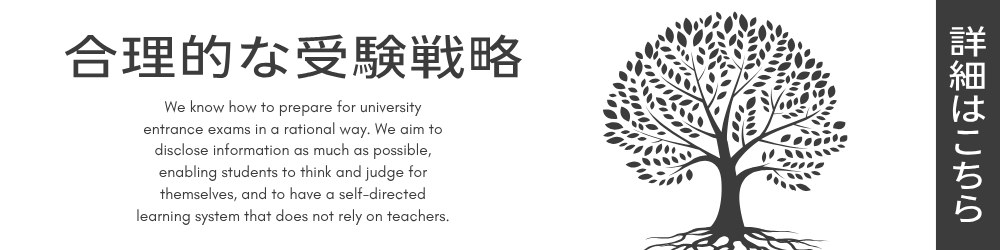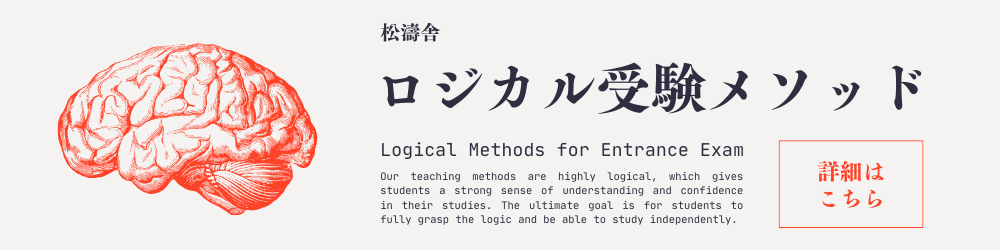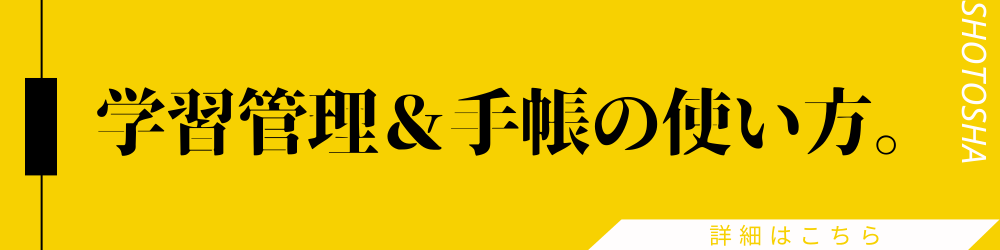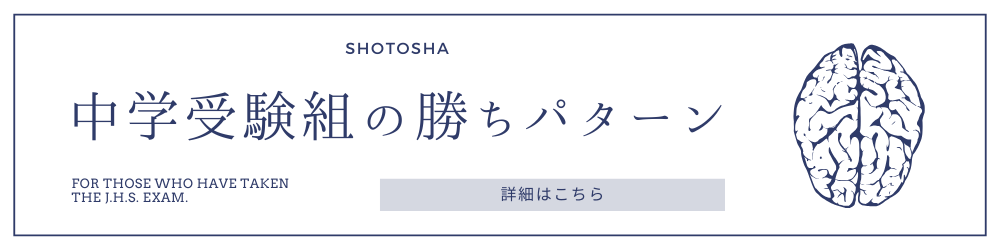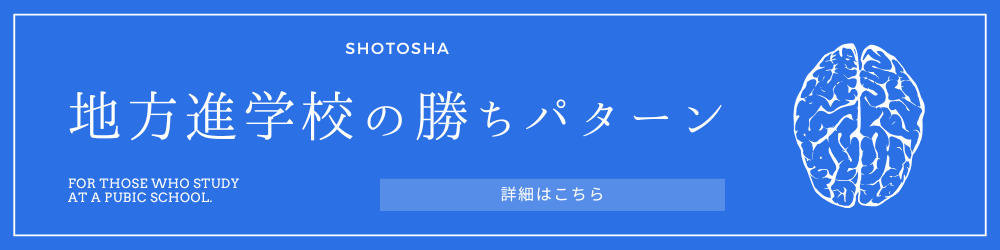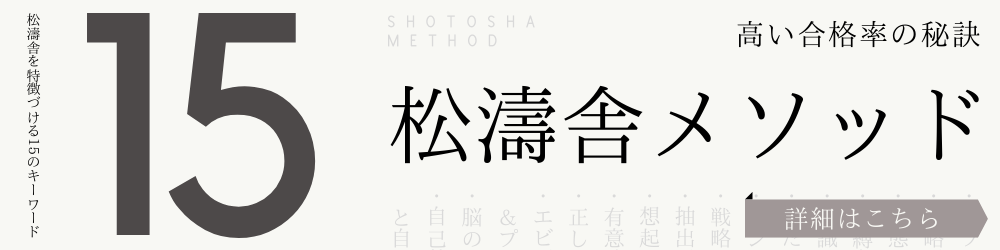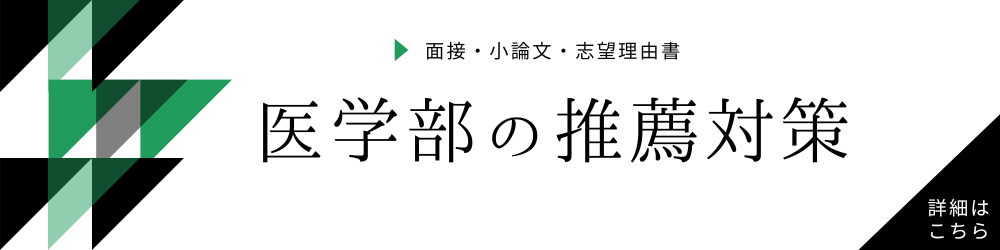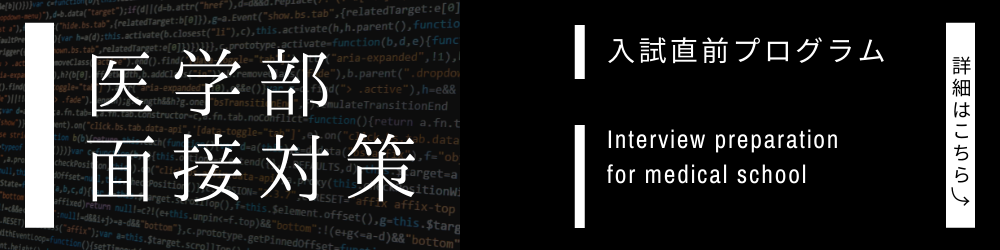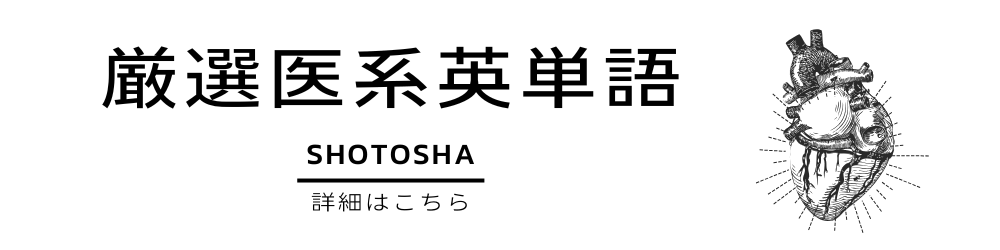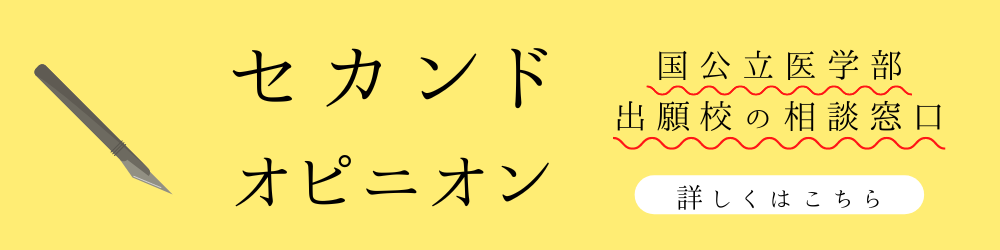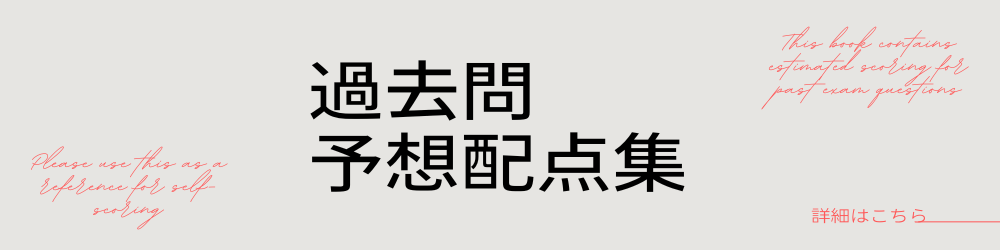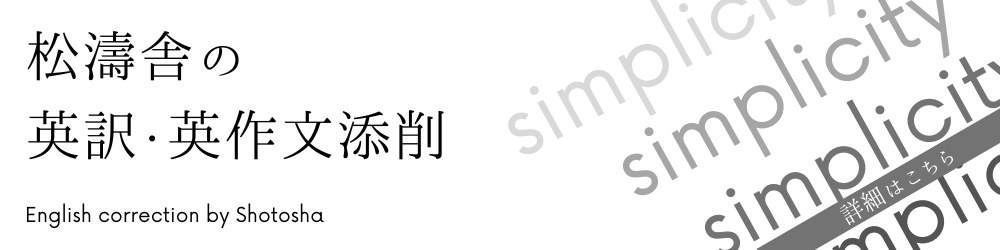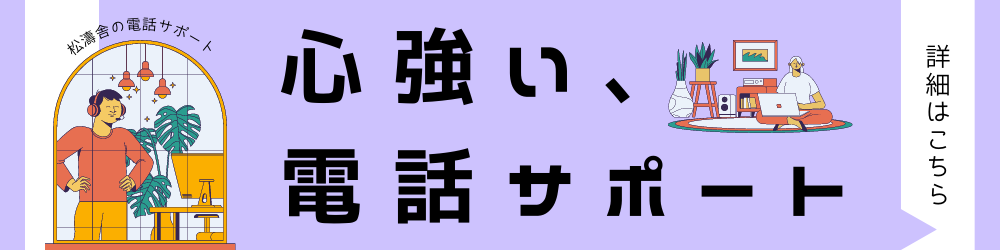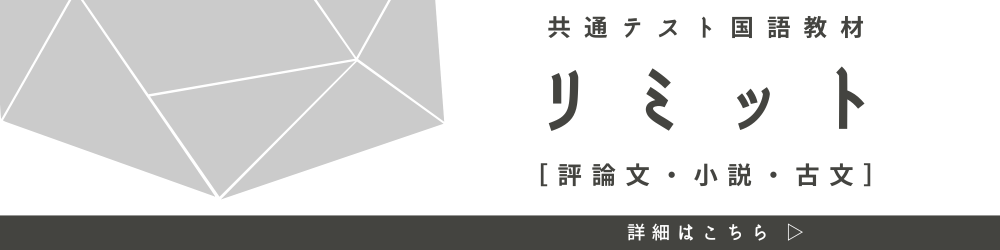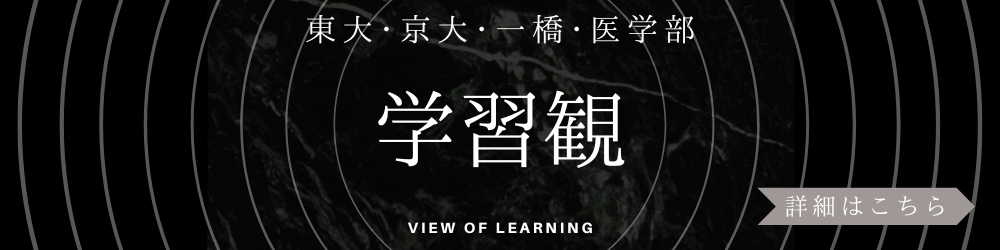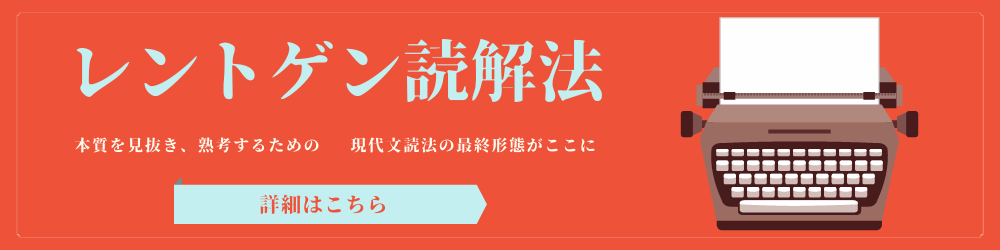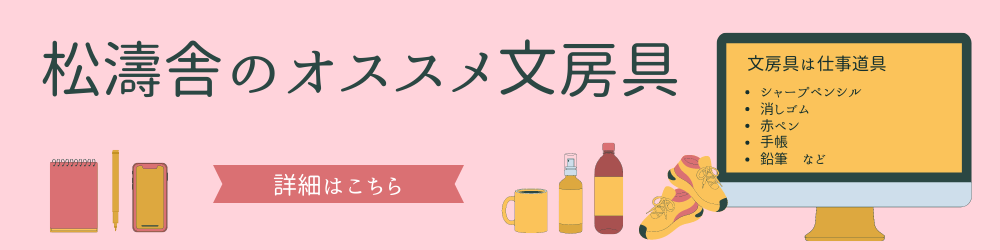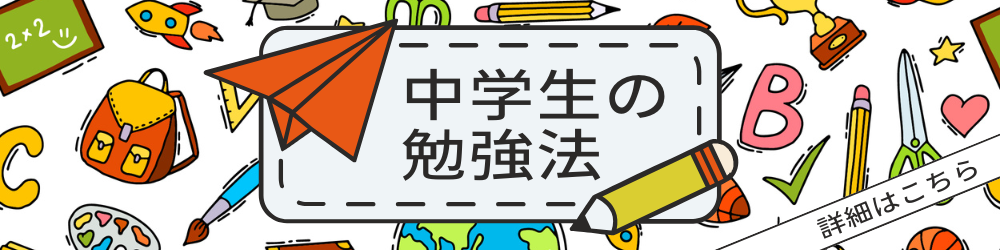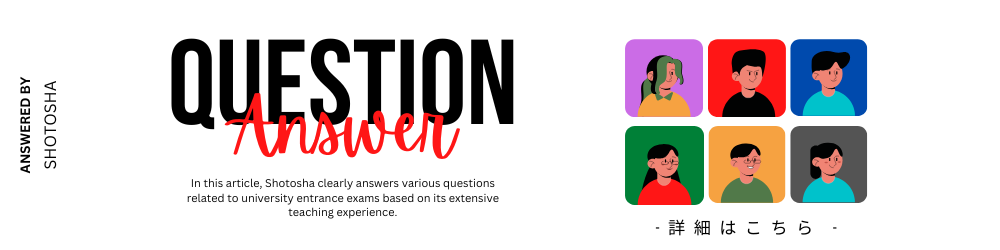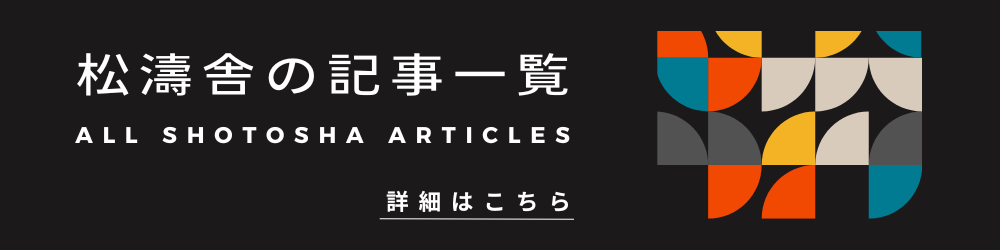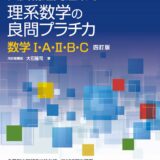『化学の重要問題集』で合格可能な医学部・上位校
松濤舎での合格実績を以下に記載します。
・医学部医学科
大阪大学、東京科学大学、千葉大学、横浜市立大学、筑波大学、広島大学、金沢大学、新潟大学、熊本大学、信州大学、岐阜大学、浜松医科大学、鳥取大学、愛媛大学、大分大学、福島県立医科大学、群馬大学、高知大学、宮崎大学、香川大学、富山大学、弘前大学、秋田大学、慶應義塾大学、東京慈恵会医科大学、順天堂大学、日本医科大学、国際医療福祉大学、自治医科大学、昭和大学、東京医科大学、東邦大学、日本大学、聖マリアンナ医科大学、東海大学、帝京大学、東京女子医科大学、埼玉医科大学 ほか
・他学部
東京大学、京都大学、大阪大学、名古屋大学、北海道大学、東北大学、一橋大学、神戸大学、慶應義塾大学、早稲田大学 ほか
※代替可能な問題集を使った合格実績も含む。
『化学の重要問題集』の習得レベル
レベル1:問題の5割を手を止めず、自力で解くことができる。
レベル2:問題の8割を手を止めず、自力で解くことができる。
『化学の重要問題集』の特徴
『化学の重要問題集』はよく知られた問題集です。最大の特徴は「多くの人が使用している」という点です。
「この特徴だけで本書を使用する理由になる」と考える人もいます。「解説がわかりづらい」「本当に重要な問題なのか疑問」という感覚を大事にする人もいます。
松濤舎ではどちらの意見も重要としつつ、本書『化学の重要問題集』は指定教材に入れていません。学校から指定されて、宿題や定期テスト対策、長期休みの課題として取り組む分にはいいと思っています。
また、他問題集を通して化学の各テーマの真髄が理解できてから、改めて本書に取り掛かって「解けるようになっていることを確認」するにはいいと思います。
しかし、本書を通じて化学の理解を深めようとすることは、ましてや化学が苦手な人が本書を通して得意になろうとすることは、ほぼ100%の確率で効果が薄れるため、推奨しません。 |
『化学の重要問題集』の使い方
すでに教科書傍用問題集が8割以上解けている状態の人は、難しいと感じてもすぐに解説は見ず、少なくとも3分程度は考えてみてください。
一方、教科書傍用問題集が8割以上解けておらず、『化学の重要問題集』が学校の宿題や定期テスト対策として着手しないといけない人は、解説冊子を開きながら本書を進めましょう。
解けなかった問題だけ復習するため、解けた問題には○マーク、解けなかった問題には×マークを累積していきましょう。
『化学の重要問題集』の前にやるべき問題集
教科書傍用問題集(『セミナー化学』『リードα化学』『エクセル化学』『センサー化学』『ニューグローバル化学』等)が8割以上解けるようになりましょう。
『化学の重要問題集』の改善点
『化学の重要問題集』の改善点は、数値代入を中心とした解説である点です。
化学は現象理解ありきのため、何が起きているか理解しているからこそ正しく立式できます。しかし、本書は参考書でないということもあり、現象理解の促進はしません。
また、できるだけ最新年度の問題を選定しようという方針は素晴らしいのですが、その結果、重要でない問題(=テーマの理解を深める問題)が選ばれているように感じます。
松濤舎では、『化学の重要問題集』の上位互換として、典型テーマを網羅的に扱いながら、全て過去問ベースとなっている『化学の良問問題集』(旺文社)を指定教材としています。
本書は「典型問題をちょっとずらした問題」が載っているため、典型問題の理解補助になりますし、当該テーマの理解促進にもなります。決して難問が載っているわけではないのですが、そもそも当該テーマの理解を深めるために難問を解く必要はないのです。
実際、多くの卒業生が、指定教材の中でも良かった問題集に『良問問題集』を挙げており、過去問や本番入試でも『良問問題集』の類題ばかりが出題されたと言っています。
『化学の重要問題集』の使用場面
『化学の重要問題集』は学校指定でない限り個人的に購入する必要はないのですが、学校指定になっていることも多いです。高3から『化学の重要問題集』を使った授業が始まる高校もあります。
しかし、基本的には「化学嫌いを生む可能性が高い問題集」と考えていますので、宿題で自分が解いてくるよう指定された問題以外には手を付ける必要はありません。
一方、先生がやってくるよう指定する問題は、『化学の重要問題集』の中でも比較的基礎的な問題だったり、厳選してピックアップされていることがありますので、そういった問題は着手してもよいでしょう。
特にA問題であれば難易度は教科書傍様問題集にも掲載されているレベルなので着手してよいです。
『化学の重要問題集』の解説につまずいたら・・・
『化学の重要問題集』の解説でつまずいたり、式変形はわかったけど、その裏で何が起きているのか現象がイメージできない場合は、化学が得意な友達に聞いているとよいです。
東大・京大・一橋・医学部生にヒアリングした「学習観」のうち「友人観」の回答で、友人はライバルではなく助け合う存在であり、わからない問題があったら聞き合っていたと答える人が非常に多かったです。
【決定版】化学の勉強方法と年間スケジュール
医学部・上位校受験生向けに、化学の勉強方法と年間スケジュールをまとめました。参考にしてみてください。
『化学の重要問題集』に関するQ&A
- 『化学の重要問題集』のレベルはどのように設定されていますか?
- 『化学の重要問題集』は2つのレベルに分かれています。レベル1は問題の5割を自力で解ける状態、レベル2は8割を解ける状態です。これにより、使用者の理解度に応じた学習が可能です。
- 『化学の重要問題集』の主な特徴は何ですか?
- 本書の最大の特徴は、多くの受験生に使用されている点です。ただし、解説がわかりにくいとの意見もあり、使用目的に応じた適切な活用が求められます。
- どのように『化学の重要問題集』を使うべきですか?
- 教科書傍用問題集が8割以上解ける人は、解説を見ずに考える時間を持つべきです。逆に、解けない問題が多い場合は、解説を参照しながら進めることが推奨されます。
- どの問題集を先にやるべきですか?
- 『化学の重要問題集』に取り組む前に、教科書傍用問題集(例:『セミナー化学』など)を8割以上解けるようにすることが重要です。基礎が固まってから本書に進むと効果的です。
- 『化学の重要問題集』の改善点は何ですか?
- 本書は数値代入中心の解説が多く、現象理解を促進しない点が改善点です。化学の理解には現象を理解することが重要であり、参考書としての役割が不足しています。
- 『化学の重要問題集』はどのような場面で使用されますか?
- 学校指定で使用されることが多く、高3から授業で使われる場合もあります。しかし、個人的に購入する必要はなく、指定された問題に集中することが推奨されます。
- 解説でつまずいた場合、どうすれば良いですか?
- 解説でつまずいたら、化学が得意な友人に聞くことが効果的です。多くの受験生が友人との助け合いを通じて理解を深めています。
- 『化学の重要問題集』の使用による合格実績はどうですか?
- 使用者の中には、合格実績がある人もいますが、化学が苦手な人には向かない問題集とされています。適切な使い方が重要です。
- 『化学の良問問題集』との違いは何ですか?
- 『化学の良問問題集』は典型問題を網羅的に扱い、過去問ベースで理解を深めるのに適しています。一方、『化学の重要問題集』は難易度が高く、基礎的な理解を促進しません。
- 受験生が『化学の重要問題集』を使う際の注意点は?
- 本書は化学嫌いを助長しやすい問題集とされているため、宿題以外の問題には手を付けないことが推奨されます。基礎的な問題から着手することが重要です。