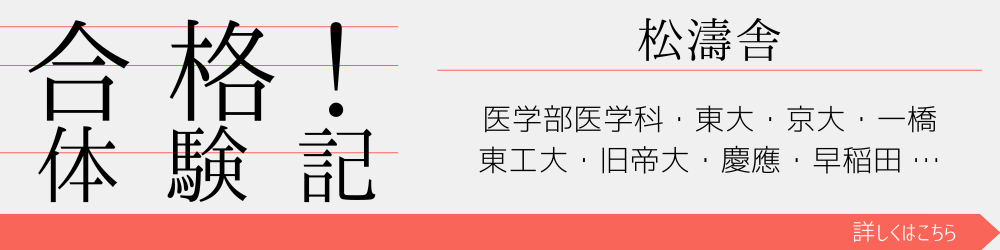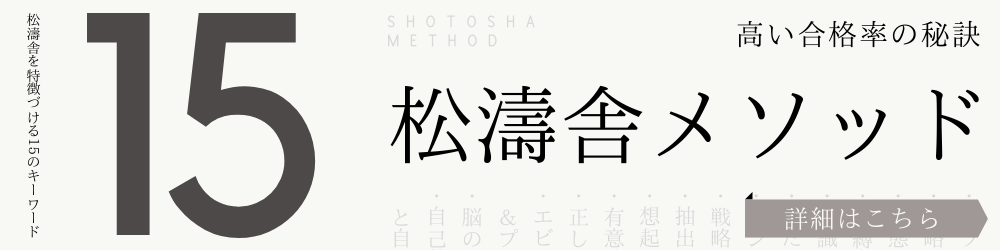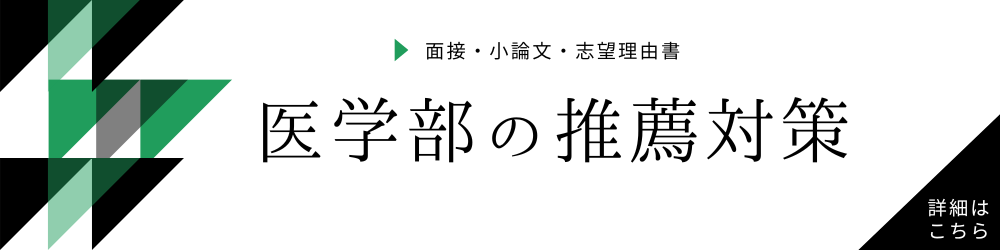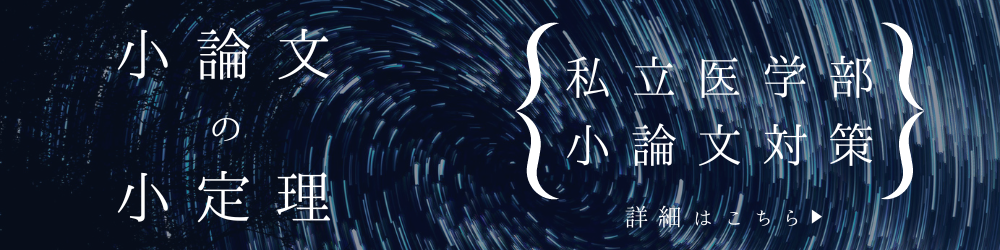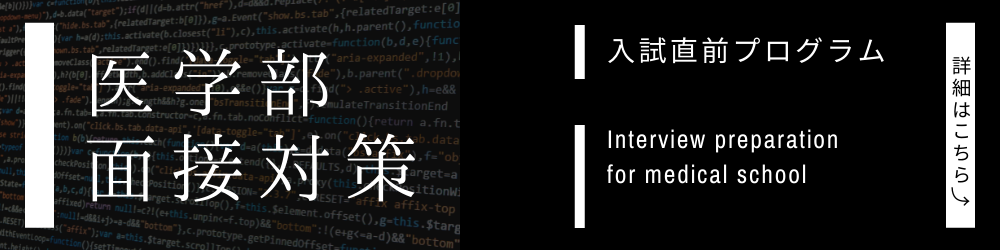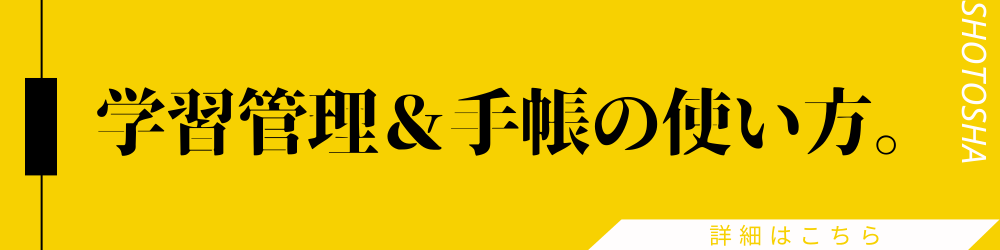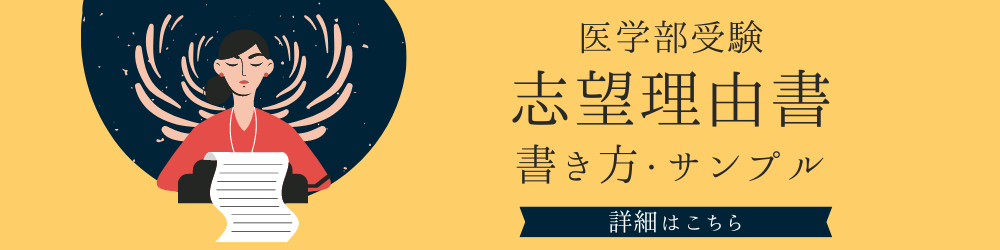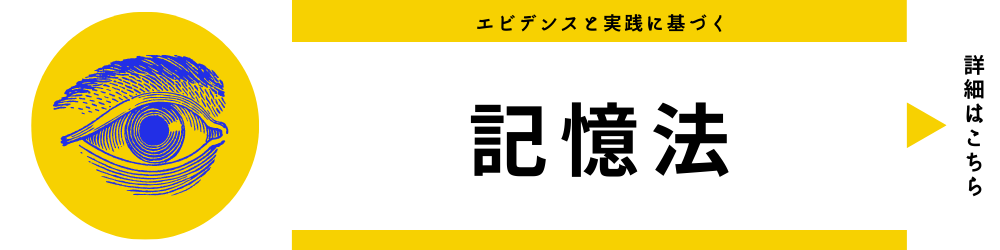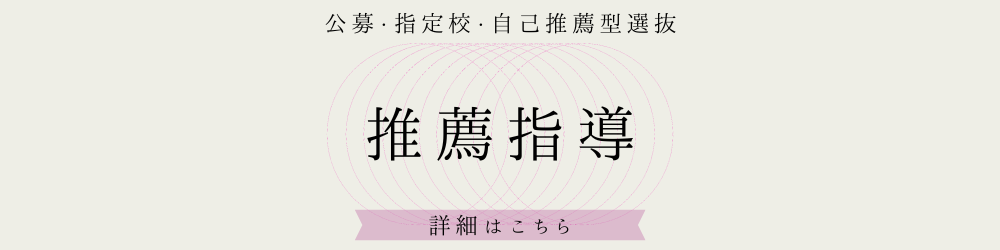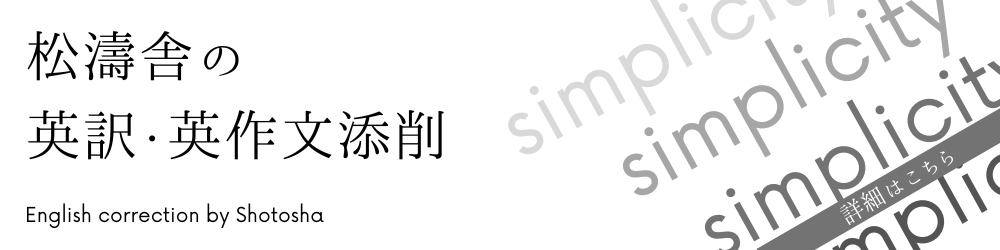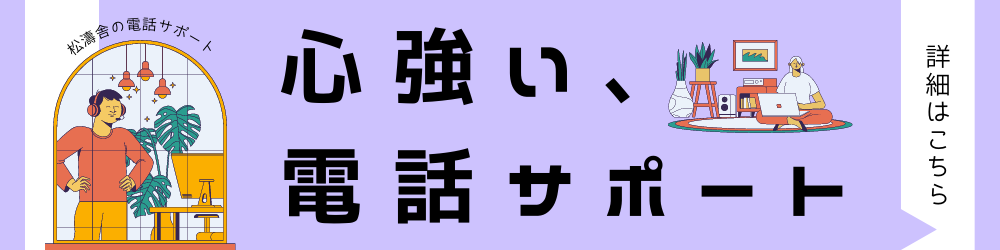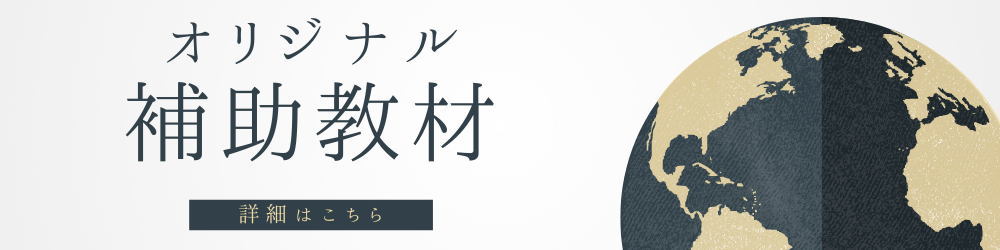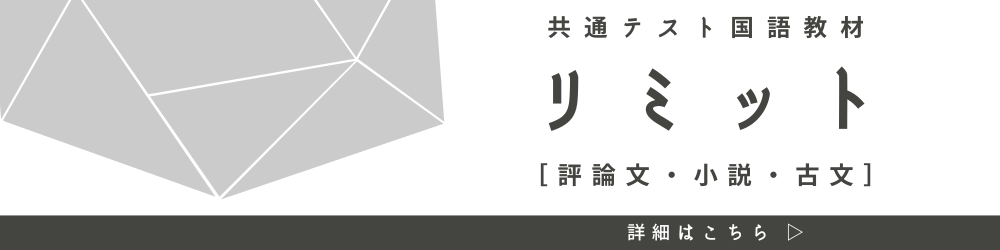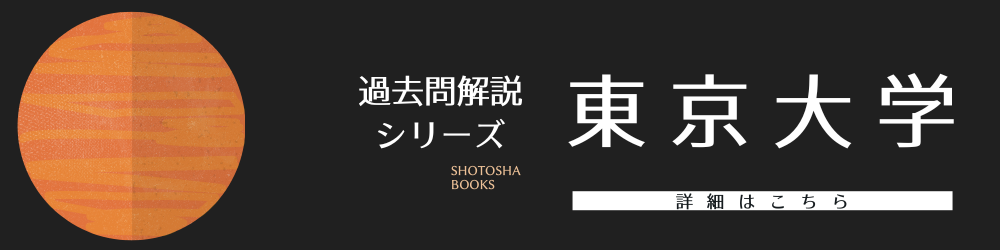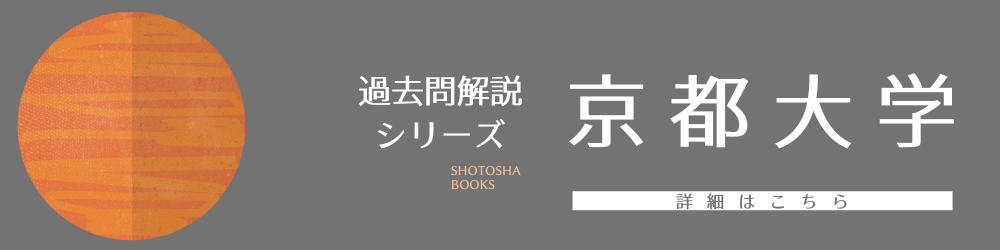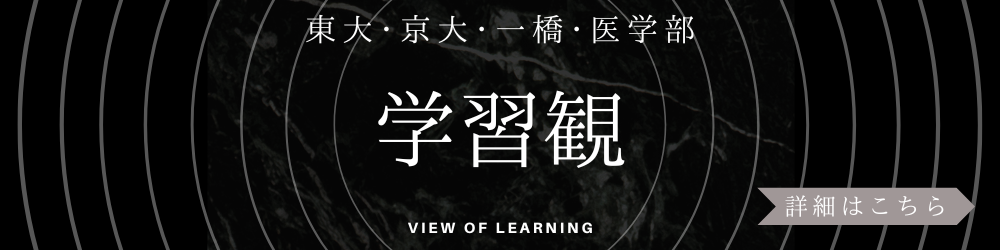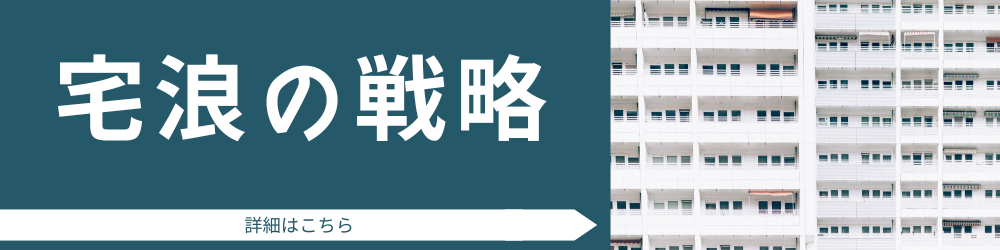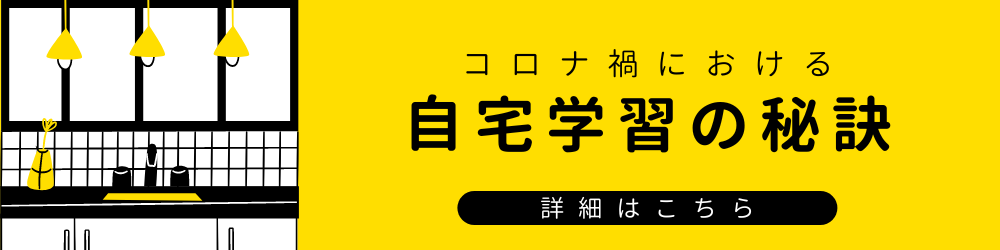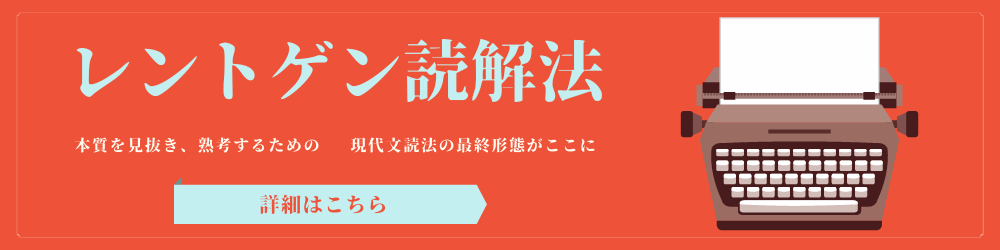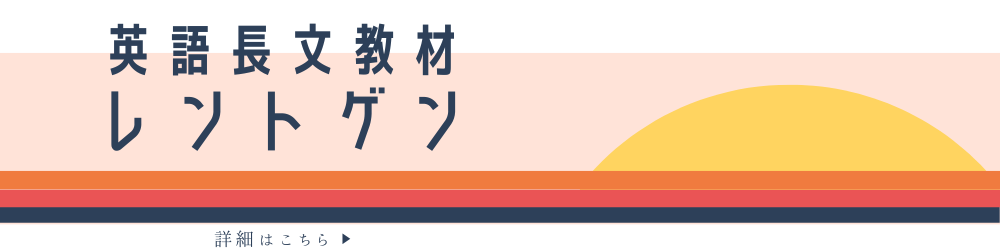▼受験観
・受験はとにかく「守り」の戦いだと考えていたので、落とせない問題をどれだけ落とさずに解けるかというところを重視して勉強した。逆に他の受験生はとれる問題を勝手に落としていくので、自分のとれる問題をきちんと取りこぼさずに解き切ることが合格につながると確信していた。
・受験を意識し始めたのは高2の秋からで、その時に高3の冬までの大まかな学習計画と理想の成績の伸び方を固めた。特にいわゆる進学校に在学していたこともあって多くの部活仲間が高2の秋に部活を辞める中、自分は陸上の全国大会に出ることを目標としていたため、高3の夏まで陸上を行うことを意識して計画を立てた。
・進学校にありがちな生徒の行動として、学校に行かずに塾で自習するというものがあるが、学校での授業があまりにも酷くない限り学校は行った方が良いと考える。これは生活リズムを整えるだけでなく、友人との会話で刺激しあったりリラックスしたりできるからである。
・ずっと勉強ばかりしていると段々気分が落ち込んできて効率が著しく下がるので、学校では友人との会話を楽しむようにしていた。特に卒業式(受験前)が行われたときにはとにかくストレスを発散するようにしていた。
・定期テストに取り組むことはその教科の基礎を固めることにつながると考えたので定期テストはできるだけ全力で取り組むようにした。
・前述の通り、基礎の問題を取り切れば合格点に届くのでとにかく基礎の問題集を完璧にすることに努めた。また周りが難しい問題集に手を出していたので焦りそうになったが、基礎のレベルからきちんと段階を踏んで完成させるようにした。
▼記憶観
・自分は単語帳をじっと見つめることが苦手なので、演習問題を回すことで記憶に定着させるようにした。問題で出てきた知らない英単語はきちんと調べ、何度も書いて覚えるようにした。
・とはいえ古文と漢文の文法や単語は問題を解けば身につくようなものではないので、同じ単語帳を何度も見返した。
▼モチベーション観
・周りが引退した中、部活を高3まで続けて受験に失敗したら引退した仲間や教師にバカにされると思い、必死になっていた。
・周りが息抜きに遊びにいくということがあったが、自分は部活のハンデを背負っていると考えて遊びには行かなかった。その代わりに、学校では休み時間の間できるだけ友人と話して楽しんだ。
・自習室のあったビルの非常階段で音楽を聴きながらたそがれることがモチベーションを保つ要因となっていた。客観的に見ると痛々しいことは分かっていたが、多少痛々しくても最後に合格したら勝ちだと思っていた。
・受験が近づいてきて、過去問があまり解けずにナーバスになることもあったが、模試でA判定をとっていたためそれを見て心を落ち着かせていた。同じように、教師に添削してもらった答案がボロボロでも「A判定の方が信憑性あるやろ」と考えて自信を取り戻していた。
・家は休む場所、学校は楽しむ場所、自習室は勉強する場所というように場所で行動を変えるようにしてモチベーションを保つようにした。
▼国語観
現代文観
・国語は自分の学部の配点においてウエイトがかなり低いので、現代文は基本学校の勉強だけで完結させていた。医学部を受けない限り現代文をする時間は理科に当てたほうが効率的だと思う。
・京大の現代文は文字制限がほとんど無いので、自分が解答の材料になると思ったところはできる限り全て書くようにしていた。
・自分は現代文が壊滅的にできなかったので解答のパターン化に努めた。具体的には、「AだがB。」、「AしたらかえってB。」「Aは〜でBは〜であり、両者ともにCという点で同じである。」といったように型を覚え、それに要素を当てはめるようにした。
・基礎的すぎるかもしれないが、句読点と語尾に注意した。一点減点されるだけで不合格になる可能性もあるので日頃から気にしておくべきである。
古文観
・古文文法は高校2年までにある程度仕上げ、高3で完璧にすれば十分だと思う。また、古文常識は最低限授業で出てきたものは覚えるべきである。
・古文単語は重要なものを完璧に仕上げ、余力があればマイナーなものも覚えるようにした。
漢文観
・京大は漢文がないのでセンター対策しか行わなかった。基本事項を完璧に仕上げ、失点を避けるようにした。
▼数学観
・その問題は何を題材としているのか、何を聞いているのかを確認しながら解くように心がけた。また、その問題で与えられた条件を全て使っているか、なぜその条件を与えられているかを考えながら解くようにした。
・数学は「守りの教科」の典型例なので多くの問題を解こうとするよりも自分の解ける問題を6問中4問選び出してそれらに時間を費やすようにした。残りの2問は部分点をもぎ取れば良くて、時間がなければ捨ててもよいと考えていた。
・京大では部分点がほとんどなく、計算ミス一つで大幅に減点されるのでとにかく計算ミスには気をつけた。
▼化学観
・理科では場数を踏むことが学力の向上と考えて、他大学の問題でも積極的に取り組むようにした。特に化学は題材にする事象や背景知識の種類に限界があるのでとにかく問題をこなし「見たことのある問題」を増やすことに努めた。
・京大では有機化学の構造決定の問題をとることが重要となる上、構造決定の問題が解くことが純粋に楽しかったため構造決定の練習にかなり時間を費やした。無機化学はほとんど出ることはないので最後に詰め込むことにした。
・実験の条件が度々変更されたり積み重なったりすると訳がわからなくなることが多いので、混乱した時には少しでも良いから図を書くことにした。
・頭のいい解き方、考え方を持っていなかったので、できるだけ解く問題数を増やして問題に慣れるようにした。実際、受験期後半になってくるとその問題で何を行なっているのかを頭の中で整理でき、早く解けるようになった。
▼物理観
・京大の物理は基礎から応用まで幅広く出題してくるのでとにかく基礎と中間レベルくらいの問題を落とさないように心がけた。そのために基礎の問題集は何度も繰り返し解き直した。
・特に公式の導出を行う問題は電磁気を中心によくあるので、公式は導出できるようにした方が良いと思う。
・最初の問題で計算ミスすると後の問題が全滅するので、最初に基礎問題にどれだけ焦らず時間をかけられるかが点数を上げるカギになると思う。
・物理、特に電磁気分野では単位に注意することが重要になる。単位を気にするだけで検算や確認ができる上、何よりもわからない問題でも当て勘で答えることができる。実際、この当て勘は体感3割くらいの確率で成功するし、定数倍のズレならお情けの部分点がもらえることもあるので重要である。
▼英語観
単語
・単語を覚えることは必須だが、知らない単語を文章から類推する力も必要。また、簡単な単語は一つ目の意味だけでなく三つ目、四つ目の意味から出題されることがあるのでそこも覚えておくと有利になると思う。
・とはいえ、記憶観のところに書いたように、自分は単語を覚えることが苦手であったので、受験期後半に問題で出てきた知らない単語を書き殴るという方法で詰め込んだ。
文法
・和訳問題をひたすらこなすことで身につけた。逆に京大では和訳問題以外に文法が必要になることは少ないのでとにかく和訳に必要な文法を重視した。
和訳・精読
・和訳ではきちんと原文の意味を考えて解くようにした。意味を取り違えるとその問題はほとんど点数が残らないと言っても過言ではないので、和訳部分以外の文章もしっかり読んでから解くと良いと思う。
・原文のニュアンスを崩さないように自然な日本語にするということに注意した。自然な日本語にしようとしすぎて原文の構文が取れていないと判断されることが度々あったからだ。
・最後に余った時間で自分の和訳を「攻めた和訳」にしていた。具体的には作った和訳について、単語帳に載っているような訳ではなく巧みな日本語にすることで最後の点数アップを狙っていた。
和文英訳・自由英作文
・自分は和文英作の勉強を怠っていたので受験期後半にかなり苦労した。その頃になってようやく基本例文を暗記するということをし始めた。
・基本例文をどれだけ暗記しているかで勝負が決まってくると思う。ここでも自分は基本例文を何度も書き連ねることでギリギリ間に合わせることができた。
・英語の勉強は言語学習なので、日本語を勉強したときに行ったように書くことが重要になると思う。ただし時間がないなら、スマホで英文を打ち込むだけでも効果はあると思う。
・どれだけ内容が良くても論点がずれていれば大幅減点、最悪0点になることもあり得るので、自由英作文は問われていることに答えるように意識することが重要であると考えていた。
長文
・とにかく文章の意味を正確に取ることを意識した。正確に取れていないと妄想で的外れな解答を作ることになるので、読み取った主張のエビデンスを文章の中にきちんと持つことを意識した。
・時間がないので和訳になっているところ以外は流し読みしていた。また説明問題ではその問われているところをもう一度読んだ上で答えるようにしていた。
・京大の英語の説明問題は文字制限がほとんど無いに等しいのでとにかく関係ありそうなところは書き連ねた。理系の、特に自分の受けた学部の英語の採点は緩いと有名であったのでこのようにした。実際、説明問題の解答に余計なことを書いたのにもかかわらず点数が高かった。
・ただし、その他の学部、特に医学部を受ける人は英語の採点が厳しいのでこんな戦術を取るべきでは無いと思う。
リスニング
・京大ではリスニングが出ないためセンター対策しかしなかった。ただ、最近京大の英語はかなり変化しているのでリスニングが出ても不思議では無いと思う。
その他出題形式
・最近の京大の出題形式は変化が激しいので他大学の問題も広く解くようにしていた。
▼地理観(センターのみ)
・息抜きとして資料集と地図帳を眺めることを習慣化した。また、過去問をやっていくうちに出題形式や問われるところが被っているところを重点的に覚えた。
▼その他
京大受験観
・京大は難関大学とされているが、医学部でもない限り、才能のない自分にも手の届く範囲にあると常に考えて努力していた。
部活観
・部活に入ることが直接受験にメリットとなることはあまりないと思う。しかし「部活で目標があるけど受験のために断念しなきゃ…」と考えている人は、きちんと前倒しで計画を進めると大丈夫なので諦めずに頑張ってほしいと思う。