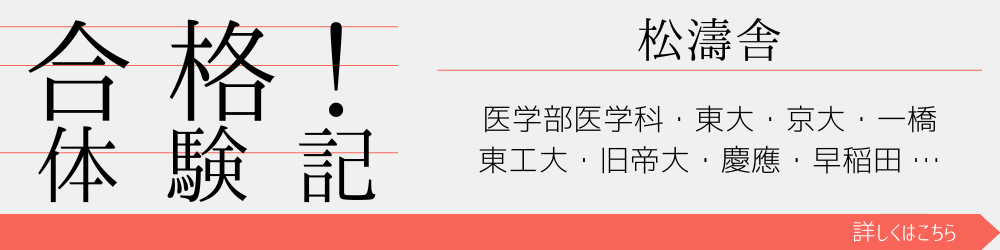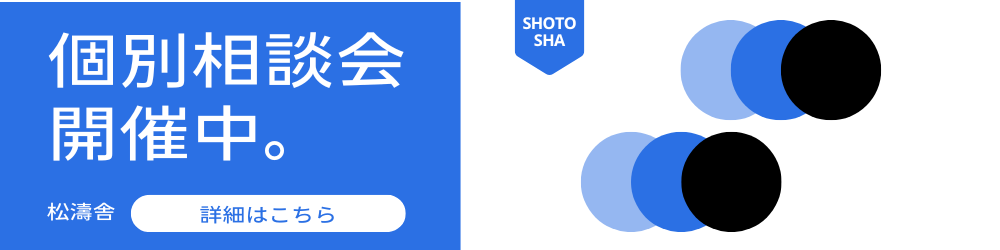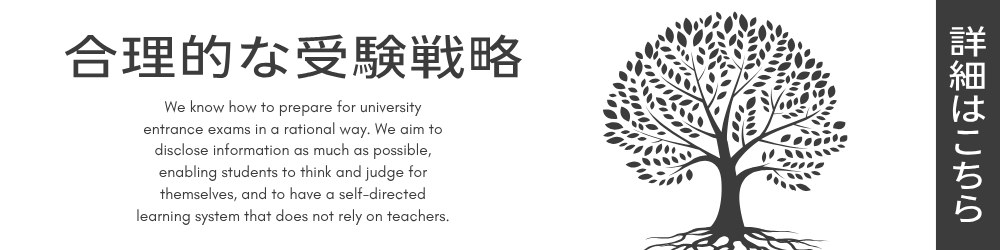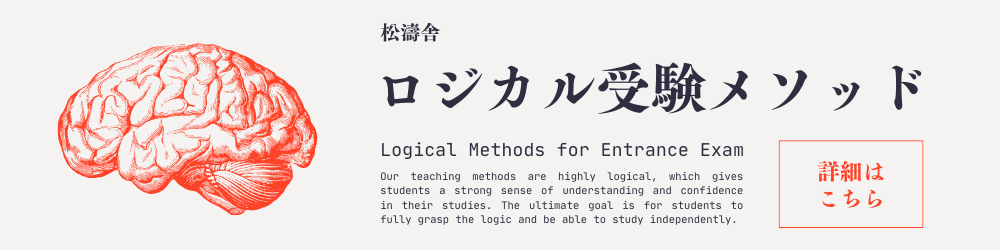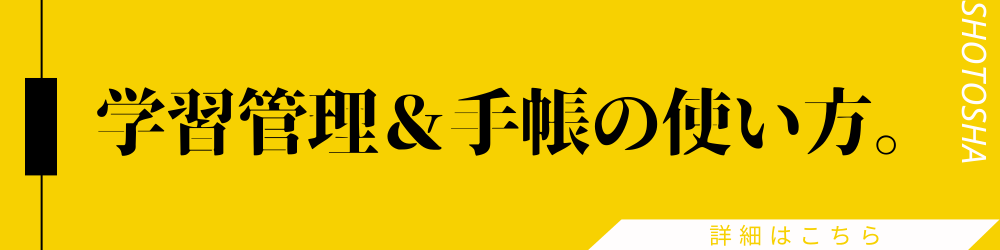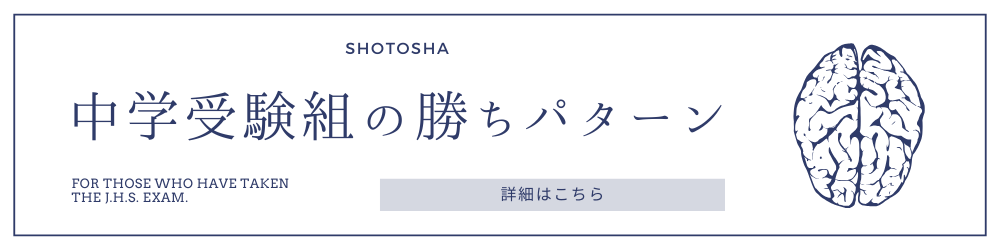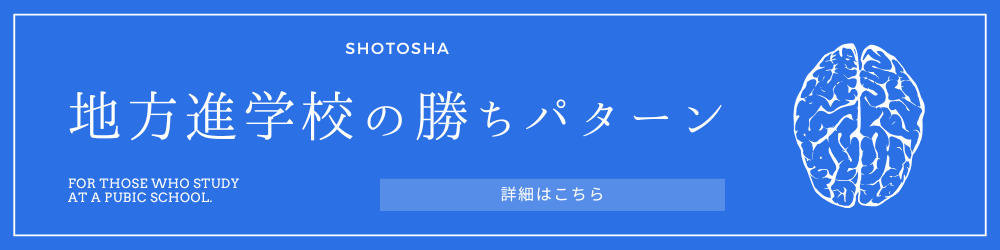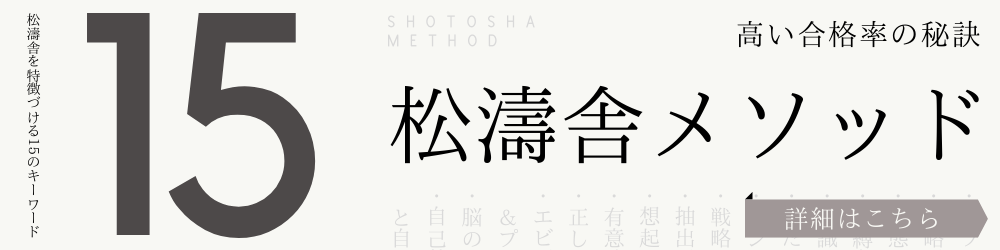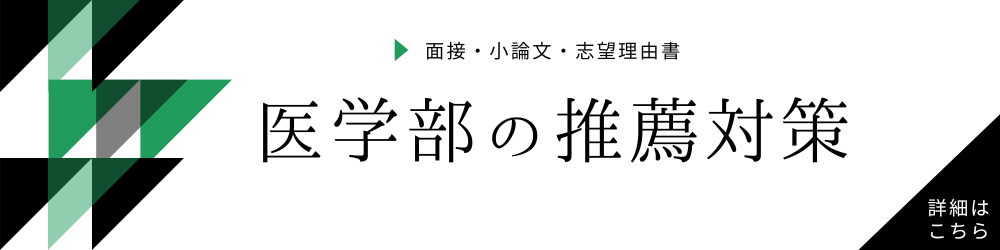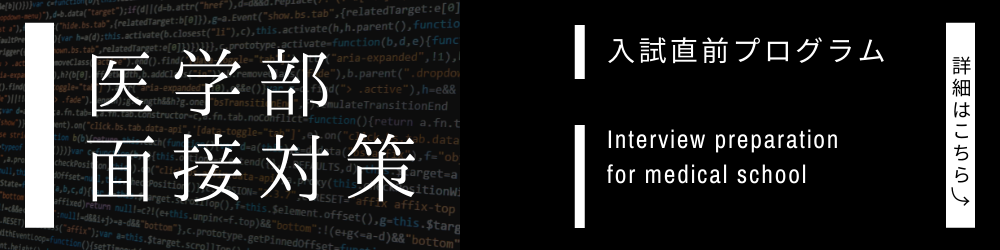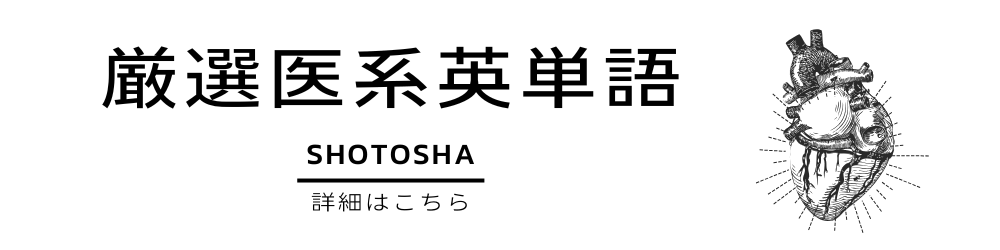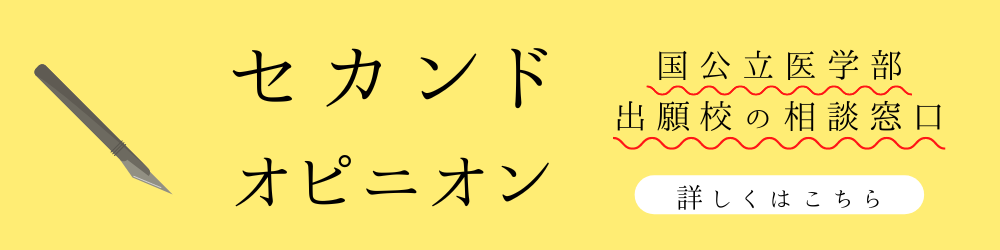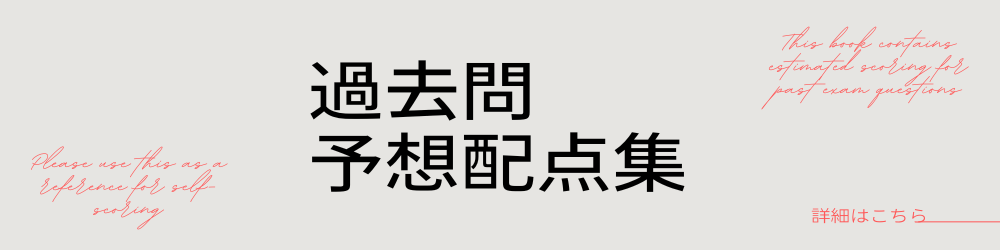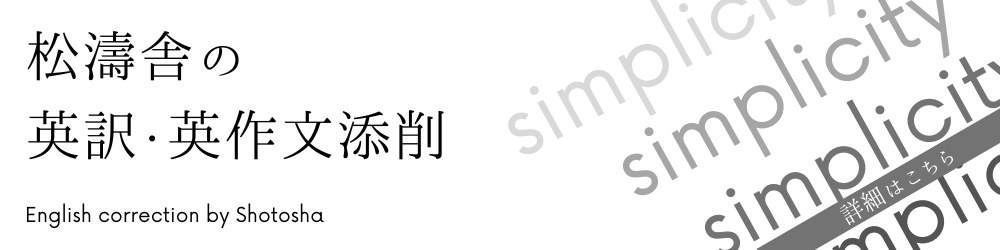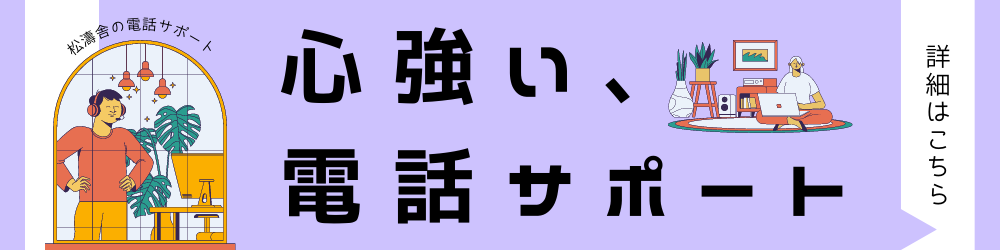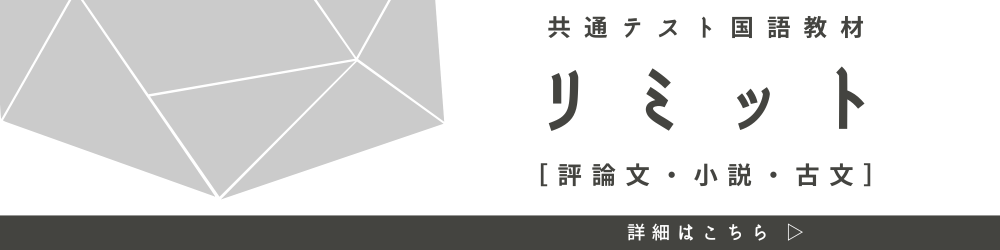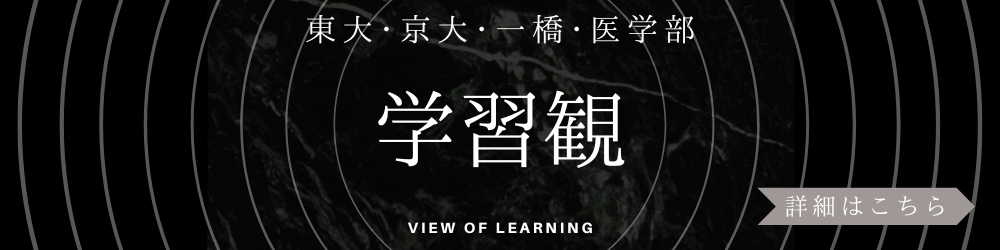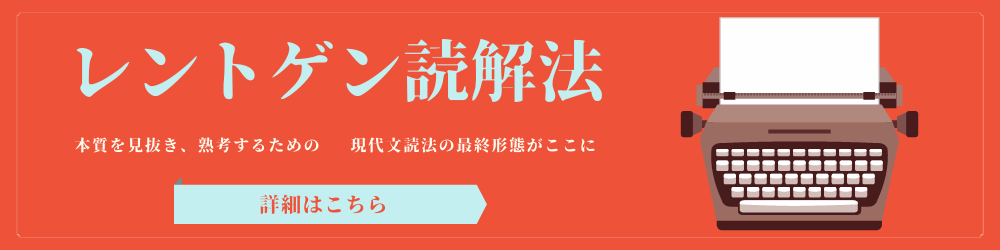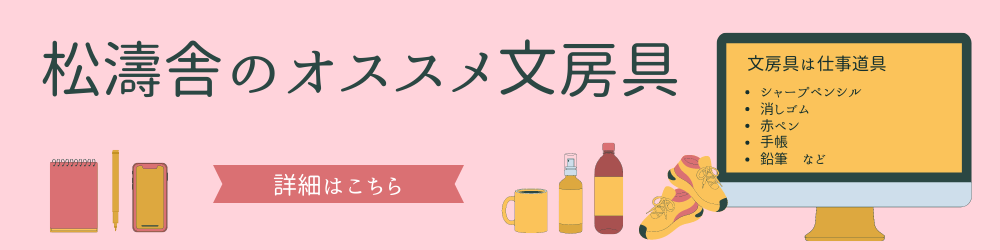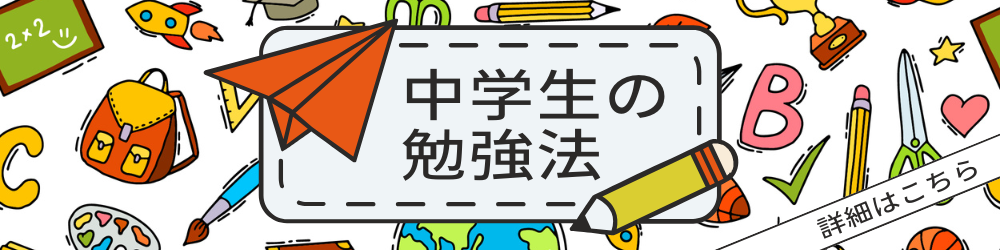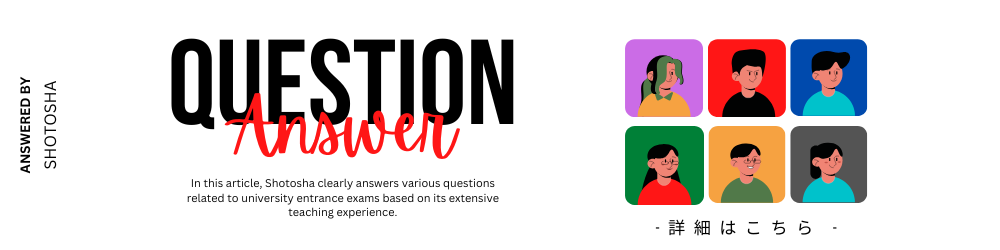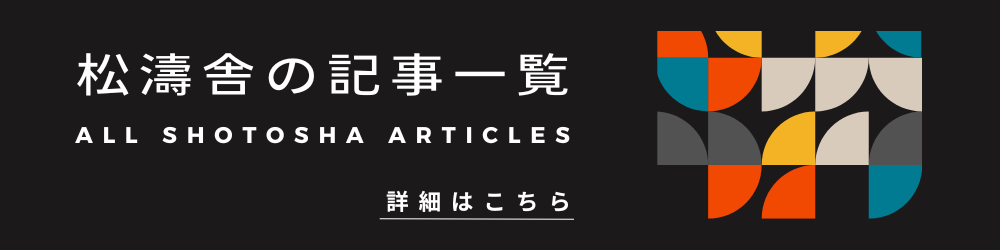▼受験観
・受験は人生の通過点に過ぎず、結果が人生の評価を決めるものではないという意識があったため、気楽に取り組むことを考えていた。あまりプレッシャーを背負いすぎるのもよくないという考えから生じた解釈でもある。
・はじめのうちに量を積んでおけば自然と容量と効率が良くなってくると考えていたので、受験期の序盤はとにかく勉強時間を多くとることを目標としていた。
・直前に身についていないことに絶望したくなかったため、他の受験生がスパートをかける前の序盤に勉強してリードを取り、逃げ切ろうと考えていた。
・もちろん最低点を取る勉強でも合格することはあるが、下を見ずに上を目指す方が良いという考えから、自分が納得できる勉強をし、余裕を持って合格しようというスタンスで受験に臨んでいた。
▼記憶観
・記憶の定着には意味づけが不可欠だと考え、どの科目でも複数の知識を結びつける暗記方法を試みた。
・特に古文漢文、日本史などの文系科目に関しては記憶こそ最上の解法だと考えていたので、滞りなく問題に取り組むためにできるだけ濃密な(様々な暗記事項が有機的に繋がっている様な)記憶を目指した。
・暗記はまとまった勉強時間にするともったいない様な感覚があったので、勉強と勉強の間のリフレッシュや移動時間の手持ち無沙汰な時間にこまめに取り組むことを意識した。
▼モチベーション観
・基本的には学内順位をあげたいというモチベーションで勉強していた。大きな目標も重要だが、こまめに目標を設定することも重要だと考えていたためである。
・どうせ人生で一度しかないことだし、全力でやってみようという意識があったので、モチベーションの維持にはこまらなかった。
・高校の友達と同じ大学に行きたいという単純な気持ちもモチベーション維持の一端を担っていたと思う。また、人が見ていないところで勉強して成績を伸ばしたいという気持ちも強かった。
▼国語観
・国語は特に理系の東大受験においては他の受験生が万全の状態ではない部分と認識していたので、ある意味他と差をつけるボーナスステージの様なものだととらえていた。そのため点数の配分としては理系科目に比べて小さめだったが力を入れて勉強した。
現代文
・現代文は定まった解法が見えにくい科目ではあるが、ある程度文章の読み方を覚え、注目すべきところ(筆者の意見など)を捉えれば回答しやすいものだと捉えていたので、読解問題でも常に帰納できる考え方がないかを考えて勉強していた。
・センター試験は前半の知識問題はもちろん、後半の配点が大きい選択問題を落とさないことを意識した。明らかに2-3択にまでは減らせることが多いので、そこから選択肢を二分するなどして、文中の該当箇所を精読した。
・二次に関しては記述欄の長さから要求されているポイントの数を考え、その中で何を盛り込むかを考えた。必要な要素が入っていることが重要だと考え、なるべく記述量は増やした。
・センターも二次も、設問を読んだときすぐに該当箇所に飛べる様に記憶に残すため、文中に線を多く引いた。また、重要な単語をメモしたりして自分の頭の中に留める様にした。
古文
・細かい助詞助動詞、活用がわかれば内容は自然とわかるので、とにかく要素主義に拘った。助動詞や文法法則をとにかく反復して、同様に古文単語も毎日見る様にして自然と意味が出てくる様に勉強した。
・国語観全体で言った様に、理系にとって古文で他より差をつけられればラッキーと思っていたので、隙間時間や理系科目同士の勉強時間の間に暗記などをしていた。
漢文
・古文と同様、要素主義にこだわったため、漢字と読み方などを覚えた。
・二次に関して古文漢文共通して言えることだが、難化している可能性もあることや、他もそこまで力を入れていないこと、国語でテンションを下げても意味がないことなどの理由で、模試や受験であまりうまくいかなかったときでも気にしない様にしていた。
▼数学観
・センターにおいては満点で当たり前の科目と捉えていたので、とにかく練習量を積んで余裕を持って解ける様にしていた。
・二次においては物化と並んで最重要科目だったので、一番力を入れて勉強した。そのため過去問も間違えた問題を中心に2周、3周勉強した。
・部分点をとることにも大きな価値があると考えていたので、とにかく丁寧な記述を心がけた。
・東大二次に関しては完璧に取らなくてはいけない問題以外は部分点を意識していたため、完全回答できない問題があっても特に気にしないという意識でいた。
▼化学観
・物理と比べて知識がものをいう科目だと捉えていたので、演習の他に隙間時間で暗記などの勉強を欠かさなかった。
・化学の場合、計算問題も内容が似通ったものが多かったので、パターンとして覚えて反復練習をし、すぐに対応できる様に心がけて勉強した。
▼物理観
・知識というより、本質的な部分を理解していることが重要だという感覚があったので、簡単な問題でもしっかり記述して、なんの式を使っているのか、符号はどうなっているのかを意識して勉強した。
▼英語観
・英語は日常生活でも役立ち、よく目にするものであるため、受験勉強としてはもちろん、教養として捉えることで、できるだけ知識を吸収しようという意識で取り組んでいた。
単語
・英語は単語力がものをいうので英単語帳を力を入れて勉強し、文章で邂逅した難しい単語もメモしておいて覚えた。
文法
・基本的な部分を押さえていることが重要だと認識していたので、同じ文法問題集を集中して勉強した。
和訳
・英文中の和訳すべき要素を取りこぼさないため、文章を節で区切ってひとつずつ意識して和訳する勉強を心がけた。
和文英訳・自由英作文
・特に二次で問われる部分で、試験時間に対して量が多いため、問題をざっとみて他の問題に取り組んでいる間になんとなくの構想を練る様にしていた。そのため回答にかける時間を短くできる様に勉強した。
・論理の飛躍、やや強引な展開になると評価されにくいので、英語の表現はもちろん、論理的に穴がないかを常に意識して勉強した。
長文
・興味を持って取り組むことが内容の理解につながるという感覚があったので、設問を解くことはもちろん、文章を滞りなく読める様に、英語の文章を沢山読んで英語長文に慣れる勉強をした。
リスニング
・こちらも音声に慣れるということが重要だと認識していたので、移動時間にこまめに聞いたり、英語のプレゼン動画をみたりして、とにかく量を聞くことで対策としていた。
▼模試観
・自分が何をわかっていないのかを把握する存在として認識していたので、自分の出来は気にしても周りとの比較や偏差値は特に気にしない様に意識していた。
・とはいえモチベーションの上昇には効果的で、良かった得点などを心に留めておくと自信につながると感じた。
▼塾観/予備校観
・通っていなかったので、よくわかりません。
▼参考書観/問題集観
・知識のムラやもれがないことが重要だと思っていたので、何冊も手を出すというよりは数冊を完璧にこなすということを意識していた。
・参考書は自分の知識のある種最大値であって非常に重要なものだと考えていたため、教師におすすめを聞いたり、友人と情報交換をし合ってなるべく良いものを使おうとしたりなどのことを心がけていた。
▼友人観
・成績面での点でいえばライバルであり、かつ同じ高校で勉強し他の受験生とあい対する仲間でもある存在だと認識していたので、モチベーションの源泉にしたり、身近な相談相手になったりと、受験にとってとても心強い存在として付き合っていた。
▼学校観
・予備校に通っていなかったので、学校が学びの中心地であり同時に友達と関われるリフレッシュの場であるとも認識していた。
▼部活観
・引退するまではリフレッシュの場と認識していた。その後は部活に割いていた時間を勉強に回せると考え、ブースターの様な存在と認識して付き合っていた。
「【学習観】KIさん(東大理系)」に関するQ&A
- 受験勉強におけるモチベーションをどう維持すれば良いですか?
- モチベーションを維持するためには、小さな目標を設定し、達成感を得ることが重要です。また、友人と同じ大学を目指す意識や、受験を楽しむ気持ちもモチベーションの源泉となります。
- 効率的な記憶法は何ですか?
- 効率的な記憶法は、知識を関連付けて意味づけすることです。特に文系科目では、暗記項目を有機的に結びつけることで、記憶の定着を図ることができます。
- 数学の勉強法にはどのようなものがありますか?
- 数学では、まず基礎を固めるために問題を多く解くことが重要です。過去問を繰り返し解くことで、問題のパターンを把握し、部分点を意識した丁寧な解答を心がけましょう。
- 英語の長文読解を効果的に行うには?
- 英語の長文読解では、興味を持って文章を読むことが大切です。また、設問を解く際には、文章をスムーズに読み進めるために、日常的に英語に触れることが効果的です。
- 古文の勉強法にはどのようなアプローチがありますか?
- 古文の勉強では、助動詞や文法法則を反復して覚えることが重要です。要素主義に基づき、細かい文法を理解することで、内容を自然に把握できるようになります。
- 模試の活用法はどのようにすれば良いですか?
- 模試は自分の理解度を把握するための重要なツールです。周りとの比較を避け、自分の弱点を見つけることに集中し、次の学習に活かすことが大切です。
- 受験勉強における参考書の選び方は?
- 参考書は数冊を完璧にこなすことを目指し、自分の知識の最大値を引き出すものを選ぶことが重要です。教師や友人からの推薦を参考にし、質の高いものを選びましょう。
- 受験生にとって友人の存在はどのような意味がありますか?
- 友人は受験生にとってライバルであり、同時に支え合う存在です。成績向上のモチベーションを高めたり、悩みを相談したりすることで、精神的な支えとなります。
- 受験勉強における時間管理のコツは?
- 時間管理には、勉強と休憩のバランスを取ることが重要です。集中力を維持するために、短時間での勉強を繰り返し、隙間時間を有効活用することを心がけましょう。
- 受験勉強の心構えはどのように持つべきですか?
- 受験は人生の通過点であると認識し、プレッシャーを軽減することが大切です。自分が納得できる勉強を行い、十分な準備をしているという自信を持つことで、心の余裕を保ちましょう。