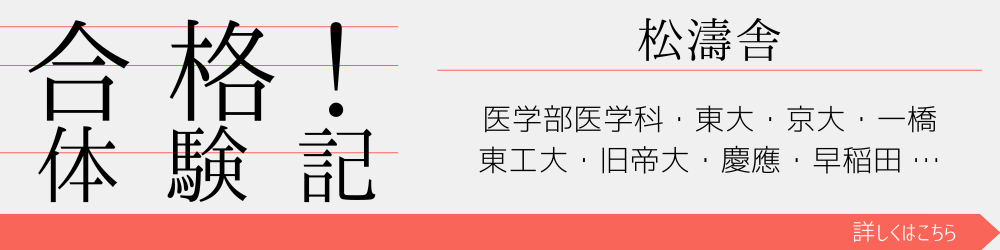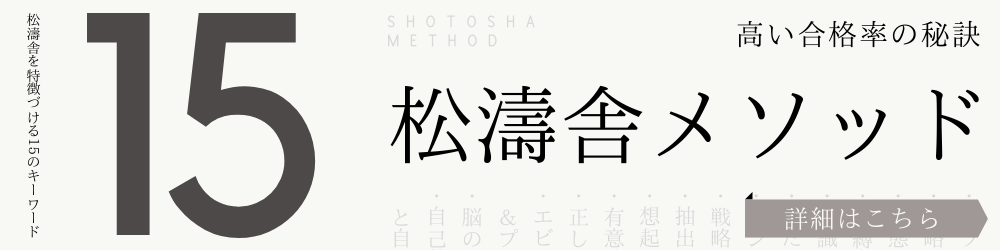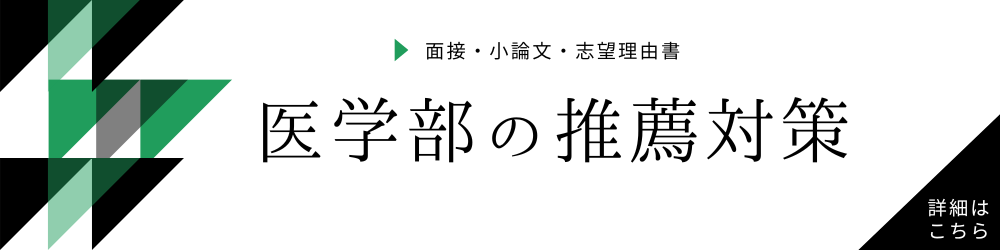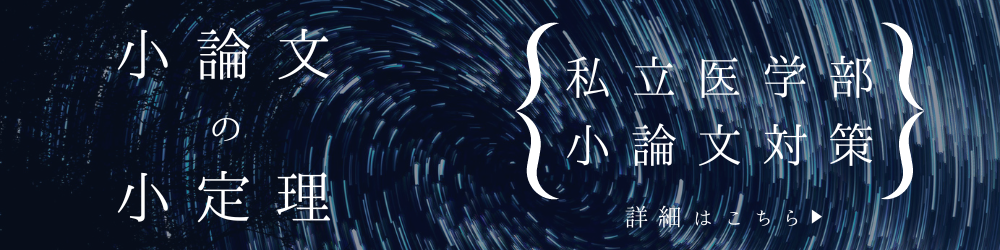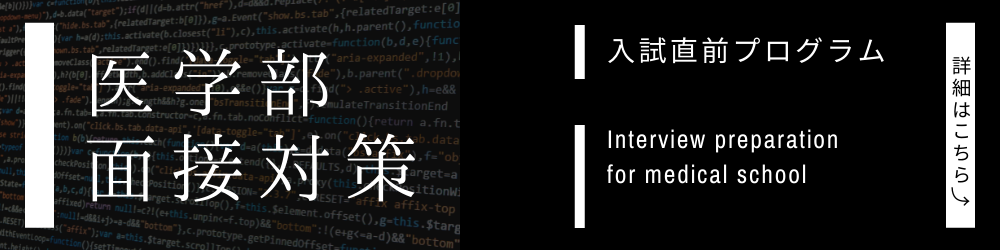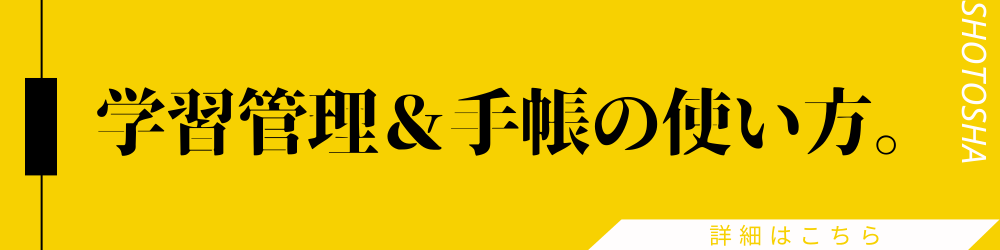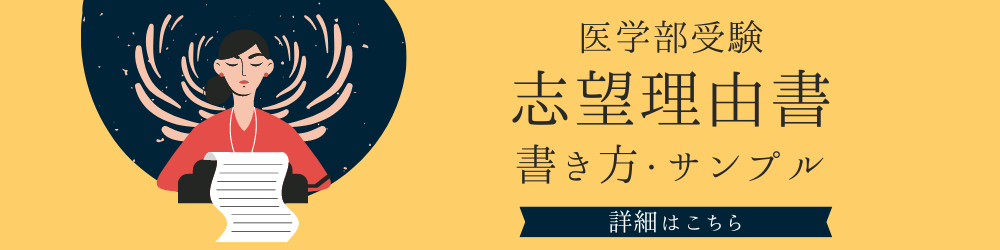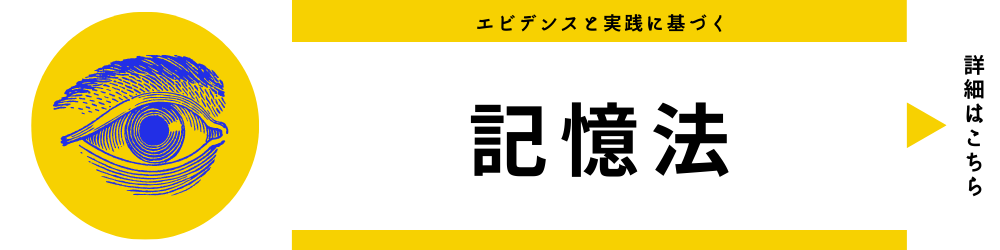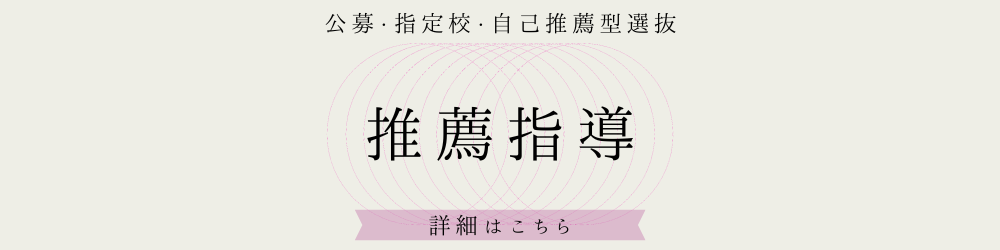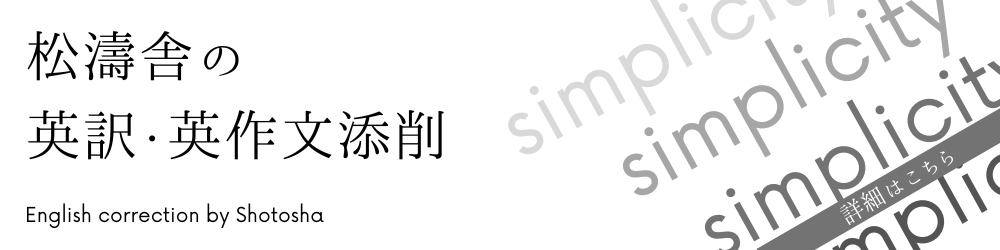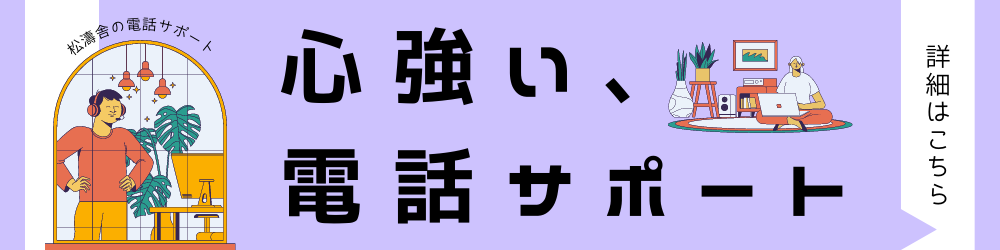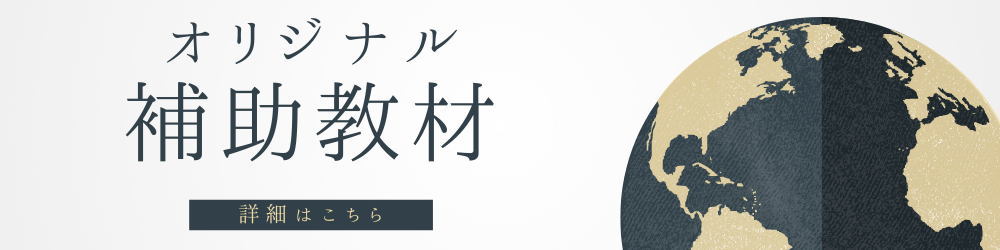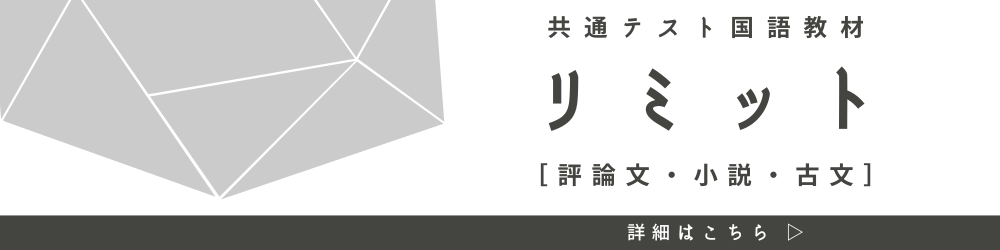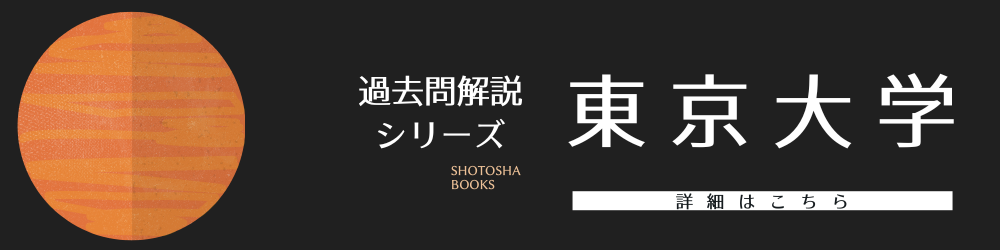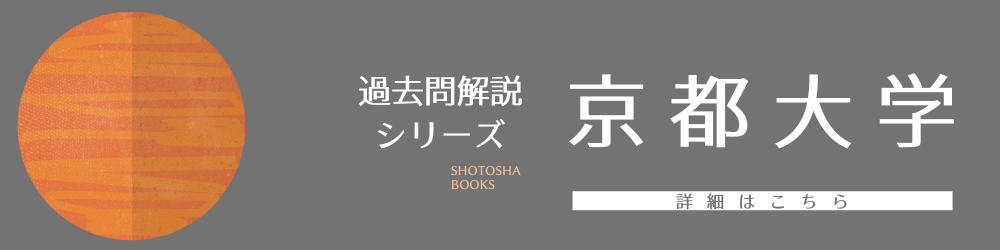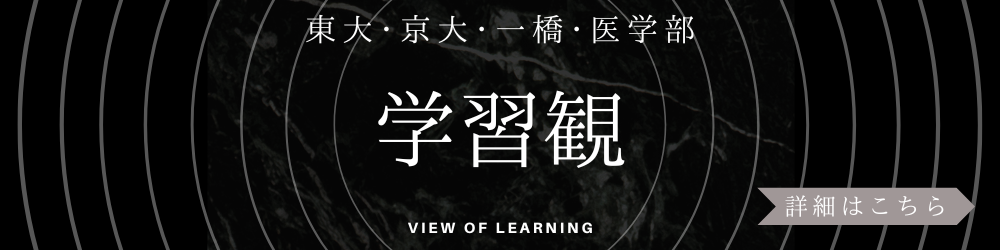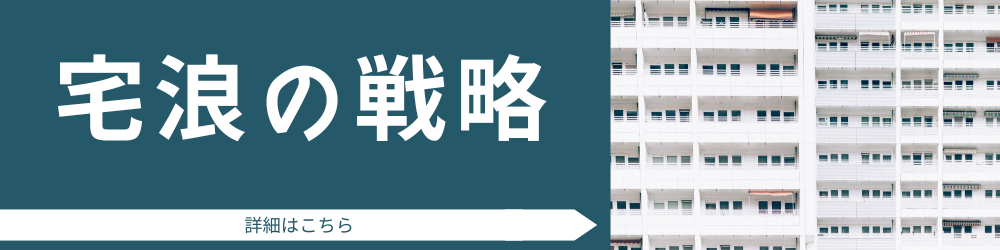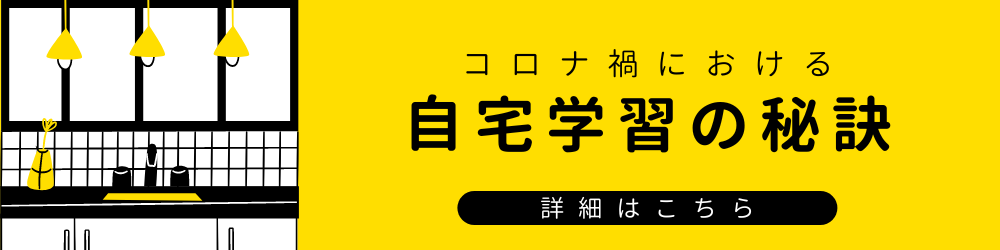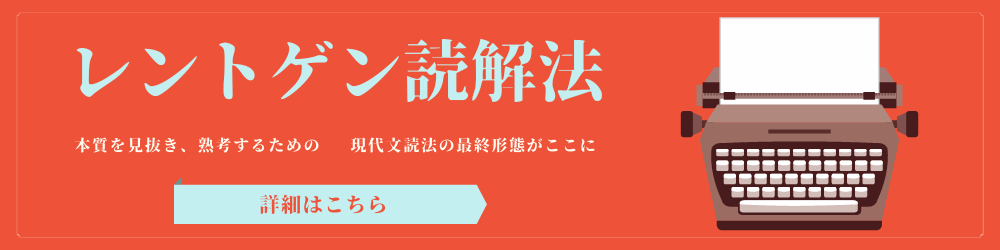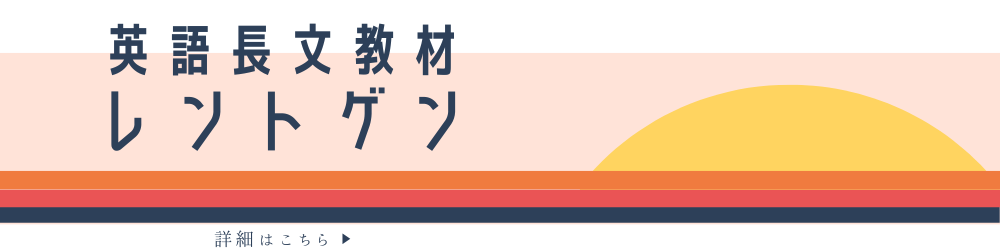▼受験観
なんとかなる精神で勉強していた。勉強しなくても大丈夫だろう、ということではない。周りに勉強しなくても成績がいい天才型の人がいたり、模試の成績が悪かったりして、ネガティブになりそうになった時に頑張ればなんとかなる、勉強するしかないと思って、勉強していた。
学校の先生、塾の先生は自分よりずっと経験があるのでアドバイスされたことはとりあえずやってみる。でも自分に合う、合わないは自分が一番わかるので、合わないと思ったらすぐにやめていた。
疲れがたまると効率が落ちたのでしっかり休むようにしていた。私は睡眠時間よりお風呂を大事にしていて、お風呂には勉強のことを一切持ち込まないでスマホで音楽を聴いたり、動画を見たりしていた。睡眠時間は多少短くても大丈夫だった。
勉強が楽しくなくなるので無理は絶対にしないようにした。早めに弁当を食べてお昼に勉強をしている人もいたが、休み時間はゆっくりご飯を食べて、友達と話したり、世界史の問題の出し合いなどをしていた。
成績が伸びない教科や苦手な分野はそれができない理由を必ず自分で考えた。私が現代文が伸び悩んだ理由は読めないからではなく、日本語のボキャブラリーが少なくて伝えられなかったためであったが、このように一般的に言われている理由と違うことがよくあったので、一般的な傾向を信じ切らないようにした。
▼記憶観
暗記は苦手で他の人より要領が悪く、みんなと一緒な方法や時間では間に合わなかった。苦手なものは苦手なので他の人より早めに始めて時間をかけて暗記したり、方法をいろいろ試してみたり、工夫して補うしかなかった。
インプットばかりではなくアウトプットも重視するようになって多少は効率がよくなった。まとめている、眺めているだけよりはたくさん問題を解いて、自分が間違えた問題を確認し、苦手な分野や覚えてない項目をしっかり見つけてそこを重点的に勉強するようにした。
文章を読んで覚えるのが一番覚えづらかったので、地図や年表、単語帳の挿絵などと一緒に覚えて、思い出すきっかけが多くなるようにした。
▼モチベーション観
テスト勉強などはやる気が出なかったが、受験勉強は自分が行きたい大学に行くためにやっているので、やる気がでないということはあまりなかった。
やる気が出ないときはどうしようもないので寝た。
たまに友達と大学で学びたいこととや、大学生活のことを話して、「じゃあ今は勉強しなきゃね」とモチベーションをあげていた。
▼数学観
2年の2学期くらいまで本当に数学が壊滅的だったのでFocus Goldを2,3周して基本的な問題の解き方とそれをどのようなときに使うのかを覚えた。これをやるだけでかなり成績が伸びたので基本の大切さを身に染みて感じた。
基本がとにかく大事で、難しい問題は基本の組み合わせだと思っていたので難しい問題は学校の授業や補修でやる過去問以外はほとんどやらなかった。でも、基本をしっかり勉強していればそれらの難しい問題もどんどん解けるようになっていった。
▼英語観
単語
3年の1学期までに大体シス単を覚えた。その後はシス単を最大限に活用しようと思い、長文を読んでわからなかった単語などはまずシス単で調べて抜けている単語に印をつけていった。
シス単が終わった後はリンガメタリカを使って自分の志望校の入試によく出る分野の単語を勉強した。単語の羅列でなく予備知識の説明もあったので長文を読むときに役に立ったし、関連付けて覚えやすかった。
文法
3年になるまでにNextStageが終わっていたのでセンター模試の過去問の第1~3問を解いて、自分が忘れている問題を確認して、その部分だけを確認していった。文法に時間はかけたくなかった。
和訳・精読
過去問を解いて慣れていった。自然な日本語にできるように練習を頑張った。自分で解いてみて、添削してもらい、そのあと模範解答も併せて見ながら書き直しをして、自然な日本語に近づけていった。丸写しではなく表現のヒントを見つけるために模範解答を見ていた(日本語のボキャブラリーが増えて現代文の勉強にもなったので一石二鳥だった)
和文英訳・自由英作文
和訳と同じように過去問を添削してもらって、模範解答を見ながら書き直しをしていた。シス単のレベルを超えるような難しい単語は使わずに、いいなと思った表現を真似した。英作文の問題集についていた例文集を書き写してそこからも表現を学んだ。いろんな表現を使って主語がずっと同じにならないように、単調にならないように気を付けていた。
リスニング
受験期は毎朝初めに電車のなかでセンターレベルの英語を聞いていた。リスニングはちょっとずつコツコツやるしかないと思っていた。
長文
長文は慣れるしかないと思っていた。1年生のころから自分がぎりぎり理解しきれなくて少し難しいと感じるレベルの問題を解いていたら、少しずつ難しい問題が解けるようになっていた。
全般・その他
受験期でも英会話に通っていた。楽しく勉強するのが一番身についた。先生の話を聞きたいというのがリスニングの練習になったし、どうにかして伝えたいという思いから、表現を工夫するのが英作文の練習につながった。
文法などの決まりも大切だが、こういうことを言いたいんだろうな、これだとなんか違和感あるなというような感覚も大事にしていた。
▼国語観
現代文
私の場合は言いたいことはわかるのにそれをうまく日本語で表現できないということがよくあったので、毎朝新聞のコラムを書き写して日本語の表現を増やせるように努力していた。
古文
教科書が終わるまでは授業の予習をしっかりやっていた。自分で訳してしっかり紙に書いてみて、わからない単語は古文単語で調べて単語帳に印をつけておいた。授業がなくなってからは毎日一問古文の問題を解くようにしていた。英語の長文と同じですぐに解き方を忘れてしまうので、少しずつ毎日続けるのが大切だと思っていた。
漢文
再読文字や最低限の構文を覚える。あとはそんなに難しい問題は出ないのでなんとかなる。
▼世界史観
単語で覚えるのではなく、流れで覚えるのが本当に大切。単語で覚えていると、使っている単語帳や問題集と違う聞かれ方をしたときに歯が立たない。
資料集をたくさん使う。特に地図はよく使った。重要な都市の場所や、都市同士の位置関係を覚えておけば、地図問題は少なくても問題文の中の場所に関する記述がヒントになることは多い。
眺めたり、まとめたりしているだけでは覚えられない。過去問や問題集でアウトプットして、自分が間違えたところを確認していくことでやっと覚えられた。
▼地理観
気候帯などの基本的なことを覚えれば、細かいことはあまり覚えなくてもよいと思う(センターのみ)。センター型の問題を解いて練習して、慣れていけばセンターレベルの問題はできるようになる。細かいことを詰め込もうとするより、自分の弱点を見つけてそこをしっかり復習するほうが効率が良いと思う。
▼その他、自分の「○○観」
京大受験観
二次試験はどの教科も時間はしっかりある。簡単な問題を早く解くよりは、難しい問題をゆっくりでいいから考えられる力が大切になると思う。他の大学の問題や模試は時間がギリギリなものが多いので間に合わなくてもあまり気にしないようにしていた。また、センター試験とは逆の傾向なので、12月でもセンターの勉強に力を入れすぎないようにしていた。
センター試験の点数が低くても気にしない。センターの配点が低い難関大学だからこそ、センター試験の点数が低くても二次で何とでもなる。悩んでる暇があったら二次の勉強をして、ぎりぎりまで諦めずしっかり対策をするのが大切。