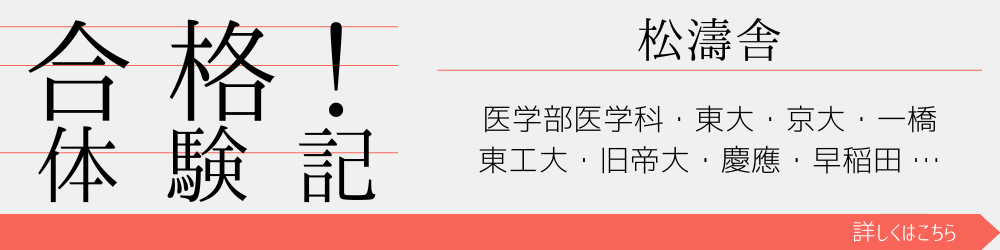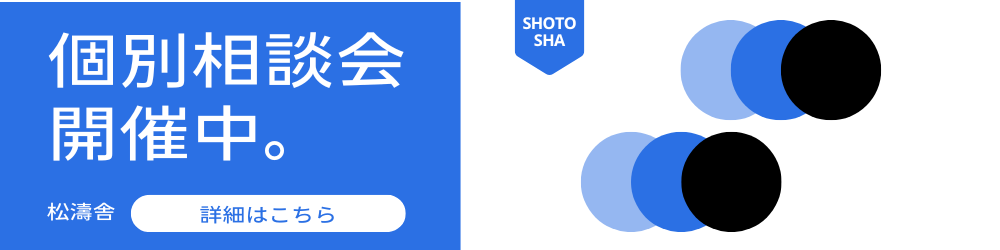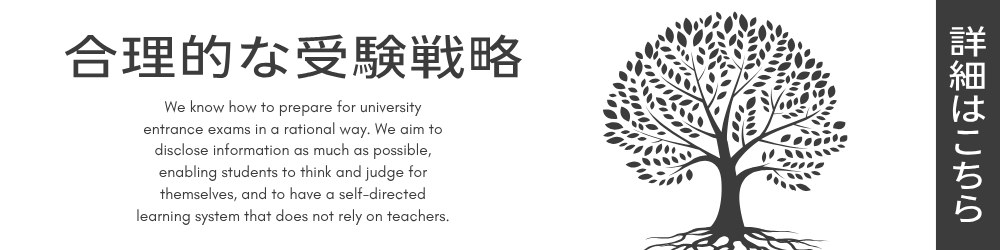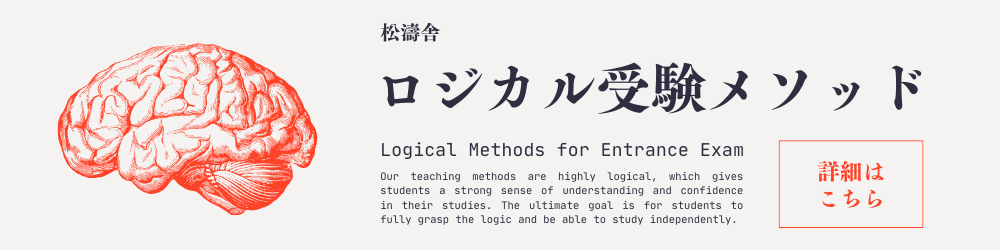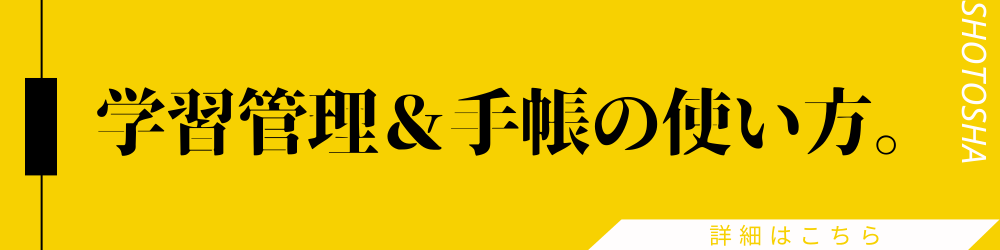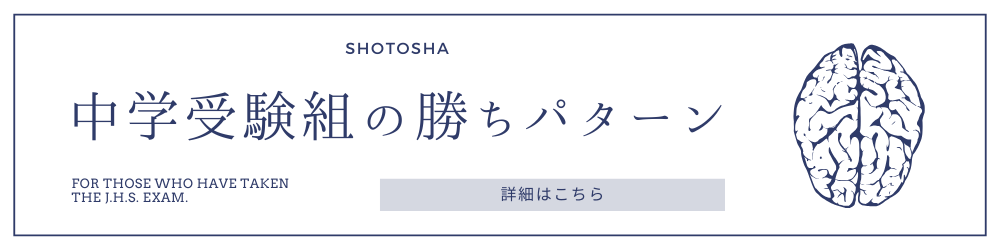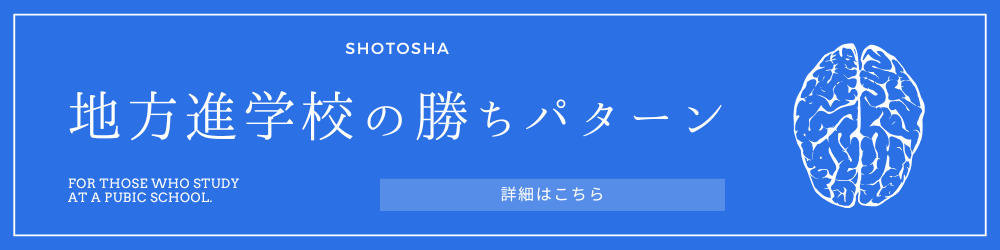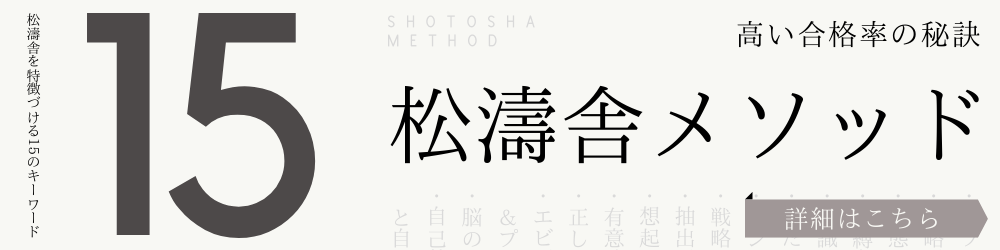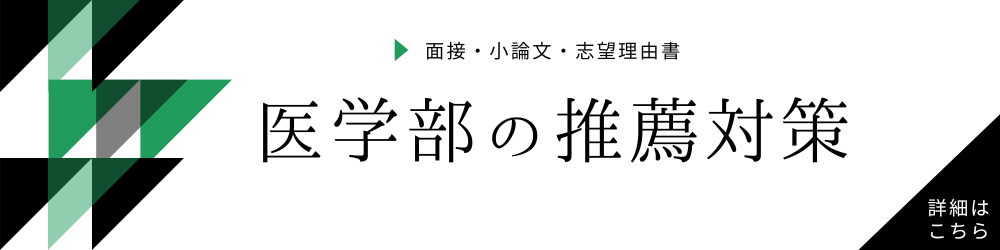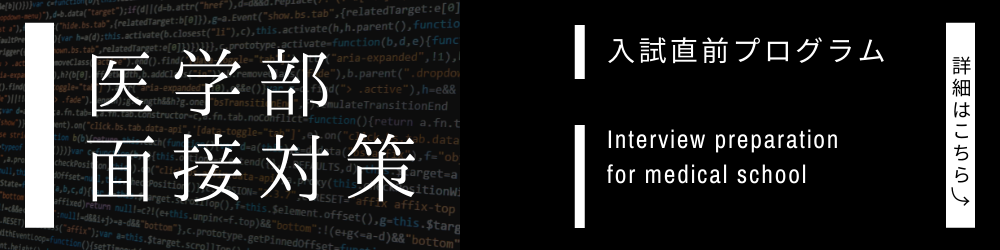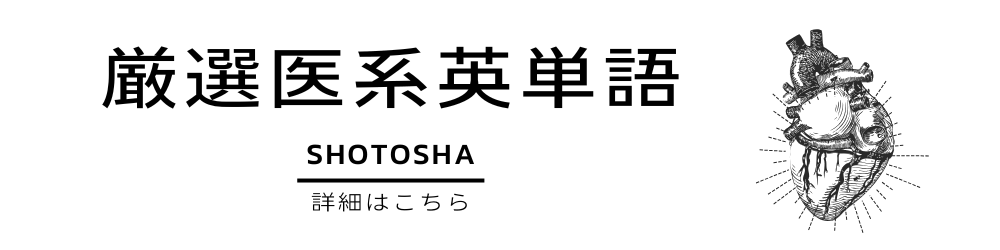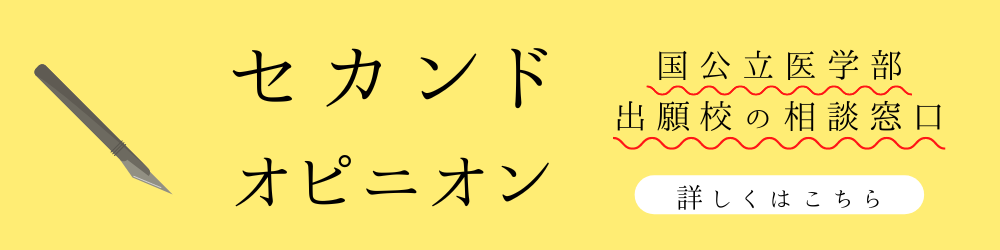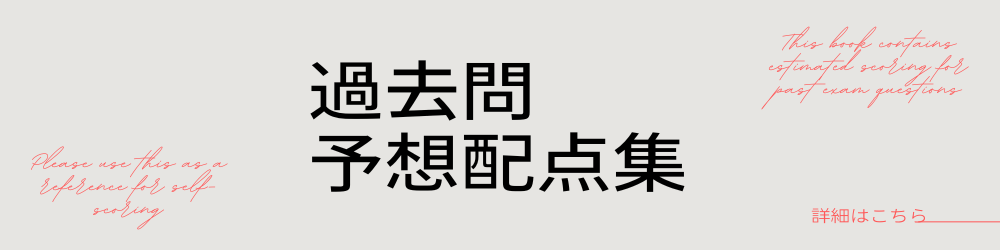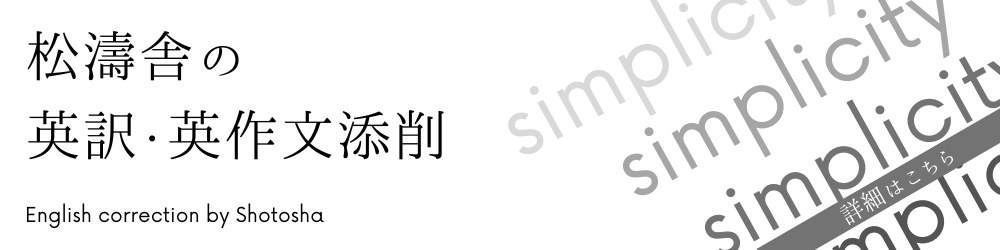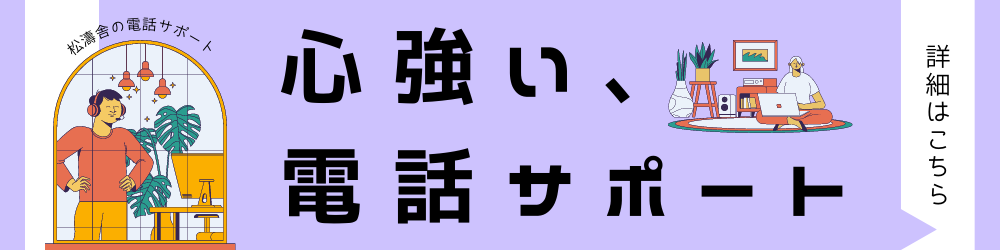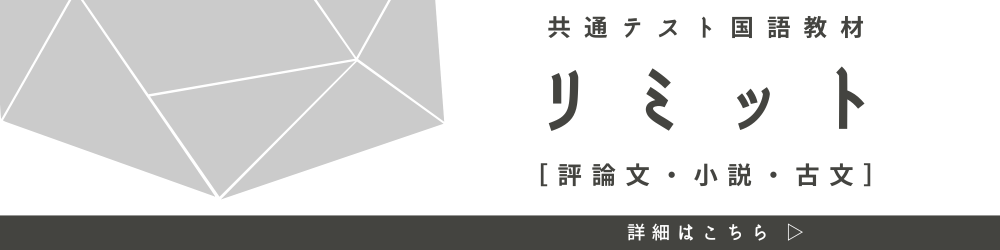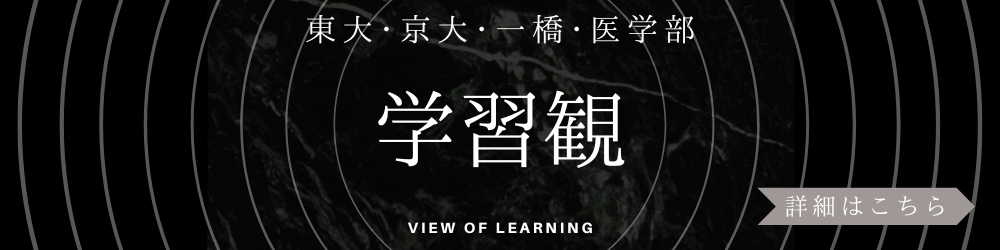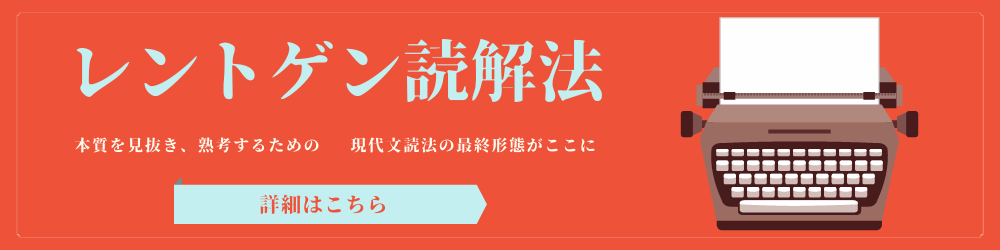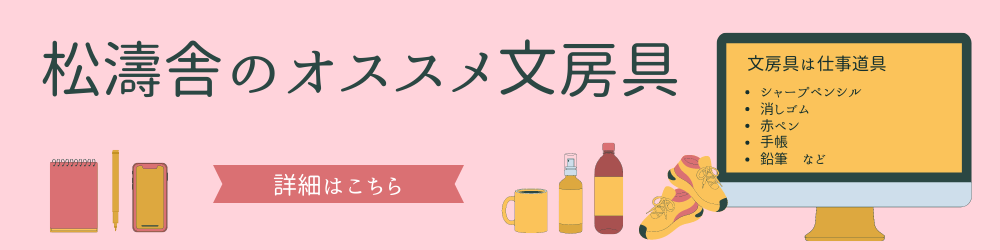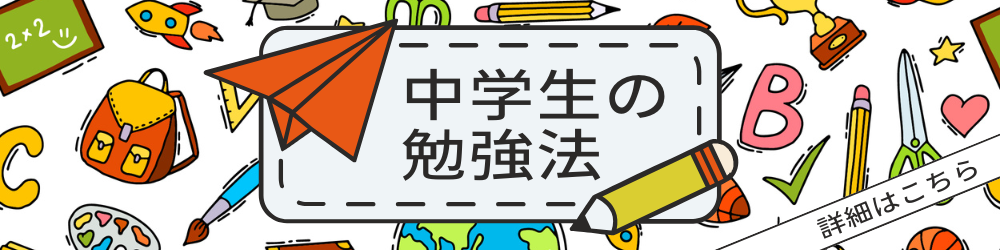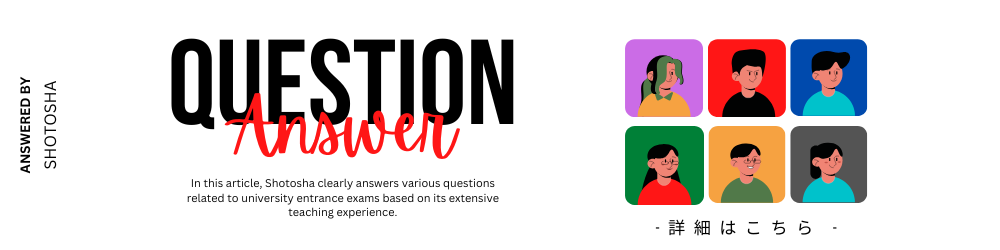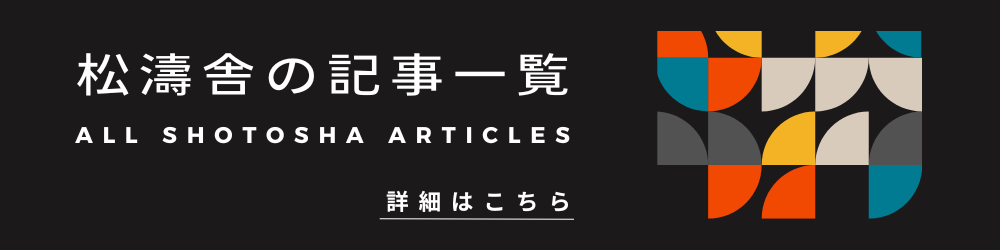▼受験観
・現役で難関大学合格を目指していたため、浪人生が多く受験する中で圧倒的な差をつけて合格するのは難しいと考え、戦略として合格最低点ギリギリで滑り込む意識で勉強していた。
・一方、得意な英語と日本史では最高点を獲得する意識で勉強した。得意教科で妥協すると合格が遠のくと考えたからだ。
・自分はもともと負けず嫌いなため、その性格も相まって冠模試やセンター・二次試験ではだれにも負けたくないという気持ちで挑むことができた。
▼記憶観
・記憶は頑張って何かを覚えようとして定着するものではなく、知らない間に定着しているものという認識があった。
・イメージとしては、壁を塗る際に、一度に厚く塗るのではなく、薄く塗るのを何層も繰り返すイメージ。
・そのため、例えば2,000単語を一ヶ月で覚える際は、一日100単語×20日+10日で復習するのではなく、一日400単語×5日×6周という形で進めた。
・場所で覚えてしまうと厄介なので、たまに順番を変えるなどを心掛けた。
▼モチベーション観
・出そうと思って出るものではない。
・自分の機嫌は自分でとることが大切。
・自分の場合、数学をやらなきゃいけないなら、その前後に好きな英語や日本史をやるという風に。
・モチベーションが出ないのは脳からのSOSだと考え、上記の方法で対処できない場合は潔く寝ることにしていた。
▼国語観
現代文
・筆者の主張(抽象)と説得力を持たせるための実例(具体)で構成されているイメージ。
・なので、速読する必要がある場合や要約を行う場合は、「例えば」という文言で始まる文章は読み飛ばすなど工夫が必要。
・ただし、筆者の主張が抽象的すぎる場合(芸術論など)は、具体例を用いて考えることが重要だ。
古文
・完全な暗記科目というイメージ。
・文法と単語さえ覚えてしまえばあとは量をこなすだけ。それも、必要な量を過不足なく。
漢文
・古文と同様。但し、漢文の方が登場人物の感情描写が少なく、訓戒的な内容が多いイメージだった。
▼数学観
・自分は数学が苦手だったので、まず学校の定期テスト対策を徹底した。範囲の基本問題の解法を暗記し、演習問題で実際に使う。
・とは言えその本質を理解していなければ応用問題に対応するのは難しいと考え、公式や定理などを自分自身で証明することを重視していた。
▼英語観
単語
・単語は英語力の基礎となるものなので、覚えているものが多ければ多いと考えていた。
・そのため、基本レベルの単語帳を終わらせた後は、時間が許す限りより高い語彙レベルの単語帳に取り組んでいた。
文法
・単語と同様、英語力、より具体的に言えば長文読解の基礎となるもの。
・こちらは、基礎のレベルが入ってしまえば、どんな問題にも対応できると考えた。なぜなら、どれだけややこしい文章でもS,V,Oなどで文構造を理解できれば読み解けるため。
和訳・精読
・精読ができていなければ、多読をしても意味がないと考えて英文解釈の参考書を読みこんだ。
・加えて、自然な日本語を意識していた。なぜなら、採点官も日本人である可能性が高いと考えたため。
和文英訳・自由英作文
・知識をひけらかすというよりは、自分が書きたいことをしっかり書けることが重要と考えた。
・お洒落な表現というよりは、中学レベルの単語や文法でよいからシンプルでわかりやすい表現を心掛けた。
長文
・精読をした上で、多読をすることで速く正確に読めると考えていた。そのため、英文解釈の練習を十分行ったうえで、センター試験の過去問や一橋の過去問を大量に解いた。
・独りよがりな解釈ではいけないと考え、必ず学校の先生に添削をお願いし、認識に齟齬があった場合にはお互いが納得するまで擦り合わせた。
リスニング
・受験におけるリスニングは、日常会話とは明らかに異なるものと考えた。そのため、センターや二次試験の過去問の音源を用いて、シャドウイングやディクテーションを行った。
▼模試観
・模試は現在の自分の立ち位置を知る手段だと考えていた。そのため、結果のみに一喜一憂するのではなく、何が苦手で何ができていないかを把握し、勉強計画に生かすという風に活用していた。
・出題に関して、運という要素もあるので結果が悪くても必要以上に落ち込まないようにしていた。
▼塾観/予備校観
・塾や予備校は、基礎はできるけれど勉強法や勉強計画に関して迷っている生徒が行くところというイメージがあった。そのため、自分は特に困っていなかったこともあり利用しなかった。
▼参考書観/問題集観
・RPGでいうところの自分の能力を上げるアイテムという認識があった。そのため、自分に何が足りないかを考えることで必要な知識や技術を身に着けられると考え、慎重に取捨選択した。
▼友人観
・切磋琢磨する仲間という認識だった。実際、東工大を目指す友人と二次試験直前まで一緒に勉強していた。
▼学校観
・伝手を作る場という認識だった。そのため、出来るだけクラスメートや先生方とは仲良くし、受験期は友人と切磋琢磨し、先生方には過去問の添削などでお世話になった。
▼部活観
・学校と同様、コミュニケーションを取り、人脈を広げる場。
▼日本史観
・日本史は年号や出来事を単体で覚えるというよりは、それぞれの出来事の因果関係を理解することで全体像をつかむ必要があると考えていた。
「【学習観】MIさん(一橋社会)」に関するQ&A
- 受験戦略はどう考えるべきですか?
- 受験戦略は、合格最低点を意識しつつ得意科目で高得点を目指すことが重要です。特に、競争が激しい難関大学では、得意分野での高得点が合格の鍵となります。
- 記憶を定着させるための効果的な方法は?
- 記憶は繰り返しの薄塗りで定着するため、一度に多くを覚えようとせず、少しずつ繰り返すことが効果的です。例えば、1日400単語を6周する方法などが推奨されます。
- モチベーションを維持するためのコツは?
- モチベーションは自分で管理することが大切です。好きな科目を前後に配置することで、やる気を引き出し、必要に応じて休息を取ることも重要です。
- 国語の現代文を効果的に学ぶ方法は?
- 現代文では、筆者の主張と具体例を理解することが重要です。速読や要約の際には、具体例を飛ばす工夫をし、抽象的な内容は具体例を用いて考えると良いでしょう。
- 数学の苦手意識を克服するには?
- 数学が苦手な場合、まずは基礎問題を徹底的に解くことが重要です。公式や定理を自分で証明することで、理解を深め、応用問題にも対応できる力を養います。
- 英語の単語力を向上させるための方法は?
- 単語力は英語力の基礎です。基本的な単語帳を終えた後は、より高いレベルの単語帳に挑戦し、語彙を増やすことが効果的です。
- 模試をどのように活用すべきですか?
- 模試は自分の立ち位置を知るための手段です。結果に一喜一憂せず、苦手分野を把握し、次の勉強計画に活かすことが重要です。
- 塾や予備校の役割は何ですか?
- 塾や予備校は、基礎ができているが勉強法に迷っている生徒にとって有効です。自分に合った学習法を見つけるためのサポートを受ける場として活用できます。
- 参考書や問題集を選ぶ際のポイントは?
- 参考書や問題集は、自分の能力を向上させるためのアイテムです。必要な知識や技術を身につけるために、自分に合ったものを慎重に選ぶことが大切です。
- 日本史を効率よく学ぶための方法は?
- 日本史は年号や出来事を単体で覚えるのではなく、因果関係を理解することが重要です。全体像をつかむために、出来事の関連性を意識して学習しましょう。