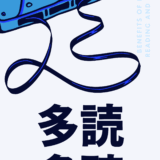はじめに
中学受験で第一志望に入れなかった、高校受験で失敗した・・・。
そんな意気消沈している人に向けて希望を伝えるために書きました。
大学受験でゲームチェンジが起こる
中学受験や高校受験で”失敗”したと思っている人は意外と多いのではないかと推測します。
しかし、安心してください。大学受験からゲームチェンジが起こります。
中学受験や高校受験のルールでは評価されなかったかもしれませんが、大学受験のルールであれば勝負できるかもしれません。いや、大学受験には、中学受験や高校受験以上に勝ち筋がたくさんあります。
中学受験で失敗し、医学部に合格したケース
中学受験と大学受験は、全く別のゲームだと思ってください。
英語が必要、暗記重視、推薦入試などの多様な選考方法がある・・・等々、大学受験独自の特徴が多数あります。松濤舎の生徒でも、中学受験で第2志望以下に進学したが現役で医学部合格している子は多数います。例えば、第一志望の中学ではもらえないような高い評定をもらい推薦入試で合格したり、英語対策を重視することで大学受験で有利になったり、中学受験時に通っていたような集団授業はやめて演習メインで進めた結果飛躍的に成績を伸ばしたケースなど、枚挙にいとまがありません。
いずれも、大学受験のルールを改めて学び直し、その上で最適な対策取れたから得た合格です。中学受験での合格経験を引きずっていたら、大学受験に最適化した対策はできなかったことでしょう。
高校受験で失敗し、医学部に合格したケース
高校受験と大学受験も、また全く別のゲームになります。
演習重視、パターン整理の重視、英語重視・・・といった特徴が大学受験にはあります。もし高校受験でうまくいかなかったという自覚があるなら、改めて大学受験に最適な方法で勉強していくことでやり直しが効きます。
大学受験からやり直せる。いや、やり直そう。
中学受験や高校受験で成功した人も、大学受験から頭を切り替える必要があります。
僕自身、高校受験での経験を引きずったことが、東大受験に悪影響を及ぼしていました。
英語:高校受験より英語は10倍以上重要だったが、それに気づくのが遅かった。
数学:高校受験より解法整理が重要だったが、体系化への意識が低く、無闇に演習を追加していた。
化学:高校受験より応用レベルの問題演習をすべきだったが、典型問題に留めていた。
生物:高校受験より教科書の読み込みが重要だったが、あまり行わなかった。
国語:高校受験より重要度が低かったが、時間をかけて勉強してしまっていた。
このように、中学受験や高校受験での成功・失敗によらず、改めて大学受験に最適な勉強を組み直す直す必要があるのです。
大学受験は「学習指導要領の範囲から出題される」
大学受験のルールブックがあるとして、1ページには何が書いてあることはこれです。
大学受験は、学習指導要領の範囲から出題される
これこそが、大学受験の原理原則です。
特に医学部・上位校受験生は、学習指導要領を超えたマニアックな知識や難しい解法を入れることに時間を使い、合格につながらない誤った努力をしていることが多いです。
逆に、学校から配られた簡単な問題集(4STEPなど)や、基本的な問題集(基礎問題精講など)だけをやっていて、学力が合格水準に達しないケースも多々あります。
タイルを敷き詰めるように、学習指導要領の範囲を徹底する
という意識を持つことが、とにかく重要なのです。
東大ですら、学習指導要領の範囲を超えた出題はしません。東大受験生は「教科書に載っている知識は何が問われても文句が言えない」と考え、教科書範囲を徹底的にやり込みます。であれば、他大学を志望する生徒はなおさら教科書範囲以外を勉強する合理的理由はありません。
追うべき指標は「全統記述模試の偏差値」
学習指導要領の範囲の徹底具合が測れるのが、全統記述模試の偏差値です。
なぜなら、全統記述模試は原則、学習指導要領の範囲内からしか出題されないからです。
そのため、医学部・上位校受験生は全統記述模試の偏差値を見ながら進めていくことになります。
偏差値は「問題集の習得レベル」が決める
全統記述模試の偏差値を上げるには、教科書傍用問題集を中心とした「学習指導要領の範囲を網羅的する問題集」を徹底するに尽きます。この網羅度を、独自指標にしたのが「松濤舎の習得レベル」であり、習得レベルを上げることが目下の目標となります。
医学部・上位校合格者の当たり前を徹底せよ
これまでの内容をまとめると、
学習指導要領の範囲を徹底するために、教科書傍用問題集を徹底し、習得度合いを全統記述模試の偏差値で測定する。
これが、医学部・上位校合格者にとっての”当たり前”です。
あとは、当たり前を人より徹底するだけです。
希望はあります。正しいやり方もあります。
気持ちを切り替えて、やるだけなのです。
保護者の方へ
中学受験・高校受験での経験を、保護者の方が引きずってしまっているケースも多いです。
生徒本人はすでに切り替えているのに、保護者の方が当時の話をしてしまう、それが生徒を大きく傷つけてしまう・・・。
こういったことが起こらないよう、大学受験では保護者の方の役割も大きく変わることをご認識ください。
以下の記事が参考になります。
お問い合わせフォーム
こちらからもお問い合わせいただけます。