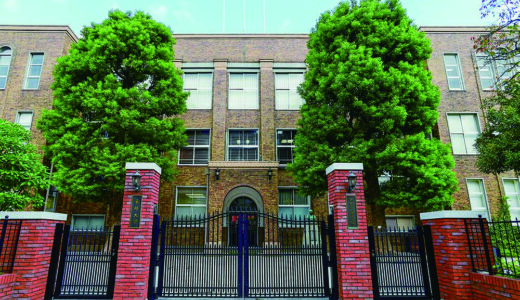医学部偏差値ランキングで、最新の難易度を把握しましょう。
河合塾から駿台まで、五大予備校の偏差値データや共通テスト得点率が比較できます。
学費や地域枠の違いまで網羅した決定版ガイドで、自分に合う医学部を見つけましょう。
1. 医学部偏差値ランキングの見方
医学部の出願校決めや学習計画の調整に偏差値は最も重要な役割を果たします。しかし、医学部偏差値ランキングは、各予備校によって異なります。これは受験者層の違いや出題内容、算出方法が異なるためです。
ここでは、「医学部偏差値ランキングの決定版」として最新の偏差値情報を網羅的に集めました。予備校5社(松濤舎、河合塾、駿台、東進、ベネッセ)を比較することで、偏りなく偏差値ランキングを把握することができます。
偏差値ランキングには、以下の項目があります。
記述模試偏差値ランキング(国公立医学部+私立医学部)
国公立・私立含めた総合での偏差値ランキングです。特に国公立医学部・私立医学部併願者にとって、出願校決めの際の参考となる偏差値・ランキングです。予備校によって偏差値の定義が異なる点に注意が必要です。
記述模試偏差値ランキング(国公立医学部のみ)
国公立医学部のみの偏差値ランキングです。国公立医学部専願者や、国公立医学部出願先の参考に活用できます。予備校によって偏差値の定義が異なる点に注意が必要です。
記述模試偏差値ランキング(私立医学部のみ)
私立医学部のみの偏差値ランキングです。私立医学部専願者や、私立医学部出願先の参考に活用できます。予備校によって偏差値の定義が異なる点に注意が必要です。
共通テスト得点率ランキング
国公立医学部の共通テスト得点率ランキングです。ランキングも大事ですが、ここでは得点率自体を参考にしながら、出願に必要な共通テスト得点率がどれくらいか把握しましょう。予備校によって得点率の定義が異なる点に注意が必要です。
共通テスト偏差値ランキング
国公立医学部の共通テスト偏差値ランキングです。共通テストは偏差値より得点率のほうが重要ですが、志望校の難易度を総合的に把握する際の1つの指標として活用してみてください。予備校によって偏差値の定義が異なる点に注意が必要です。
まとめ記事を読む
以下の記事に、上記項目に関する予備校5社の最新データが全て掲載されています。まずは以下の記事を読み、全体感を把握しましょう。
2. 医学部偏差値ランキングTOP10〈国公立編〉
国公立医学部のみの偏差値ランキングTOP10をご紹介します。詳細データについては各大学の詳細ページをご覧ください。
順位|大学名|松濤舎偏差値|所在地|学費6年概算|備考
1|東京大学〈理三〉|76.7|東京|約350万円
2|京都大学|75.3|京都|約350万円
3|大阪大学|73.5|大阪|約350万円
4|東京医科歯科大学|72.6|東京|約350万円
5|名古屋大学|71.4|愛知|約350万円
6|九州大学|71.3|福岡|約350万円
7|千葉大学|70.4|千葉|約350万円
8|大阪公立大学|70.4|大阪|約350万円
9|東北大学|70.2|宮城|約350万円
10|奈良県立医科大学|70.2|奈良|約350万円
3. 医学部偏差値ランキングTOP10〈私立編〉
私立医学部のみの偏差値ランキングTOP10をご紹介します。詳細データについては各大学の詳細ページをご覧ください。
順位|大学名|松濤舎偏差値|所在地|学費6年概算|備考
1|慶應義塾大学|73.0|東京|約2,220万円
2|東京慈恵会医科大学|69.4|東京|約2,250万円
3|日本医科大学|68.6|東京|約2,200万円
4|順天堂大学|68.5|東京|約2,080万円
5|国際医療福祉大学|67.9|千葉|約1,850万円
6|関西医科大学|67.9|大阪|約2,100万円
7|大阪医科薬科大学|67.4|大阪|約2,910万円
8|東京医科大学|66.4|東京|約2,940万円
9|昭和大学|66.4|東京|約2,400万円
10|東邦大学|66.2|東京|約2,580万円
*自治医科大は学費貸与方式、卒後9年間の勤務で返還免除。
4. 地域別医学部偏差値ランキング(関東・近畿・東海ほか)
地域別の医学部偏差値ランキングは以下です。
〈関東トップ5〉東京大学/慶應義塾/東京科学/東京慈恵会医科/日本医科
〈近畿トップ5〉京都大学/大阪大学/大阪公立大学/神戸大学/京都府立医科大学
〈東海トップ5〉名古屋大学/名古屋市立大学/三重/浜松医科/岐阜
関東地方
近畿地方
東海地方
5. 医学部共通テスト得点率ランキングTOP10〈国公立編〉
順位|大学名|松濤舎得点率|所在地|学費6年概算|松濤舎偏差値
1|東京大学〈理三〉|91%|東京|約350万円|76.7
2|京都大学|89%|京都|約350万円|75.3
3|東京科学大学|88%|東京|約350万円|72.6
4|大阪大学|88%|大阪|約350万円|73.5
5|横浜市立大学|87%|神奈川|約360万円|70.1
6|山梨大学(後期)|85%|山梨|約350万円|68.2
7|神戸大学|87%|兵庫|約350万円|70.2
8|千葉大学|85%|千葉|約350万円|70.4
9|九州大学|87%|福岡|約350万円|71.3
10|名古屋大学|87%|愛知|約350万円|71.4
6. 医学部共通テスト偏差値ランキングTOP10〈国公立編〉
順位|大学名|駿台偏差値|所在地|学費6年概算
1|東京大学〈理三〉|84.0|東京|約350万円
2|京都大学|83.0|京都|約350万円
3|大阪大学|80.0|大阪|約350万円
4|東京科学大学|80.0|東京|約350万円
5|九州大学|76.0|福岡|約350万円
6|山梨大学〈後期〉|76.0|山梨|約350万円
7|東北大学|76.0|宮城|約350万円
8|名古屋大学|76.0|愛知|約350万円
9|横浜市立大学|75.0|神奈川|約360万円
10|神戸大学|75.0|兵庫|約350万円
7. 医学部偏差値ランキングの活用ステップ5
①現状の偏差値帯を確認
まずは記述模試を受験し、自身の偏差値を把握することから始めます。松濤舎としては松濤舎の偏差値(≒全統記述模試の合格者の平均偏差値)を指標にすることを推奨していますので、全統記述模試以外を受験した場合は「5社比較」で松濤舎の偏差値に対応させてみてください。
②志望校の偏差値帯、共通テスト得点率を確認
併せて志望校の偏差値も確認してみてください。これも松濤舎の偏差値を確認することを推奨しますが、他者の偏差値も含めて総合的に判断してみてもよいです。国公立医学部の場合は同じくらい共通テストの得点率が重要になります。これも松濤舎の指標である「合格者の共通テスト平均得点率」を使用すると固く出願できます。
③学費・立地で最終フィルタリング
偏差値も共通テスト得点率も目指せそうな大学であれば、学費や立地でフィルタリングしましょう。学費的に厳しい大学は早めに切っていいですが、立地に関しては”贅沢が言えない”こともあると思いますので、ある程度は妥協することも視野に入れましょう。
④合格最低点を確認、科目別の目標点を設定
進学可能であり、進学したいと思える大学が絞れたら、次に合格最低点を確認します。国公立医学部の場合は「総合点=共通テスト+ニ次試験」の合格最低点を確認します。ここから、共通テストの得点率に相当する点数を引くと、ニ次試験で取るべき各科目の点数が算出できます。あとはこれを、自分の得意・不得意を踏まえて目標点を設定します。目標点は「合格最低点をギリギリ上回る程度」で設定するのがポイントです。
⑤過去問演習の開始
これで準備完了です。あとは過去問演習を通して合格最低点を再現性を持って上回れるようにするだけです。松濤舎の偏差値(=全統記述模試の合格者平均偏差値)を超えていれば、過去問演習を繰り返せば基本的に合格最低点を超えるようになります。超えない科目がある場合は目標点を間違えている可能性があるので、この時点で調整します。そもそも松濤舎の偏差値を超えていない場合は、いくら過去問演習を重ねても合格最低点は超えないので、過去問演習を止め、偏差値が上げられるよう問題集の習得レベルを上げることに時間を使いましょう。
8. FAQ|医学部偏差値ランキングでよくある質問
- 医学部偏差値ランキングは毎年どれくらい変動しますか?
- 平均±0.5pt程度です。ただし、学費変更や地域枠拡大、定員変更がある大学は ±2ポイント動くことがあります。
- 共通テスト得点率の91%や85%は何を示していますか?
- 松濤舎では「合格者の平均得点率」、河合塾では「合格可能性50%ライン(ボーダー)」、駿台・ベネッセでは「B判定(合格60〜70%)」、東進では「合格80%ライン」を掲載しています。判定基準が違うため同じ得点率でも意味合いが異なる点に注意してください。
- 模試間で偏差値が3ポイント以上違うのは普通?
- はい。河合塾は全受験層、駿台は上位層が多いため、駿台<河合塾になりやすいです。
- 松濤舎の医学部偏差値ランキングは、どの模試データを使っていますか?
- 河合塾の全統記述模試で毎年公表される「合格者の平均偏差値」を5 年以上蓄積し、独自に調整して作成しています。単一年度・単一模試のボーダー値ではありません。
- 松濤舎偏差値の“独自調整”とは何をしているのですか?
- 河合塾の全統記述模試の過去5年以上の合格者平均を平均化し、年度間の出題難度差を補正しています。これにより「その偏差値が取れれば平均的な合格者レベル」という実力指標になります。
- ランキングには国公立と私立が混在していますが、同じ偏差値で難易度は比較できますか?
- いいえ。私立医学部の偏差値は比較的低めに出ている感覚があります。2~3pt低めに出ていると思って捉える必要があります。また、共通テスト配点や二次試験科目は大学ごとに違うため、最終的な合格可能性は個別に確認してください。
- 河合塾サイトの偏差値と松濤舎の偏差値がずれているのはなぜ?
- 河合塾が公表しているのは「ボーダー偏差値(合格50 %ライン)」です。松濤舎版は「合格者の平均偏差値」を使っており、ボーダーより1–3 ポイント程度高く出るのが普通です。
- ランキングはいつ更新されますか?
- 各予備校の最新情報がリリースされ次第、随時反映します。年度内に難度変動が大きい大学(定員増減・入試改革など)も臨時更新を行います。
- 年によって順位が上下するのは何が原因ですか?
- 共通テスト配点の変更、特色選抜の新設、定員増減、出題傾向の難化・易化が主因です。特に地域枠の拡大や推薦枠増、学費変更は偏差値を2 ポイント以上動かすことがあります。
- 医学部偏差値ランキングで安全圏はどう判断すればいい?
- 目安として、松濤舎偏差値以上であることが安全圏です。合格者平均で合格できる水準にあることを意味します。共通テストに関しては、松濤舎の共通テスト得点率以上が安全圏ですが、共通テストに関しては-3%以内なら許容範囲と考えていいです。
- 偏差値が同じ大学でも共通テスト得点率が違うのはなぜ?
- 共通テストの配点割合と科目難度が大学ごとに異なるためです。配点が高い大学ほどボーダー得点率が高く設定されています。例として横浜市立大は共テ配点が高く91%が目安です。
- 大学別の詳細(学費・配点・過去問など)はどこで確認できますか?
- ランキング表の大学名リンクから個別ページに飛べます。そこに学費、共通テストボーダー、二次配点、過去3 年の合格最低点などをまとめてあります。